記事・レポート
人はなぜ旅をするんだろう?
旅の本、いろいろ 〜好きな本がみつかる、ブックトーク
カフェブレイクブックトーク
更新日 : 2014年04月15日
(火)
第8章 旅の移動手段あれこれ(2)
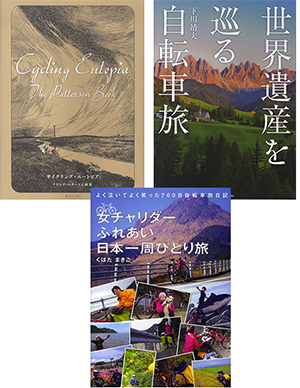
澁川雅俊: 自転車旅行の本はあまり多くありませんが、まず『サイクリング・ユートピア』(フランク・パターソン/文遊社)を最初に挙げなければなりません。子どもの頃から自然に親しみ、周囲の風景をスケッチするのが好きだった英国人が19世紀末に大流行した自転車に魅せられ、自転車で自宅近郊を散策し、広く英国各地をサイクリングしたときの風景をペンで描き残しました。この本は、その数千点のペン画の中から選り抜かれたスケッチの画集です。その雰囲気が自転車で気ままに走り回る趣味とうまくマッチしていて、ほのぼのとした気持ちにさせてくれます。
一人の元製鉄会社研究員が退職後に世界54か国、約5万kmを自転車で訪ね『世界遺産を巡る自転車旅』(下川靖夫/パレード)をだしました。これは、肺がん闘病に挑戦する71歳・25年間の軌跡です。『女チャリダーふれあい日本一周ひとり旅』(くぼたまきこ/イカロス出版)は、岡山から四国へ、四国で88ヵ所の霊場を回り九州へ、さらに沖縄諸島を回り、鹿児島、富山、北海道へと走り、岡山に戻った日本一周の、女ひとり、700日間のチャリの旅の本です。
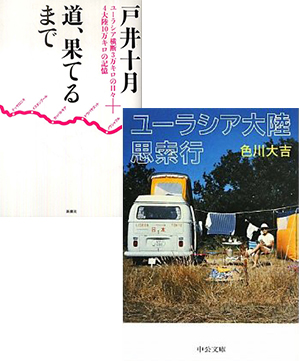
『道、果てるまで』(戸井十月/新潮社)はバイク旅の本です。作家活動のかたわらで、映画監督とドキュメンタリーディレクターの顔も持つ著者はいわゆるバイク野郎なのでしょう。1983〜2009年まで26年間も走り続け、既に30万kmを走破しています。その上で、今回は副題にある「ユーラシア横断3万キロの日々+4大陸10万キロの記憶」を本にしました。こうなると「旅をする」ではなくて「冒険する」でしょうね。大学教授で、自分史編纂の提唱者、一般民衆史の研究者でもある色川大吉は、一台のキャンピングカーに所帯道具を積み込んで、仲間たちと一緒にポルトガルのリスボンからインドへと108日間4万kmの旅をし、『ユーラシア大陸思索行』(中央公論新社)を書きました。この旅で彼は「文明とは何か」を問い、生き甲斐を求めながら、山々を越え、茫漠たる砂漠を走り抜いたなどと言っていますが、思索を常とする学者でも、旅をしないとそれらの問いへの答えは得られないのでしょうか。それは皮肉ではなく、このブックトーカーの純粋な疑問です。
現代の旅でも歩き旅、自転車旅、バイク旅があることは以上でわかりましたが、鉄道や飛行機で旅をするのが一般的でしょう。『鉄道旅行の歴史』(ヴォルフガング・シヴェルブシュ/法政大学出版局(新装版))は、産業革命以降の鉄道の発展を空間と時間の工業化としてとらえ、その中で草創期の鉄道旅行の市民的体験から交通文化史を編み、さらに進んで旅の思想史を構成しています。学術書なのでテキストを読むのに少し苦労しますが、多数掲載されている版画や写真の図版が興味をそそります。それらが何を語っているのかを拾い読みするだけでも面白い本です。
一方『鉄道大バザール』(ポール・セルー/講談社)は本格的な鉄道旅行記です。著者は米国の小説家ですが、彼は世界中の鉄道を徹底的に乗りまくって汽車旅を楽しみました。まずロンドンからオリエント急行で欧州を通り過ぎて中近東へ、そこからインドそして東南アジアを一回りして、日本へ。日本では各種の新幹線を乗り継ぎ、東京から札幌、東京から関西へと駆けめぐり、帰路はシベリア鉄道を経由してロンドンへと、四ヶ月の旅をしたのです。その間この作家が何を見聞きし、何に感動したか、そして何を思索したかが書かれていますが、それを文化勲章受章作家の阿川弘之が情感を込めて邦訳しています。なおその初出は1977年(原作は75年)ですが、汽車旅記の古典として最近文庫化されました。
一方『鉄道大バザール』(ポール・セルー/講談社)は本格的な鉄道旅行記です。著者は米国の小説家ですが、彼は世界中の鉄道を徹底的に乗りまくって汽車旅を楽しみました。まずロンドンからオリエント急行で欧州を通り過ぎて中近東へ、そこからインドそして東南アジアを一回りして、日本へ。日本では各種の新幹線を乗り継ぎ、東京から札幌、東京から関西へと駆けめぐり、帰路はシベリア鉄道を経由してロンドンへと、四ヶ月の旅をしたのです。その間この作家が何を見聞きし、何に感動したか、そして何を思索したかが書かれていますが、それを文化勲章受章作家の阿川弘之が情感を込めて邦訳しています。なおその初出は1977年(原作は75年)ですが、汽車旅記の古典として最近文庫化されました。
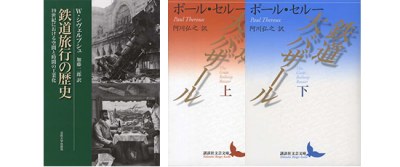

日本の作家も『西の果てまで、シベリア鉄道で』(大崎善生/中央公論新社)旅をしました。シベリア鉄道でユーラシア大陸を横断し、その西の端にあるリスボンまで汽車に乗り、途中であちこちに立ち寄り遊び回りました。そして「旅はある意味では作家としては欠かせない語彙と体験の補充の場なのかもしれない。新しい何かに出会い、こころ動かされ、それを言葉で表現するとき、自分の中にいくつかの新しい言葉の組み合わせが生まれていく」なんて、気の利いたセリフを吐いています。でも帰路は、汽車に乗るのに飽きてしまい、飛行機で、なんてまったくつや消しです。
面白いのは『時刻表に載っていない鉄道に乗りにいく』(遠森慶/ 講談社)です。なにが面白いって、SLならまだしも軽便鉄道やトロッコや場鉄(馬が引く鉄道車)や人鉄(人が引く鉄道車)に乗るマニアック鉄道遊びの本なのですから。しかも驚かされるのは、日本にそんな鉄道が少なくとも36ヵ所あるというのですから。旅行ライターならではの本ですね。
関連リンク
人はなぜ旅をするんだろう? インデックス
-
第1章 本の中の旅
2014年03月26日 (水)
-
第2章 昔の旅にタイムスリップ
2014年03月28日 (金)
-
第3章 数奇な冒険・探検記
2014年04月01日 (火)
-
第4章 「山のあなた」に、何かが見つかる?
2014年04月03日 (木)
-
第5章 巡礼・お遍路・ピルグリム
2014年04月04日 (金)
-
第6章 我、辺境・異郷を愛す
2014年04月07日 (月)
-
第7章 旅の移動手段あれこれ(1)
2014年04月08日 (火)
-
第8章 旅の移動手段あれこれ(2)
2014年04月15日 (火)
-
第9章 旅の移動手段あれこれ(3)
2014年04月17日 (木)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













