本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年9月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の”いま”が見えてくる。
新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介します。
今月の10選は、『つくるをほぐす -完成を目指さないものづくりで学びとアイデアを生み出す「造形対話」 』『会話の0.2秒を言語学する』など。あなたの気になる本は何?
※「本から「いま」が見えてくる新刊10選」をお読みになったご感想など、お気軽にお聞かせください。
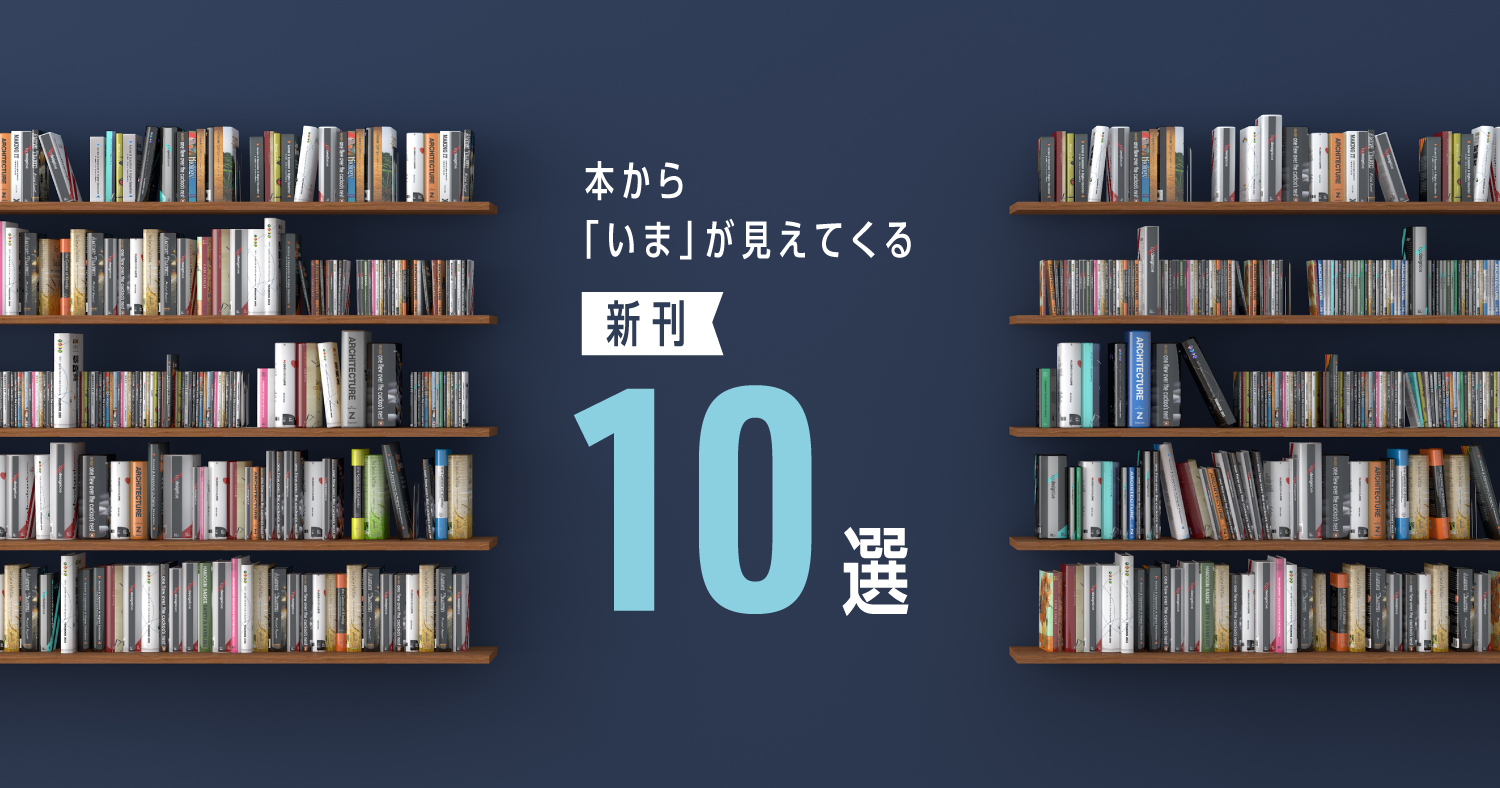
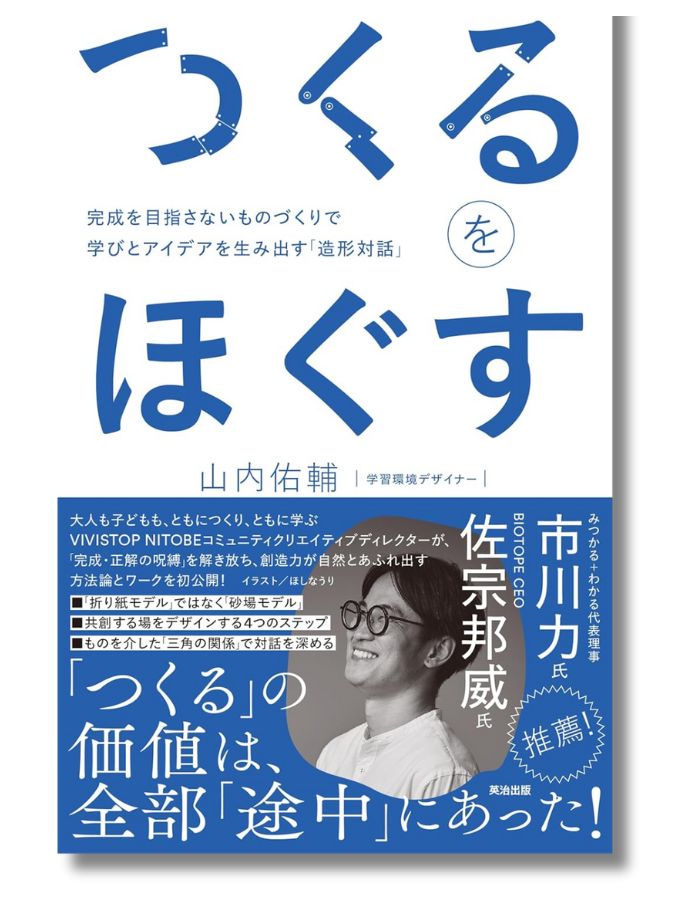
完成を目指さないものづくりで学びとアイデアを生み出す「造形対話」
あなたなら「つくる」をどう説明しますか?と著者は問いかけますが、日頃からつくることに関わっていない人にとっては、案外答えにくい質問ではないでしょうか。
本書では、折り紙で鶴を折る時のように、手順とゴールが決まっている作り方を「折り紙モデル」、一方砂場で遊ぶように何ができるか決まっておらず、作りながら考えるような創作を「砂場モデル」と呼びます。そして、学校の図工の時間も、広く言えば世の中も「折り紙モデル」に偏っている現状を危惧し、「砂場モデル」のつくりかた、学びかたを提案・実践していきます。
「つくる」の先には何かが「出来上がる」ことが想定されるのが一般的です。しかし、既存のゴールや外見上の美しさ、技術的なうまさだけを追求するだけでは、こどもにしても大人にしても、自由な発想は育まれないでしょう。
そんな中で、著者はつくる「過程」の中に重要性を見い出していきます。そこには創作物を間に挟んだコミュニケーションやフィードバックがあり、それを受けまた創作物は変化していく。その一連の過程を「造形対話」と名づけ、人と人とのやりとりを通じて新しい物事の見方を発見したり、相互に理解を深めたりする手法として実践しています。
「つくる」力すなわちは創造力は、個人の能力として、または新しいモノやサービスを世の中に生み出す力として重視されているきらいがありますが、本書では、「つくる」ことはそのプロセスを通じて人と人が関わることを重視しています。「共創」という言葉もよく聞かれますが、つくることとは本来必然的に「共創」である、と捉え直せるかもしれません。
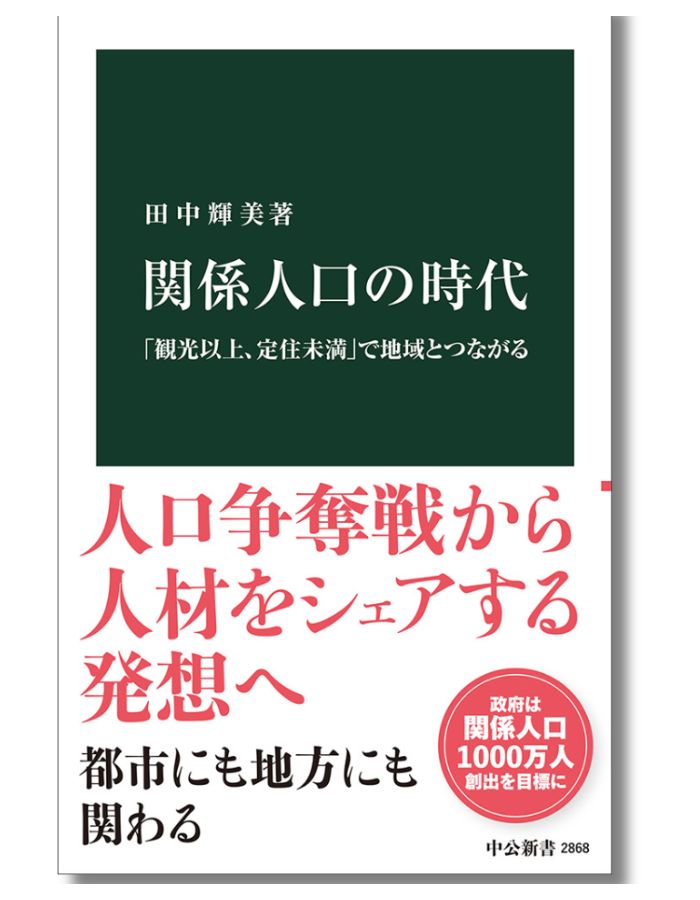
関係人口の時代
「観光以上、定住未満」で地域とつながる
人口減少という大きな社会課題に向き合う中で行政からも注目され、地域づくりに関わる人たちに限らず広く知られるようになった「関係人口」という言葉。著者は、ローカルジャーナリストという肩書で地元島根を拠点に活動する田中輝美氏。関係人口を主題にした本を過去に2冊出版もしています。本書ではあらためて「関係人口」という言葉の意味するところを整理し、豊富な事例と取材経験をもとに、関わっていく側、受け入れる側双方の視点で、今後の関係人口のあり方について論じています。関係人口は、人口減少時代の暮らし方、生き方のひとつとして捉えなおしてみると、その実態が見えてくるかもしれません。
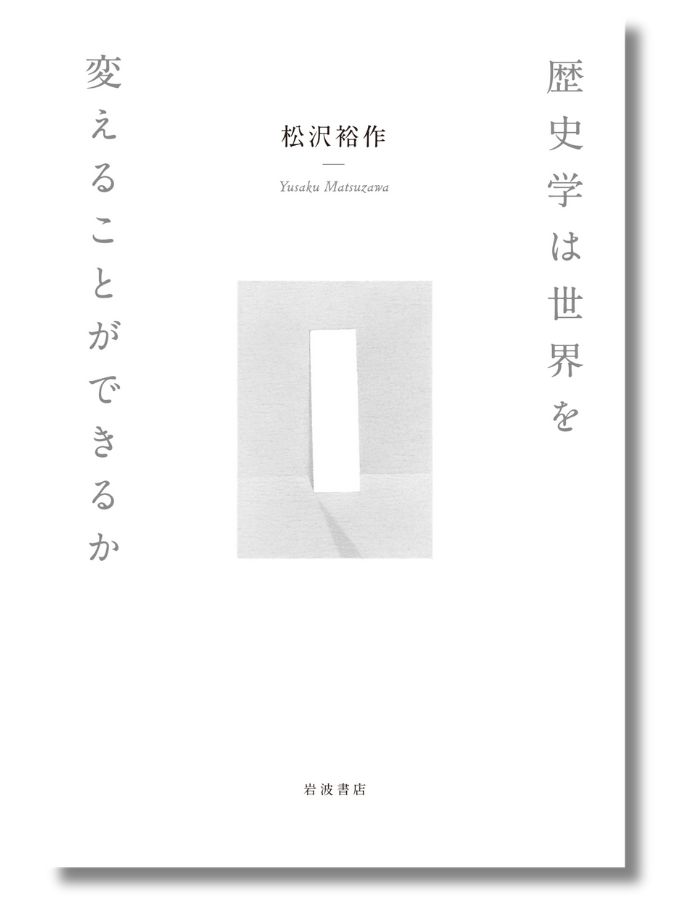
歴史学は世界を変えることができるか
私たちが知っている歴史とは、さまざまな歴史家たちが過去の出来事を調査し、解釈しながら紡いできたものの総体である、ということは意外と気づきにくい事実かもしれません。著者は、そんな歴史家たちの営みにスポットを当てながら、歴史学とは社会の何に寄与できるのか、と問いかけていきます。確定的なもののように思われる歴史も、どの時代のどんな人が論じるかによって違った様相を見せ、揺らぎや別の視点があることがよくわかります。歴史学の見方が変わる一冊です。
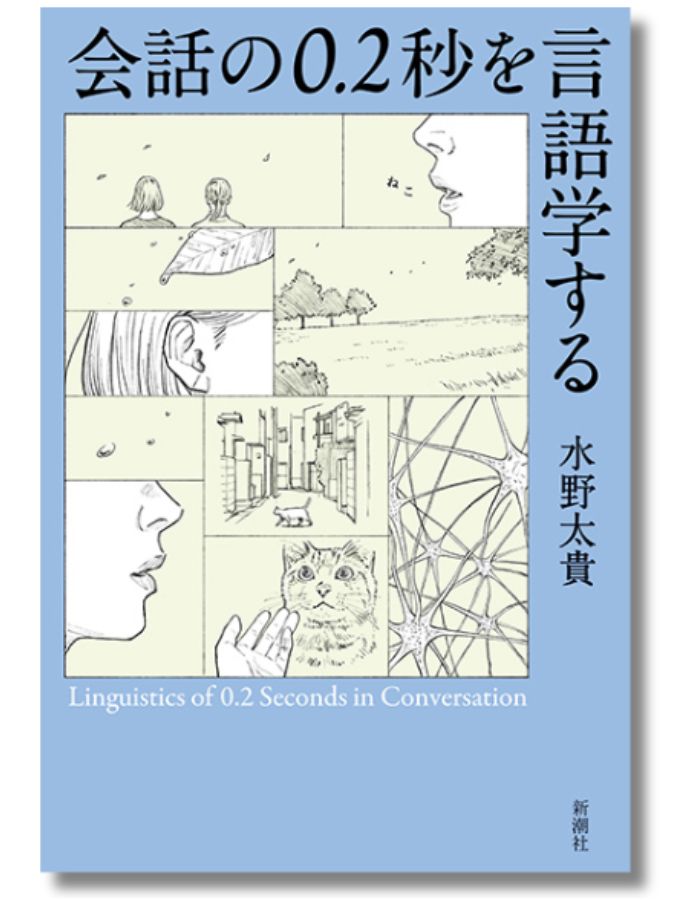
会話の0.2秒を言語学する
この10選でもよく取り上げている「ことば」や「言語」の本。毎月のように興味深い本が出版され、専門領域を越えて親しまれるようになっています。本書の著者は、普段は出版社で勤務しながら、登録者数30万人を超える言語学のYouTube番組も運営。非研究者だからこその間口の広さや楽しむ姿勢は本書からもよく伝わってきます。メールにLINEにスラックなど、テキストだけでも多様なツールを使い分け、それぞれ独特の言葉のやりとりが存在する昨今。本書のテーマである「会話」、あるいは言葉そのものについて考えることは、多様化する人間関係や社会関係を考えることとつながっているのかもしれません。
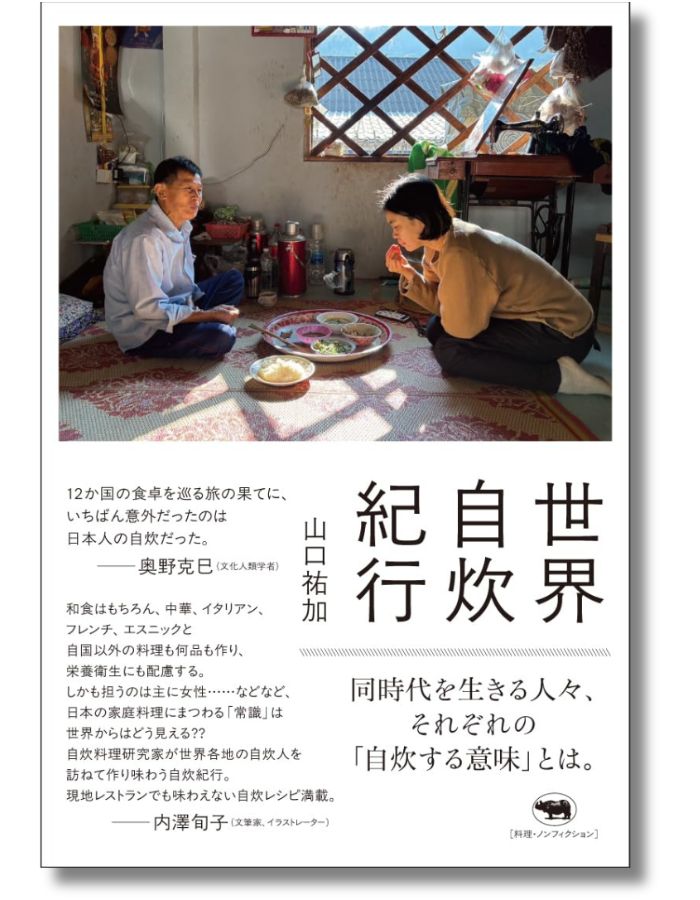
世界自炊紀行
「自炊料理家」という肩書きを持つ著者が、2024年の間に全世界12ヵ国38家庭を取材し、各国から2家庭、合計24の「いつものごはん」の現場の様子を収録した紀行文。自炊文化はどの国にもありますが、多くの家庭では“お母さん”がご飯をつくり、一人暮らしのマンションにもキッチンがあり、中華やイタリアンなどさまざまなメニューの選択肢がある日本の自炊事情は、どこまで「あたりまえ」なのか。文化人類学のように、他文化との比較を通じて自国文化をよく知ることができる、学びの多い一冊です。
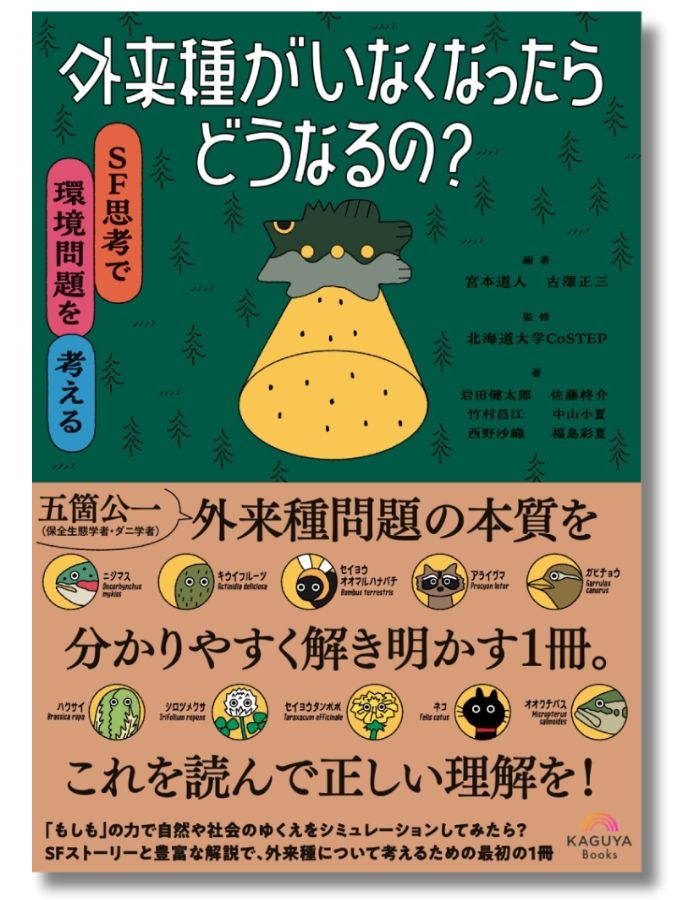
外来種がいなくなったらどうなるの?
SFプロトタイピングの手法で外来種問題を考える、というユニークな本書は、北海道大学CoSTEP(科学技術コミュニケーション教育研究部門)のライティング編集実習として、教員のサポートを受けながら受講生たちが中心となってつくられたもの。「もしも北海道の外来種が倍増したら?」「もし在来種あわれみの令がでたら?」などのSF小説の設定のような問いを立て、その結果を検討していくことで、自然と人間社会の関わりの複雑さを描いていきます。SF思考と外来種問題、両方の入り口となる1冊。
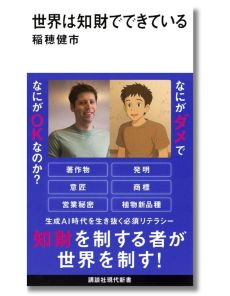
世界は知財でできている
知財、すなわち「知的財産」(または「知的財産権」)の現状と今後について、はじめてこの分野に触れる人にもやさしく、かつ網羅的にまとめられた一冊。最近ではジブリ風のイラスト画像がSNSで一気に広まったことも記憶に新しいですが、生成AIの登場により各国は知財をめぐる対応を迫られています。日常的に生成AIを使用するようになりつつある昨今、知財についてのリテラシーはビジネスシーンや専門家にとってだけでなく、日常生活においても重要となっていきそうです。
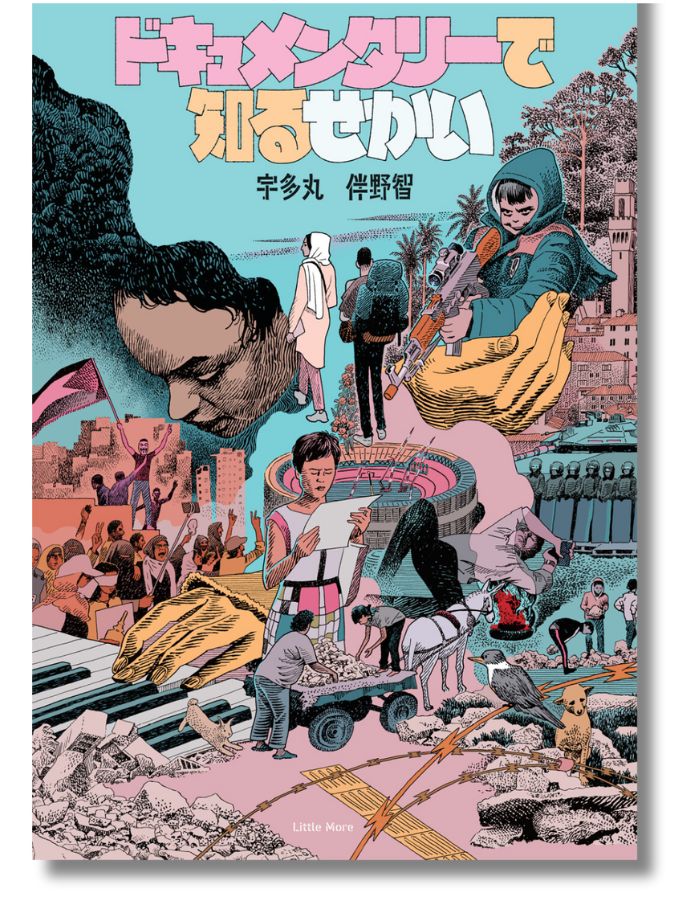
ドキュメンタリーで知るせかい
ラジオ番組のコーナーが発端となってできた本書。戦争、ジェンダー、環境などをテーマとした章立てで、昨今の世界の姿を切り取ったドキュメンタリー映画作品31作を紹介しています。それぞれの作品の興味深さもさることながら、ラッパーである宇多丸氏と、ドキュメンタリー映画の動画配信サービスを運営する伴野氏の率直な言葉からは、作品の解説だけでなく“ドキュメンタリーの観客”としての私たちのあり方についても考えさせられます。
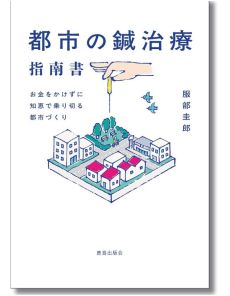
都市の鍼治療指南書
お金をかけずに知恵で乗り切る都市づくり
ブラジル・クリチバの都市計画は、世界的に賞賛された成功事例として知られています。その立役者である当時の市長ジャイメ・レルネルは、都市の課題を解決していく様子を鍼治療になぞらえ、「ツボに鍼を刺すように」大きな効果を生むポイントをおさえたアクションを積み重ねてきました。本書は、レルネルと親交が深かった著者がその哲学を引き継ぐ形で、世界各地の鍼治療的な都市の課題解決の事例を集めたもの。都市をより良くするための8つの「ツボ」を軸に、交通や環境などの課題がどう乗り越えられてきたかを紹介。都市づくりにとどまらず、日々の仕事や生活にも効きそうなヒントが詰まっています。
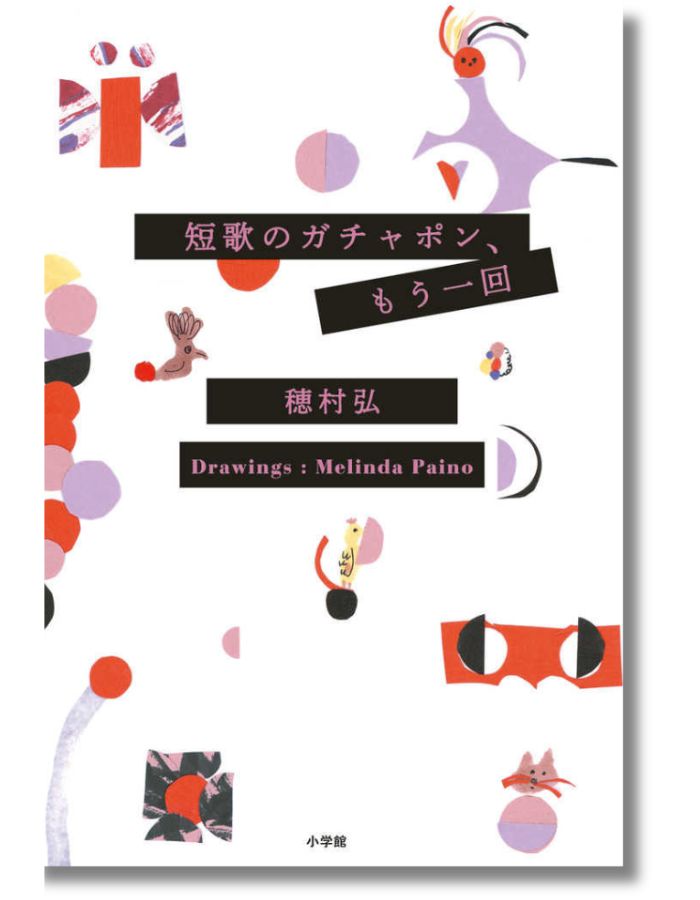
短歌のガチャポン もう一回
歌人でありエッセイストであり、さまざまな歌人や短歌作品を世に紹介するキュレーター的な顔も持つ穂村弘氏が選定した、明治から令和までの短歌100選。見開きの右ページには短歌作品、左には穂村の解説というシンプルな構成で、ガチャポンを回した時のように次から次へと短歌が現れてきます。現在でも20-30代を中心に根強い人気が続く短歌は、その時代の気分や空気感を閉じ込めたカプセルのよう。それを開封していくような穂村の解説も楽しく読めますが、自分なりにも読み解きたくなります。「もう一回」とあるように本書が第2弾ですが、気にせずに楽しめます。
つくるをほぐす 完成を目指さないものづくりで学びとアイデアを生み出す「造形対話」
山内佑輔英治出版
関係人口の時代 「観光以上、定住未満」で地域とつながる
田中輝美中央公論新社
歴史学は世界を変えることができるか
松沢裕作岩波書店
会話の0.2秒を言語学する
水野太貴新潮社
世界自炊紀行
山口祐加晶文社
外来種がいなくなったらどうなるの? SF思考で環境問題を考える
監修:北海道大学CoSTEPKaguya Books
世界は知財でできている
稲穂健市講談社
ドキュメンタリーで知るせかい
宇多丸、伴野智リトルモア
都市の鍼治療指南書 お金をかけずに知恵で乗り切る都市づくり
服部圭郎鹿島出版会
短歌のガチャポン、もう一回
穂村 弘小学館
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













