本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。
新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介します。
今月の10選は、『自然資本とデザイン』や『中国Tik Tok民俗学』など。あなたの気になる本は何?
※「本から「いま」が見えてくる新刊10選」をお読みになったご感想など、お気軽にお聞かせください。
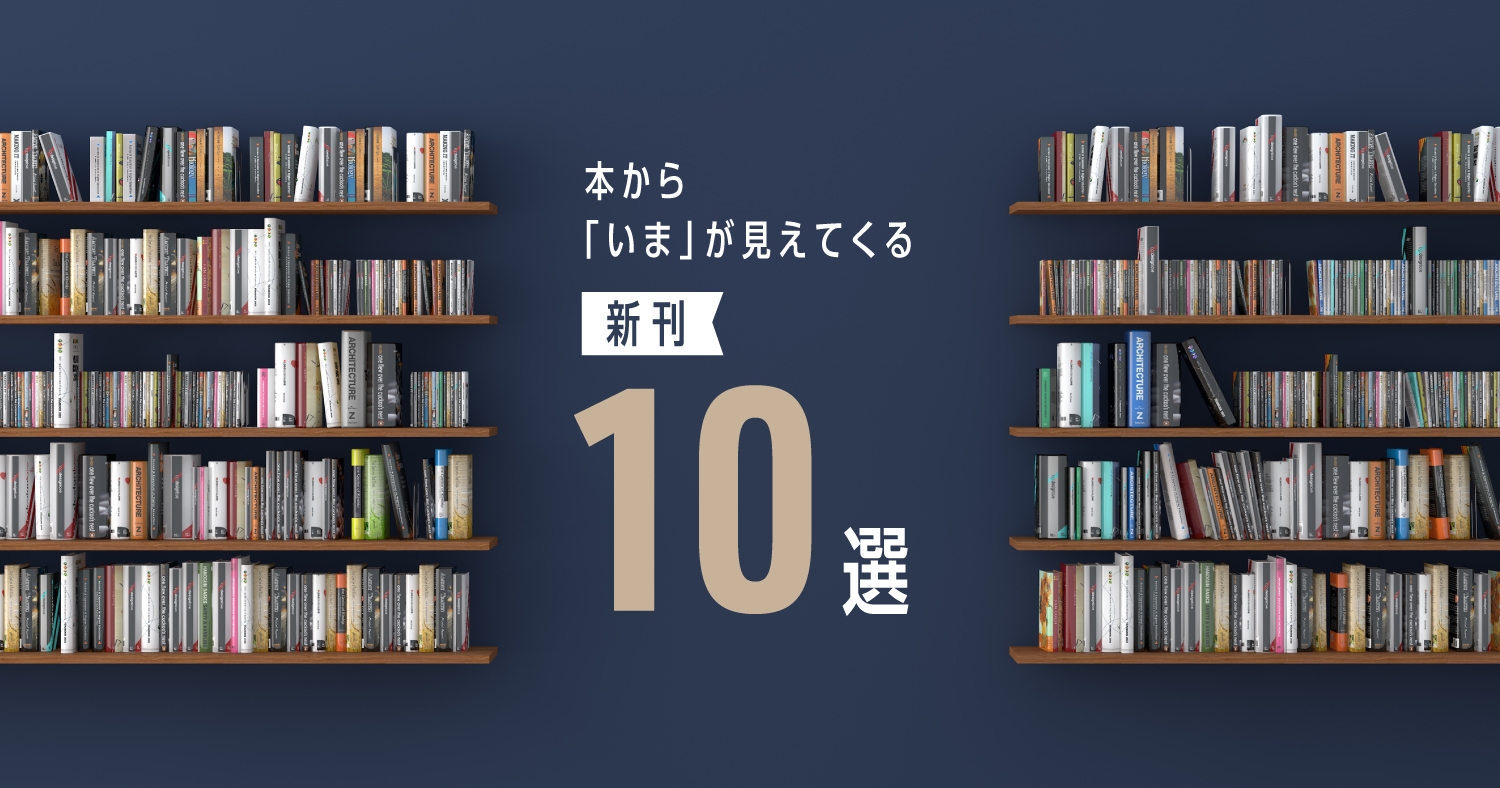
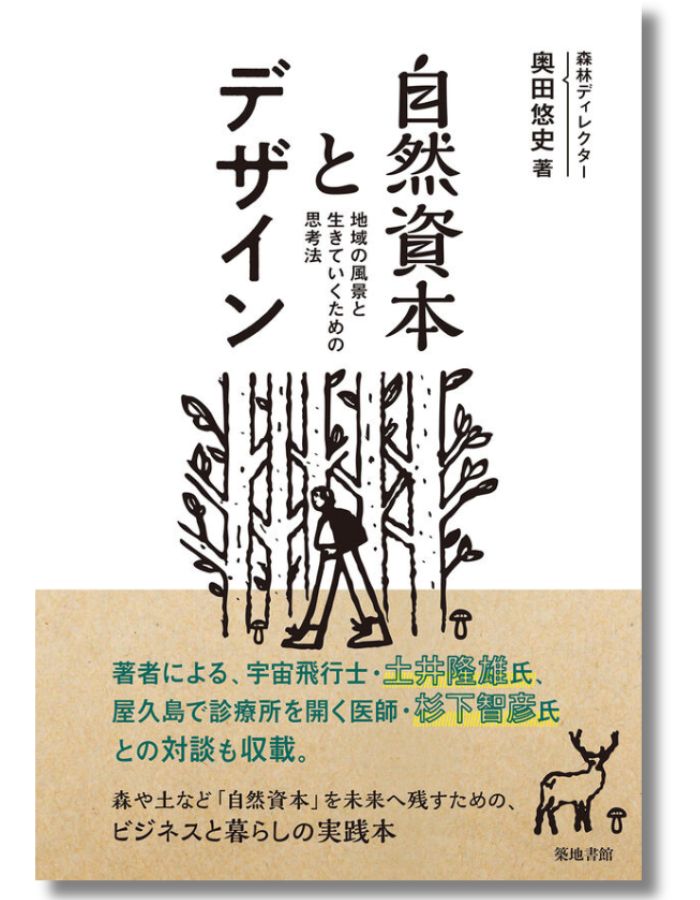
地域の風景と生きていくための思考法
「森とディレクションの専門性を持ち、森に関わる課題を解決するアイデアを考えて、カタチに。」これが森林ディレクターの定義です。その実践として、「森をつくる暮らしをつくる」という企業理念を掲げる「株式会社やまとわ」に参画しながら、長野を拠点にものづくりやインキュベーション施設の運営などを行っています。森と仕事と暮らしをつなぎ直すような著者の精力的な活動は、ローカルの範囲を超えて全国から注目を集め始めています。
印象に残ったのは「Rescale(リスケール;規模の再編集)」という考え方。スケールメリットという言葉があるように、ビジネスにおいては多くの場合で規模の拡大が目指されます。一方で、限りある地域の自然資本を相手にした場合、規模の拡大は必ずしもメリットばかりではない。かといって、小規模にとどまるままではビジネスとして成り立たず、暮らしもままならなくなってしまう。
著者は大都市ではなくいわゆる地方を拠点にしていますが、その活動や思想には都市でのビジネスや暮らし方をより快適にしていくヒントが詰まっているように思います。「自然資本」との付き合い方を見直し、それぞれの規模感に見合った持続的な手法を問い直していくことは、新たな時代の“デザイン思考”と言えるのかもしれません。
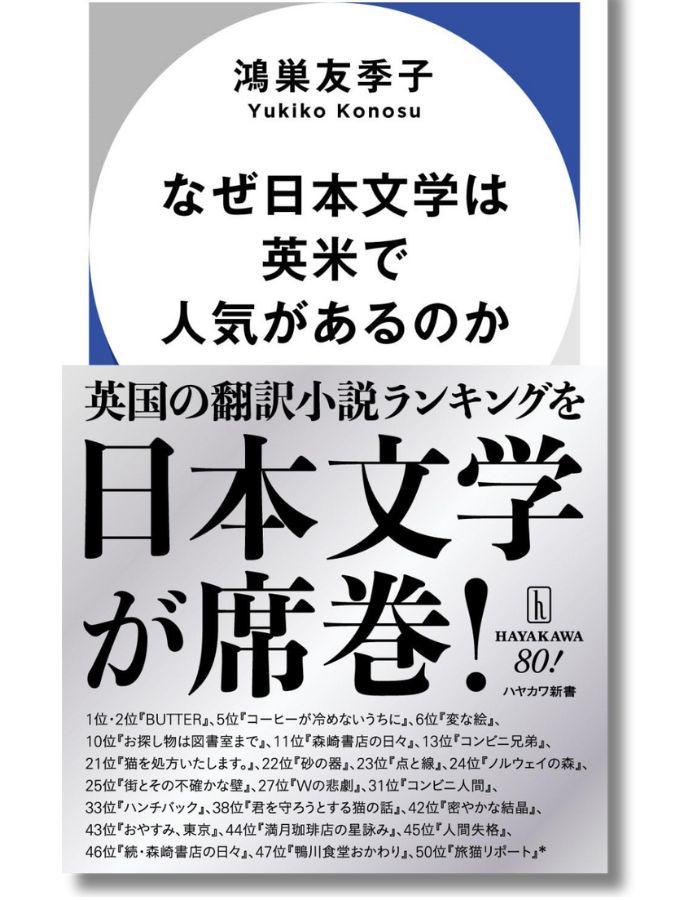
なぜ日本文学は英米で人気があるのか
2010年代半ばから日本文学が英米を席巻している、そんな話題を聞いたことがないでしょうか。実際にイギリスの2025年のある時期においては、翻訳小説のベストセラーランキング上位50位のうち23作品が日本文学となっていたそう。本書は文芸評論家・翻訳家である著者が、その現状を伝え、背景を分析した一冊。
十数年前までは海外で有名な日本文学といえば村上春樹や昭和の文豪の作品が挙げられたでしょうが、現在は全く異なる風景が広がっているようです。文学作品そのものが時代を切り取ったものでもありますが、その読まれ方、広がり方からも社会の変化が見えてきます。
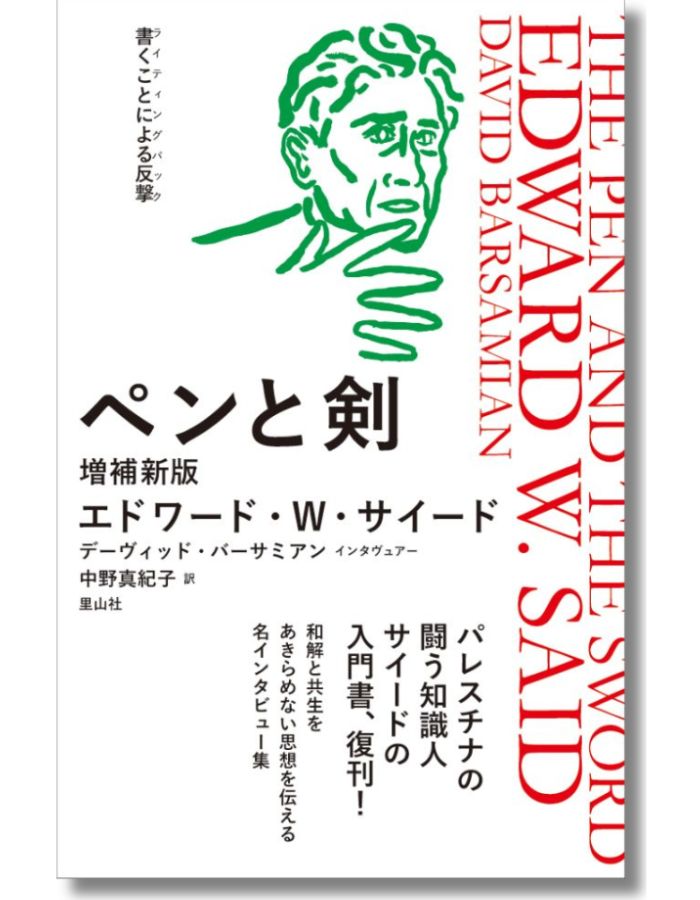
ペンと剣
『オリエンタリズム(1978)』などの著作を通じ西洋の帝国主義的な思考様式を批判し、パレスチナ問題についても積極的に発言してきた文学研究者・エドワード・サイード。本書はアメリカのラジオ番組でのサイードへのインタビューをまとめた1994年刊行の同名書籍の増補復刻版です。
インタビュアーからの率直な質問に率直で明快な言葉で答えるそのやり取りからは、勇気と優しさを持ったサイードの人柄が垣間見えます。パレスチナにとどまらず、歴史として共通認識のもとに語られる物事の中に「対抗的視点(カウンターポイント)」を持つことの重要性に気付かされます。
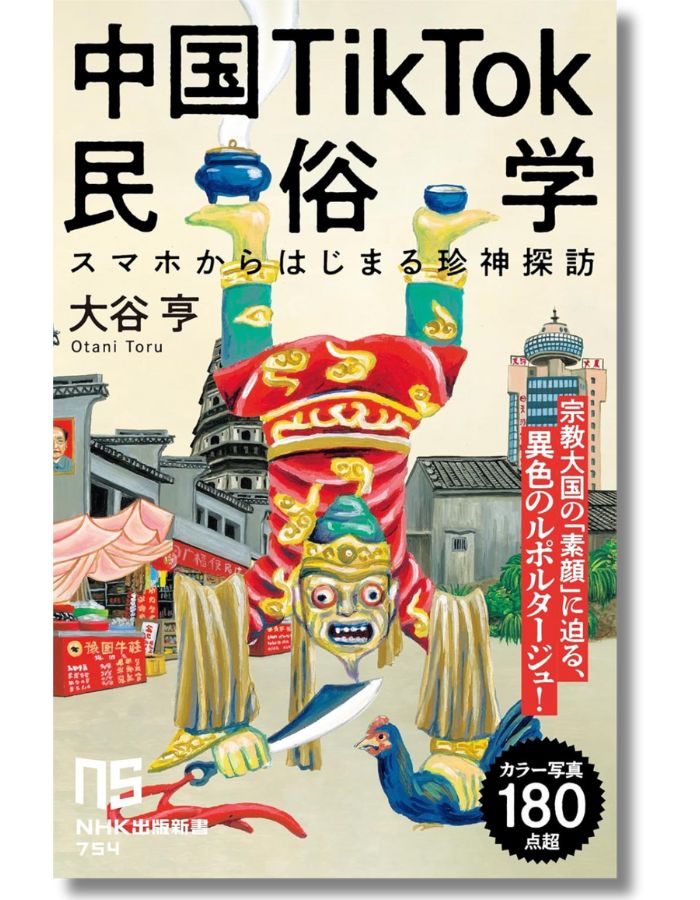
中国TikTok民俗学
スマホからはじまる珍神探訪
中国の大学で日本語を教えながら“日曜民俗学者”として研究活動も行う著者による、中国国内の民間信仰を追ったフィールドワークルポ。そのスタイルは、中国国内版のTikTok、Douyin(ドゥイン)で一風変わった風習を見つけたら即時にどこでも駆けつけるというもの。
広大な国土と人口を持つ中国には地元民以外に知られていない文化が多々あり、そこに電子決済システムの普及に伴いスマホが浸透していったことで、このような研究が可能になった、と著者は書いています。メディアやアカデミアでは取り上げられない、中国の今を生きる人々のディープな日常がここに。

東大「芸術制作論」講義
手を動かし知をつかむ、創発のポイエーシス
2024年度に、比較文化、表象文化論などを専攻する学生向けに東京大学で開講された「芸術制作論」の講義を書籍化したもの。講義パートと手を動かしてみるワークパートが交互に出てくるので、授業を追体験するように読むことができます。
芸術的な意味においての「つくる(創作、制作)」ことは、芸術家の専門領域であるかのように捉えられがちですが、制作する知性(=制作知)を通じての学びは、人間そのものの理解に新鮮で普遍的な視点をもたらしてくれます。AI時代に手を動かすことにどんな意味があるのか、という問いとも向き合う一冊。
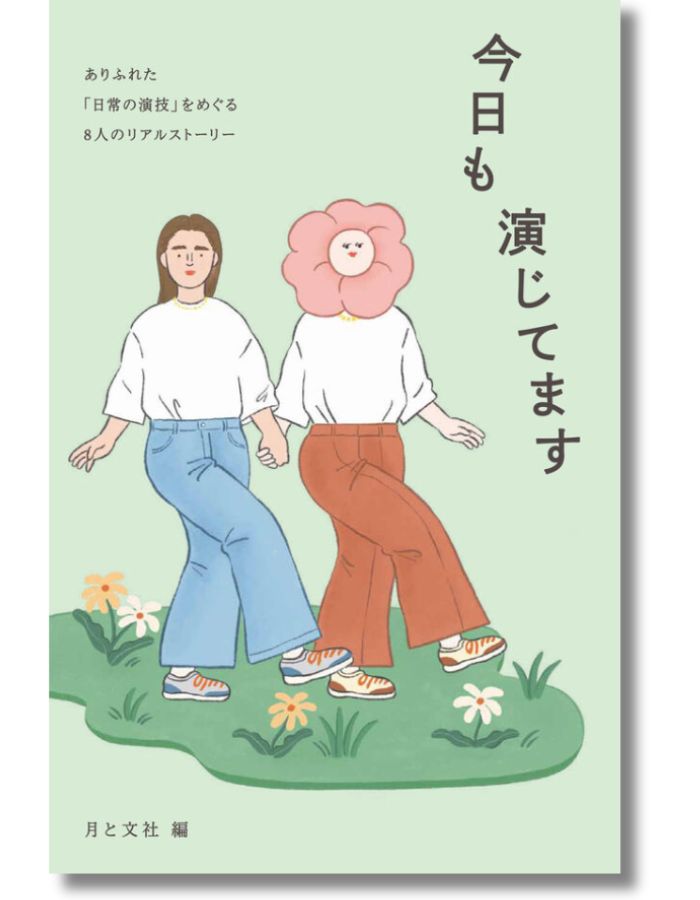
今日も演じてます
元『日経WOMEN』の編集長が立ち上げたひとり出版社・月と文社。多くの人が抱えているけど他人にはあまり話さない、個人の少しだけ深い部分に光を当てるようなテーマの本の刊行で書店で注目を集めています。同社の最新刊である本書は、日常の中での「演じること」がテーマ。
noteなどの個人発信を読んで直接コンタクトを取ったり、知人を介して出会ったりした、年齢も性別も職業もバラバラの8人に「演じること」について聞いたインタビュー集です。個人的で赤裸々な語りの中には、自分に置き換えられそうなことのみならず、社会課題として捉えることができそうなトピックも見えてきます。
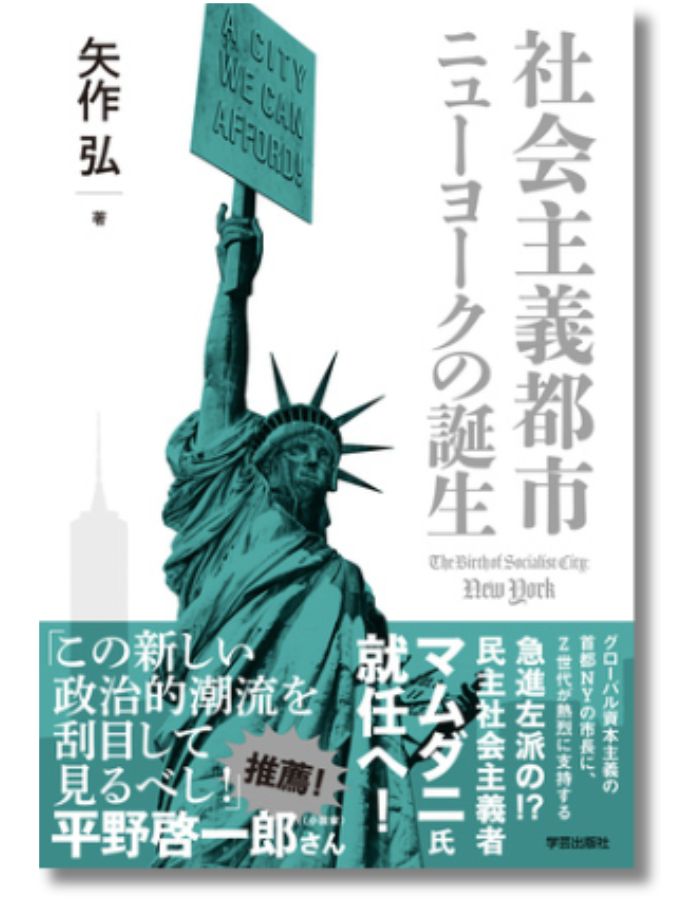
社会主義都市ニューヨークの誕生
昨年11月の選挙でニューヨーク市長に当選し、2026年1月1日に正式に就任したゾーラン・マムダニ。34歳のイスラム教徒で民主社会主義者というパーソナリティ、市営バスの無料化、保育料無償化、富裕層への増税など、グローバル経済の中心地で生活者中心の政策を掲げて当選したことで、アメリカ国内外から大きな注目を集めました。
本書は当選から間もない12月中旬に緊急出版された一冊。マムダニの当選は局地的なものではなく、大きな政治的潮流の中の出来事であり、アメリカの都市政治史とも連続性のある現象である、と読み解きます。アメリカに留まらない社会変化のきっかけとなるのか、その成果が注目されます。
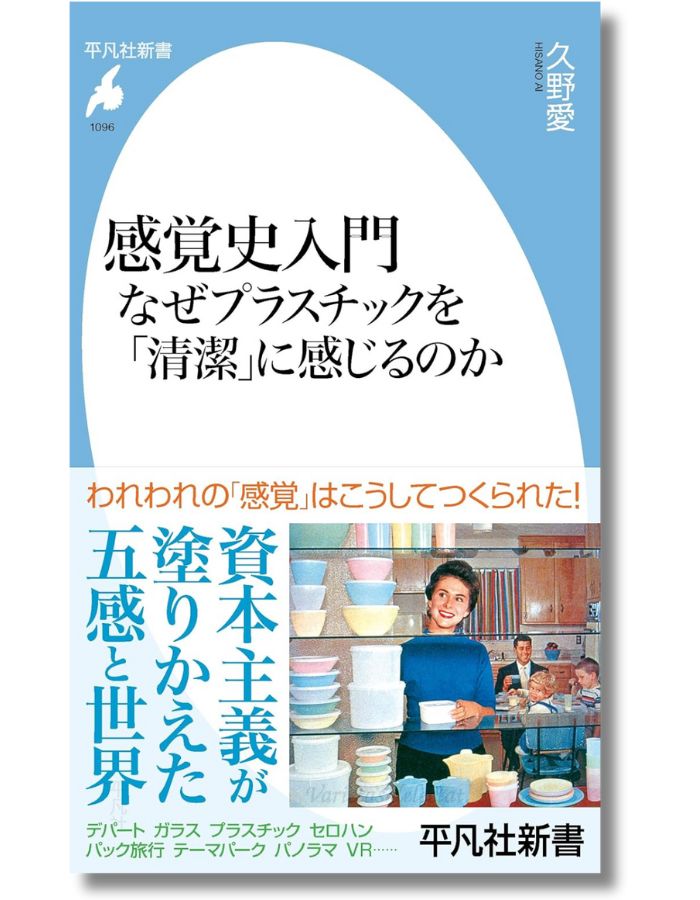
感覚史入門
なぜプラスチックを「清潔」に感じるのか
例えば「いい匂い」や「心地よい音」と言うとき、その「良さ」はどこから来たのか。この本がテーマにしている「感覚史」とは、そのような“感じ方”の歴史をたどることです。
本書では特に都市化、消費社会化が進展していった19世紀末以降の近代化の時代に焦点が当てられていますが、人々の感じ方の変化には、社会の変化が深く関わっていることがよくわかります。自然であるかのように認知されているものも、実は何か外部の要因に規定されているかもしれない、そんなことに思い至る一冊です。
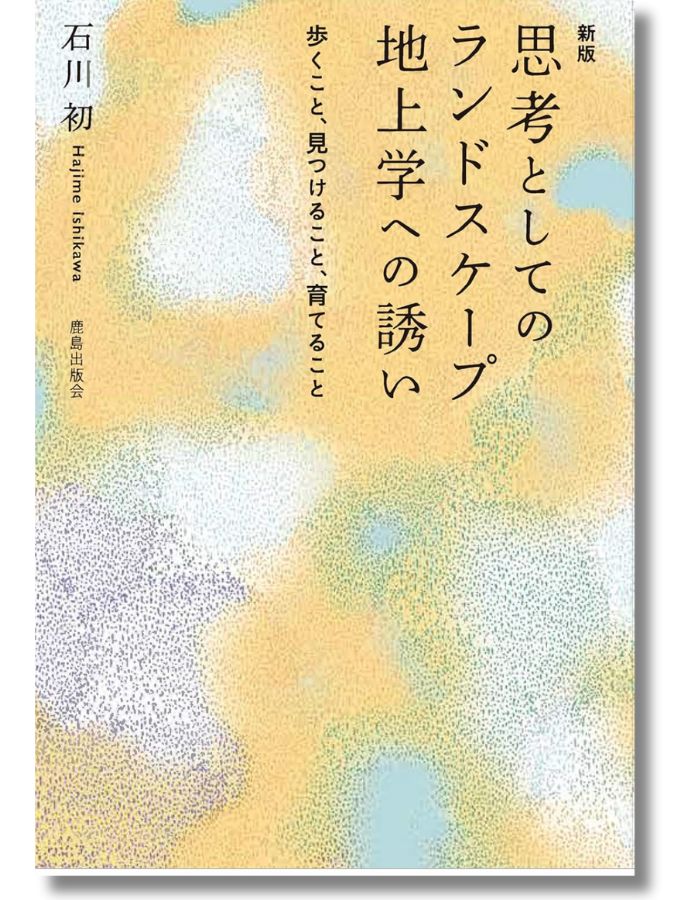
[新版]思考としてのランドスケープ 地上学への誘い
歩くこと、見つけること、育てること
ランドスケープアーキテクトである著者による、2018年に出版された同名の書籍の増補新装版。タイトルの“地上学”とは著者の造語で、ランドスケープの観察・分析を「使える思考ツール」として名付けたものです。それは、ランドスケープの設計という高度な専門性の知見を、作り手だけでなく鑑賞者にも開いていく試みです。
「風景」の読み解きを通じて、社会の変化、人と自然の関係性、新しい創造性に気づいていくまなざしとも言えるかもしれません。2018年の出版時から文章はほとんど変更していないため、少し懐かしいトピックも登場。それに対する現在からのコメントも面白く、短い期間の中での時代の変化も感じられます。
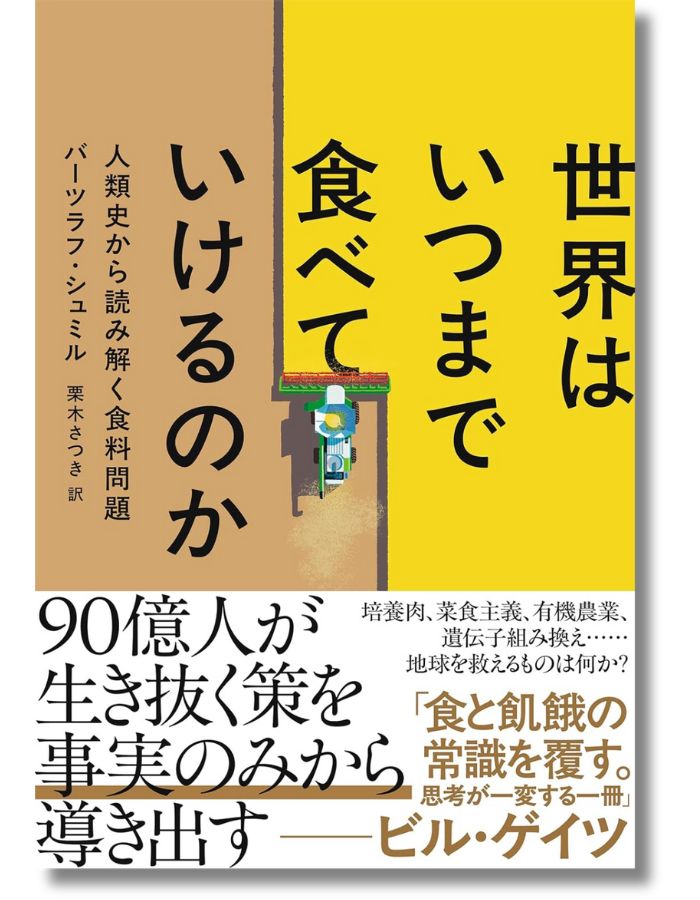
世界はいつまで食べていけるのか
人類史から読み解く食料問題
ビル・ゲイツが大きな信頼を置き、現代の「知の巨人」とも呼ばれるカナダのマニトバ大学特別栄誉教授バーツラフ・シュミルの最新の著書。エネルギー、テクノロジー、環境問題などの学際的な研究で知られますが、「食」は氏が最も長く研究し続けているテーマです。
危機を煽るでも、楽観的な未来を語るでもなく、いわば淡々とファクトに基づいて現代の食の複雑な問題を紐解いていく本書は決してドラマチックではないですが、それがシュミル氏のスタイルであり誠実さであるように感じられます。時間的にも空間的にも、巨視的な視点から「食」の現在地を描き出す一冊。
自然資本とデザイン 地域の風景と生きていくための思考法
奥田悠史築地書館
なぜ日本文学は英米で人気があるのか
鴻巣友季子早川書房
ペンと剣
エドワード・サイード里山社
中国Tik Tok民俗学 スマホからはじまる珍神探訪
大谷亨NHK出版
東大「芸術制作論」講義 手を動かし知をつかむ、創発のポイエーシス
村山悟朗フィルムアート社
今日も演じてます
月と文社(編)月と文社
社会主義都市ニューヨークの誕生
矢作弘学芸出版社
感覚史入門 なぜプラスチックを「清潔」に感じるのか
久野愛平凡社
[新版]思考としてのランドスケープ地上学への誘い 歩くこと、見つけること、育てる こと
石川初鹿島出版会
世界はいつまで食べていけるのか 人類史から読み解く食料問題
バーツラフ・シュミルNHK出版
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













