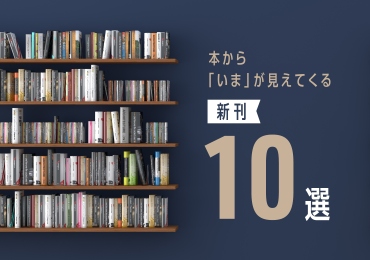セミナー・イベント
楠木建の「脱コモディティ化」の戦略~次元の見えない差別化戦略~
カフェグローブに見る、コンテンツ系ビジネスの成功要因
~矢野社長が語る、読者を惹きつけるコンテンツ創造の戦略とは~
日時
2007年01月30日
(火)
19:00~21:00

内容
企業間競争が激化する中で、競争はハードからソフトへ、機能からデザインへ移り、高付加価値やデザイン重視の商品が求められています。つまり、価格、性能、品質といった「次元の見える競争」は限界を迎えつつあり、焦点はデザインやブランドといった「価値の次元が見えない競争」へとダイナミックに転換しているのです。
自動車産業では、基本性能が充分な水準を達した今日、競争の焦点は、 クルマを買ったら生活がどのように変わるかといったコンセプトとそれを体現したデザインに移りつつあります。
PCメーカーにおいては、処理速度、本体やモニターの大きさ、RAMやHDDの容量、耐久性、多様な付加機能、サポートやアフターサービスなど様々な次元での差別化を追求してきました。しかし、こうした次元の見える競争が熾烈になる中で、顧客が充分に満足する水準に到達してしまえば、技術的に差別化しても無意味になり、差別化の次元は価格だけになってしまいます。つまり完全なコモディティ化に陥ってしまうわけです。
では、どうしたらコモディティ化から逃れることができるのか。それは、可視的な価値の次元に捕らわれず、次元の見える競争のルールそのものを破壊して考える必要があります。つまり、競争や差別化を次元の見えないものとして捉えなおすことが大切です。そして、「その製品やサービスは顧客にとって何なのか、何のためにあるのか」を見出し、顧客に見せる組織能力と構想力、いわば「コンセプト」を創造する力、が脱コモディティ戦略における鍵となります。
本講座では、競争戦略の新しいフェーズである“脱コモディティ化の戦略”構造を解説するとともに、客観的なものさしでは捉えられないような顧客価値を見出し、それを形にして顧客に伝えていく能力とはいかなるものか考えます。
今回は、コンテンツ系ビジネスとして成功、成長した好例であるカフェグローブ・ドット・コムの代表取締役 矢野貴久子氏をお招きします。
多くのネット・ベンチャーが誕生し消えていく中で、成功したコンテンツ系ビジネスは、運営サイトの何がよくて人が集まるのかが見えないところがあります。これは正に次元の見えない競争だといえます。
「カフェグローブ」は女性をターゲットしたインターネットメディア事業で成功しており、このことは広く知られています。しかし、いうまでもなく、カフェグローブの成功は、「参入のタイミング」、「女性をターゲットとしたこと」というような可視的な次元では説明できません。
インターネットというインタラクティブなメディアでどのような価値をどのような状況にあるどのような女性に提供しているのか、矢野貴久子さんと楠木建との対談形式で、カフェグローブの事業コンセプトとこれまでの変遷を掘り下げていきます。
カフェグローブの事例を通して顧客価値創造とそれを形にして伝える能力、つまりコンセプト創造力とは何かを具体的に理解し、自身の企業やサービス・商品の戦略を考える上で求められる、既存の概念に捕らわれない新しいものの見方や視点を得ることができます。
主なディスカッション項目
・カフェグローブが目指すターゲティングWebメディアとは
・カフェグローブのターゲット
・カフェグローブが創造する価値とは
・コンテンツ創造の組織と戦略~「するべきこと」と「してはいけないこと」
・いかにして顧客に価値を伝えるか
・Webメディアを核に広がる事業展開 など
自動車産業では、基本性能が充分な水準を達した今日、競争の焦点は、 クルマを買ったら生活がどのように変わるかといったコンセプトとそれを体現したデザインに移りつつあります。
PCメーカーにおいては、処理速度、本体やモニターの大きさ、RAMやHDDの容量、耐久性、多様な付加機能、サポートやアフターサービスなど様々な次元での差別化を追求してきました。しかし、こうした次元の見える競争が熾烈になる中で、顧客が充分に満足する水準に到達してしまえば、技術的に差別化しても無意味になり、差別化の次元は価格だけになってしまいます。つまり完全なコモディティ化に陥ってしまうわけです。
では、どうしたらコモディティ化から逃れることができるのか。それは、可視的な価値の次元に捕らわれず、次元の見える競争のルールそのものを破壊して考える必要があります。つまり、競争や差別化を次元の見えないものとして捉えなおすことが大切です。そして、「その製品やサービスは顧客にとって何なのか、何のためにあるのか」を見出し、顧客に見せる組織能力と構想力、いわば「コンセプト」を創造する力、が脱コモディティ戦略における鍵となります。
本講座では、競争戦略の新しいフェーズである“脱コモディティ化の戦略”構造を解説するとともに、客観的なものさしでは捉えられないような顧客価値を見出し、それを形にして顧客に伝えていく能力とはいかなるものか考えます。
今回は、コンテンツ系ビジネスとして成功、成長した好例であるカフェグローブ・ドット・コムの代表取締役 矢野貴久子氏をお招きします。
多くのネット・ベンチャーが誕生し消えていく中で、成功したコンテンツ系ビジネスは、運営サイトの何がよくて人が集まるのかが見えないところがあります。これは正に次元の見えない競争だといえます。
「カフェグローブ」は女性をターゲットしたインターネットメディア事業で成功しており、このことは広く知られています。しかし、いうまでもなく、カフェグローブの成功は、「参入のタイミング」、「女性をターゲットとしたこと」というような可視的な次元では説明できません。
インターネットというインタラクティブなメディアでどのような価値をどのような状況にあるどのような女性に提供しているのか、矢野貴久子さんと楠木建との対談形式で、カフェグローブの事業コンセプトとこれまでの変遷を掘り下げていきます。
カフェグローブの事例を通して顧客価値創造とそれを形にして伝える能力、つまりコンセプト創造力とは何かを具体的に理解し、自身の企業やサービス・商品の戦略を考える上で求められる、既存の概念に捕らわれない新しいものの見方や視点を得ることができます。
主なディスカッション項目
・カフェグローブが目指すターゲティングWebメディアとは・カフェグローブのターゲット
・カフェグローブが創造する価値とは
・コンテンツ創造の組織と戦略~「するべきこと」と「してはいけないこと」
・いかにして顧客に価値を伝えるか
・Webメディアを核に広がる事業展開 など
講師紹介


開催実績
佐山展生 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、GCA株式会社代表取締役)
安田隆二 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)
石倉洋子 (一橋大学名誉教授)
楠木建 (一橋ビジネススクール教授)
開催日 : 2007/04/25 (水)
安田隆二 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)
石倉洋子 (一橋大学名誉教授)
楠木建 (一橋ビジネススクール教授)
開催日 : 2007/04/25 (水)



大久保清彦 (株式会社インターナショナル・ラグジュアリー・メディア 取締役
オーシャンズ 兼 ローリングストーン日本版 発行人/編集長
セブンシーズ総研株式会社 取締役副社長)
楠木建 (一橋ビジネススクール教授)
開催日 : 2006/12/07 (木)
オーシャンズ 兼 ローリングストーン日本版 発行人/編集長
セブンシーズ総研株式会社 取締役副社長)
楠木建 (一橋ビジネススクール教授)
開催日 : 2006/12/07 (木)


募集要項
| 日時 |
2007年01月30日
(火)
19:00~21:00 |
|---|---|
| 受講料 |
29,800円 |
| 定員 | 50名 |
| 主催 |
|
| 会場 |
アカデミーヒルズ49(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー49階) ※都合により40階に変更する場合、受講生には直接ご案内いたします。 |
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....