記事・レポート
aiaiのなんか気になる社会のこと
【第15回】なぜクマ問題はみんなの問題なのか
~駆除か共生かの二項対立を越えて~
更新日 : 2025年09月22日
(月)
第15回 なぜクマ問題はみんなの問題なのか ~駆除か共生かの二項対立を越えて~
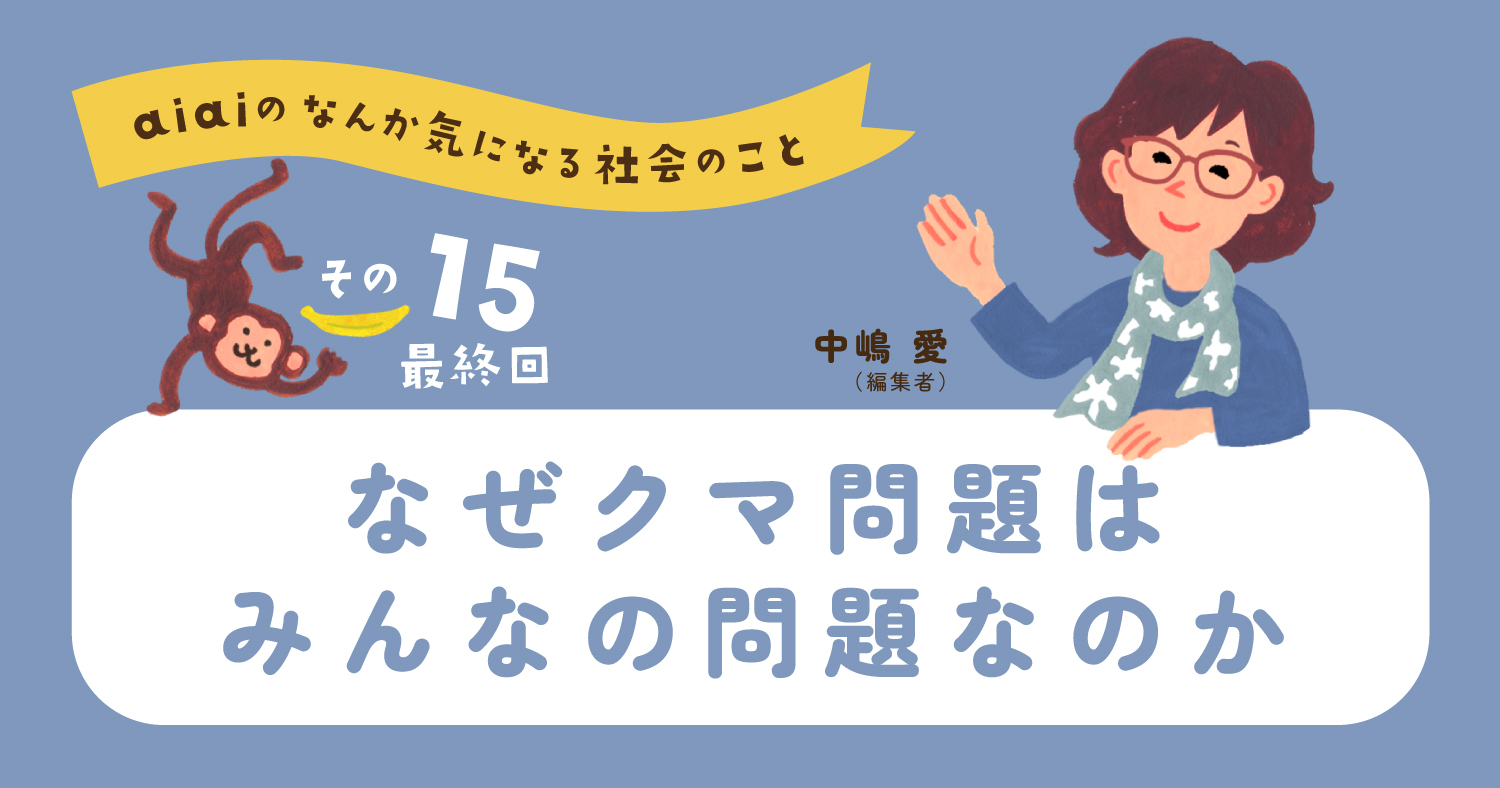
クマ被害のフェーズが変わってきている
今年、クマによる人的被害は、近年でもっとも深刻だった2023年を上回るペースで増加している。8月には北海道の羅臼岳で登山道を歩いていた男性がヒグマに襲われ死亡するという衝撃的な事件が発生。7月には北海道福島町で新聞配達中の男性が襲われて死亡、さらにその数週間前には岩手県北上市で、一人暮らしの高齢女性が自宅に侵入したクマに襲われ、命を落とした。すでに数年前から指摘されていたように、クマ被害の「フェーズ」は明らかに変わりつつある。かつては山菜採りや渓流釣りなど、クマの生息地に人間が足を踏み入れたときに偶発的に出くわすものだった。しかし今では、ハイシーズンの観光地や住宅地、総合公園といった、本来出没が想定されない場所で人が襲われるケースが相次いでいる。このような状況下で「クマに出会わないことがもっとも大事」といった従来の注意喚起は、もはや空々しく響く。
こうした連日の報道を背景に、クマ問題は全国的な関心事へと拡大しつつある。それ自体は、より広範な施策につながるという意味で一定の前進ともいえるかもしれない。しかし同時に、全国的な注目が集まることで、他の多くの社会問題と同様に「抽象化 → 単純化 → 二項対立」というお決まりのルートを辿り始めていることには危惧をおぼえる。たとえば「共存か、駆除か」というような言説にはこれまでの各地の地道な取り組みまで否定するような危うさを感じる。
クマ問題は、過疎、高齢化、環境問題などと複雑に絡み合った構造的課題であり、「共存か、駆除か」の二者択一で解決できるものではない。日々の暮らしに直結する危険に晒されている人々に「共存」の理想だけを押し付けるのは論外だが、一方で、「駆除」にはハンターの人材不足、銃猟にかかる法的制約、地域ごとの対応力の差など、現実的な障壁も多い。現場では、専門家、活動家、技術者、住民、行政がそれぞれに知恵を絞っているが、打開策が見いだせないまま、事態が悪化し続けている。
結局のところ、クマ問題は、私たちが抱える多くの社会課題のジレンマを、もっとも劇的かつ露骨な形で突きつけているのである。
野生との軋轢は「新しい問題」ではない
人と野生動物との衝突は、今に始まったことではない。国土の67%が森林という日本において、クマとの軋轢は「古くて新しい」問題である。日本で明治以降最悪の獣害事件とされるのは、1915年(大正4年)に北海道・三毛別で起きた「三毛別羆事件」だ。開拓民7人が1頭のヒグマに殺されるというこの凄惨な事件は、吉村昭の小説『羆嵐』によって広く知られるようになった。物語の中では、警察も手に負えなかったヒグマを、村から疎まれていた老猟師が呼び戻されてようやく仕留めるという経緯が描かれている。
戦後の昭和期には、北海道への入植が進むなかでヒグマによる被害が激増し、駆除によって個体数は大きく減少した。同時期、九州や四国では森林伐採や計画的な駆除によってツキノワグマが絶滅したとされる。1990年代以降は、個体数の回復が政策的に図られ、2000年代にはヒグマによる農地被害を背景に「ゾーニング計画」が推進された。ゾーニングとは、クマを保護するコア生息地、人との緩衝地帯、人間活動を優先する防除地域にエリアを分けて管理するというものだ。
クマと民主主義:島牧村の7年
令和のクマ問題は、日本社会が直面する人口減少という構造的な変化の一断面でもある。山間地域では、住民の減少に加え、農林業の担い手や狩猟者、さらには自治体職員の数も減っている。人口減少は地域コミュニティの弱体化を招き、協力して対策を進めることを難しくする。クマ問題の深刻化は、限られた人員と財源をいかに配分するかという課題としても現れている。このことを正面から扱ったドキュメンタリー映画が『クマと民主主義』(監督:幾島奈央)だ。舞台は北海道・島牧村。2018年夏、住宅地へのヒグマの出没が頻発した。山間の畑が耕作放棄され、里へのアクセスが容易になっていたのだ。村が推奨して設置したコンポストは荒らされ、水産加工場の扉も破壊されるなどの被害が続出した。
村は猟友会に駆除を依頼したが、夜間や住宅街では発砲が禁じられており、罠にかかるのを待つしかなかった。駆除完了までに2カ月を要し、報奨金は1,000万円超にのぼった。だが、村議会は補正予算を否決し、猟友会は手を引いた。その後もクマの出没は続き、住民は自らの生活を守るため、クマの生態を学び、生活習慣を見直し、啓発活動を始めた。現在、島牧村は道内のクマ対策モデル地域とされている。
命と生活にかかわる話だからこそ
この映画は北海道放送(HBC)の幾島奈央さんが、入社1年目から7年間、クマと村の問題に向き合った記録である。幾島さんは、TBSラジオ『荻上チキ・Session』で、猟友会と議会との間に生じた報償をめぐるトラブルをめぐって何より不可解だったのは議員が否決の理由を明らかにしなかったことだったと語った。住民にとっては命にかかわる話なのに説明がないのはおかしい。2年間食い下がってやっとその理由がわかった。そもそも「払わない」という話ではなかった。最初にきちんと対話できていればそこまで話がこじれることもなかったのではないかと感じたという。報奨金のやりとりは、前述の『羆嵐』にも描かれている。クマを仕留めた猟師に対し、区長が「謝礼は全部持っていっていい」と言ったところ、猟師は「もっていっていいとは何事だ」と激怒。村人たちはあらためて金をかき集めて猟師に渡した。命を懸けた行動には、それに見合う敬意と対価が必要だという点は、今も昔も変わらない。
9月からは法改正により、市街地でも一定条件下で自治体判断による猟銃の使用が可能となったが、北海道猟友会は「要請を断る場合もある」と明言している。事故時の責任がハンター個人に重くのしかかる制度設計では、対応が困難なのだ。制度を整えても、それだけでは足りない。緊急対応の有効性は、平時の信頼関係とコミュニケーションによって担保される。
恐怖心は社会を分断する
現在、クマ問題をめぐる世論は過熱しており、「平時からの準備」や「コミュニティ内の熟議」といった言葉が悠長に聞こえる空気すらある。自宅にいても襲われるという事件は、日頃クマと接点のない人々の恐怖心を強く刺激し、「共存か駆除か」の単純化された議論に拍車をかけている。恐怖心は、しばしば冷静な議論を断ち、コミュニティを分断する。クマ問題にしても、特効薬を求める声が強まれば、短絡的な「全面駆除」論へと傾いていくだろう。警察や自衛隊の動員を求める声もあるが、銃器があることと、クマが撃てることはまったく別の話であり、人命に関わる銃器の使用条件の緩和には、極めて慎重な判断が求められる。仮に令和のクマ防除隊を作るとしても、予算はどうするのか。採用、訓練、補償についてのルールも必要だ。こうした現実的な議論がなされなければ、結局は何も進まない。
クマ問題を構造的に捉え、実効的に取り組むには、先進事例の共有、法整備、専門人材の育成、生態理解の促進が不可欠だ。そしてなにより、「共存か駆除か」という二項対立の罠を超えていく、地道な議論の積み重ねが必要である。
厄介な問題はネットワークで解決する
こうした取り組みの基盤の一つが、1997年に発足したNGO「日本クマネットワーク」だ。クマに関心を持つ研究者、活動家、行政関係者、一般市民などがつながる全国的なネットワークで、情報共有、問題提起、地域活動支援を行っている。2023年の大量出没を受けて開かれたオンラインシンポジウムの報告書には、次のような声が収録されている。
「大量出没は繰り返し起こってきた。その度に問題になり、対策が検討されたが、その時ばかりの対応ではなかったか考えてみるとよい。将来、必ず起こるだろう大量出没は、今年の秋田、岩手の例を見れば、これまでよりも大きな被害をもたらす可能性がある。そうしたことに対応するためには、人員や資金など資源を投入して対策を継続するとともに、私たちは、クマ問題を意識し続ける必要がある。指定管理鳥獣指定による捕獲の強化が検討されているが、今後、捕獲というツールを有効に利用するためにも、これまでの対策とその実施体制を再点検していくことが重要だ」(大井徹・石川県立大学)
「北東北の住民の方にはクマや鳥獣害が 10 年前とは状況が変わったと認識を変えていただきたいと常々言っているが、都市に住んでいる方も同様だ。クマや鳥獣害はこれからの少子高齢化の中で日本全体の問題と捉えて、それぞれの立場で何ができるかを考えていただきたい」(大西尚樹・森林総合研究所東北支所)
「個体数管理をしなければならないことも事実だが、捕獲だけを進めるという部分で終わってはいけない。各地でこれまで様々な取り組みが行われてきて、その成果が少しずつだが出てきた。捕獲を進めれば全て解決するわけではないので、これまでの取り組みを継続することが必要であり、捕獲圧の強化についてもその延長上で進めることが大事だ」(釣賀一二三・北海道立総合研究機構)
こうした地道な議論こそが、二項対立の喧騒を越えて、構造的な解決策を探る上で重要な道しるべとなるのではないだろうか。
ネットワークを国外に広げることも重要である。獣害は現代に特有の問題でもなければ、日本に固有の問題でもない。たとえばスリランカの象による被害は、日本のクマ問題とよく似た構造を持っている。過去9年間で人と象の衝突により1,100人以上が死亡し、同時に3,400頭もの象が命を落とした。象はスリランカにおいて文化的象徴であり、観光資源としても保護の対象であるため、対策は極めて困難である。
原因の背景は異なる。スリランカでは農地拡大やインフラ建設による森林喪失が進む一方、日本では過疎化や里山管理の放棄によって人とクマとの緩衝地帯が失われている。しかし両者に共通するのは、「共存か駆除か」という単純な二択で片付けられない点である。互いの経験や知見を共有すれば、ステークホルダーの特定や巻き込み方を含め、問題解決のプロセスそのものを学び合うことができるだろう。
答えは白と黒のあいだに
ここまで読んでいただいた方にはもうおわかりだろう。「再開か停止か」「排除か包摂か」「脱炭素か成長か」──社会には、白か黒かでは語れない課題で溢れている。クマ問題もまたその一つだ。危機が高まり、社会的関心が集まると、特効薬的な解決策が求められ、議論はAかBかの単純な対立構造に流れ込み、政治的に消費される。だが、そうした構図の先に「最適解」があることはまずない。現実的な選択肢は、白と黒のあいだのグラデーションのなかにある。その選択肢を探るためには、当事者と部外者、被害者と救済者、行政と民間といった境界を越え、経験や知見を共有し、問題の深部にまで目配りしながら手当てしていく以外にないだろう。
※本連載は今回が最終回となります。お読みいただきだきあがとうございました。
執筆者:中嶋 愛
Glass Rockプログラムディレクター。編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。
Glass Rock ~ Social Action Community ~
Glass Rockは、クロスセクターの連携と共創により社会課題の解決を目指す会員制拠点です。コミュニティ運営の専門家が支える「つながる」場、実践的な学びや対話を生み出す「まなぶ」仕掛け、そしてギャラリーやスタジオなどから「ひろげる」発信機能を有します。これらの「場」と「仕掛け」を通じてクロスセクターの連携と共創を促進し、「社会課題解決」に向けたイノベーションの創出と持続可能な社会の実現に貢献します。
https://www.glass-rock.com/index.html

aiaiのなんか気になる社会のこと インデックス
-
【第1回】ドラッカー曰く「世界最古のNPOは日本のお寺?!」
2024年07月23日 (火)
-
【第2回】「コンヴィヴィアリティ」の視点で、厳しい暑さを乗り切るには?
2024年08月21日 (水)
-
【第3回】美術館は誰のもの?「正の外部性」から考えてみる
2024年09月24日 (火)
-
【第4回】「15分都市」という選択 住み心地のいい街の条件とは?
2024年10月22日 (火)
-
【第5回】私たちは「コモングッド」を取り戻せるか
2024年11月20日 (水)
-
【第6回】世の中は「虚構」で成り立っているという衝撃
2024年12月24日 (火)
-
【第7回】政治の話は嫌いですか ~ポリティカルイノベーション事始め~
2025年01月21日 (火)
-
【第8回】「コーヒーの一生」から見えてくる風景
2025年02月25日 (火)
-
【第9回】なぜ日本の学校では子どもたちが掃除をするのか
2025年03月25日 (火)
-
【第10回】柳宗悦の蒐集論がおしえてくれること
私欲が利他に転換するとき
2025年04月22日 (火)
-
【第11回】「最強のパスポート」を持っているということ
命をかけなくても越境できる「特権」
2025年05月27日 (火)
-
【第12回】履き古したランニングシューズはどうしたものか
2025年06月24日 (火)
-
【第13回】オワコンで紡ぎなおす地域の記憶と人の縁
2025年07月22日 (火)
-
第14回 私たちは「物語的不正義」にどう立ち向かうのか ~他者の語りに人生を絡めとられないために~
2025年08月25日 (月)
-
第15回 なぜクマ問題はみんなの問題なのか ~駆除か共生かの二項対立を越えて~
2025年09月22日 (月)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....














