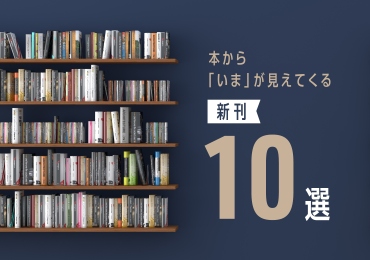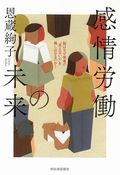セミナー・イベント
楠木建の「脱コモディティ化」の戦略~次元の見えない差別化戦略~
パネル・ディスカッション「見えないものを見る力」:
経営とリーダーシップの本質を考える
日時
2007年04月25日
(水)
19:00~21:00

内容
『楠木建の「脱コモディティ化」の戦略』の特別編として、企業成長を支える経営とリーダーシップの本質を考えるパネル・ディスカッションを開催します。
日本の経済と企業は長く続いたトンネルから抜け出し、企業経営の焦点もリストラクチャリングという「守り」のフェーズからいよいよ成長を志向した「攻め」のフェーズへと移行しつつあります。
最近では、ITや会計システムの進展を受けて、経営における「見える化」の重要性が強調されています。「見える化」はオペレーションを支える思考であり、リストラや企業再生という「守り」の局面では経営にとってとりわけ重要な意味をもっていました。企業がリストラを進め、体力を回復してきたこの10年間、財務的な指標を中心として経営のさまざまな側面で日本企業にも「見える化」が浸透してきました。
経営者の意思決定においてさまざまな「合理的」で「洗練された」定量的指標の活用がますます重視され、加えてコーポレート・ファイナンスや経営戦略のコンサルティングといったプロフェッショナル・サービスはこの傾向を加速しています。しかし、「見える化」は、成長に向かって新しい方向を打ち出したり、イノベーションによって変化をリードする「攻め」のフェーズでは、必ずしも有効でないばかりか、かえって企業のダイナミズムを阻害する危険があります。『楠木建の「脱コモディティ化」の戦略』では、経営が「見える化」を志向するあまり、それが「見えすぎ化」になってしまい、結果として企業をありきたりの方向へと向かわせてしまい、これがコモディティ化を進行させているという論理(「可視性の罠」)を提示してきました。「可視的な意思決定の物差し」への過度な依存が、攻めのフェーズではかえって逆機能するという仮説です。
このパネル・ディスカッションでは、それぞれに異なった専門分野で仕事をしている一橋大学大学院国際企業戦略研究科の4人、佐山展生氏(専門分野:M&A)、安田隆二氏(成長戦略)、石倉洋子氏(競争戦略)、楠木建氏(イノベーション)が登場し、「見えないものを見る力」という切り口からこれからの企業成長にとって必要となる経営力の本質について議論を深めます。
日本の経済と企業は長く続いたトンネルから抜け出し、企業経営の焦点もリストラクチャリングという「守り」のフェーズからいよいよ成長を志向した「攻め」のフェーズへと移行しつつあります。
最近では、ITや会計システムの進展を受けて、経営における「見える化」の重要性が強調されています。「見える化」はオペレーションを支える思考であり、リストラや企業再生という「守り」の局面では経営にとってとりわけ重要な意味をもっていました。企業がリストラを進め、体力を回復してきたこの10年間、財務的な指標を中心として経営のさまざまな側面で日本企業にも「見える化」が浸透してきました。
経営者の意思決定においてさまざまな「合理的」で「洗練された」定量的指標の活用がますます重視され、加えてコーポレート・ファイナンスや経営戦略のコンサルティングといったプロフェッショナル・サービスはこの傾向を加速しています。しかし、「見える化」は、成長に向かって新しい方向を打ち出したり、イノベーションによって変化をリードする「攻め」のフェーズでは、必ずしも有効でないばかりか、かえって企業のダイナミズムを阻害する危険があります。『楠木建の「脱コモディティ化」の戦略』では、経営が「見える化」を志向するあまり、それが「見えすぎ化」になってしまい、結果として企業をありきたりの方向へと向かわせてしまい、これがコモディティ化を進行させているという論理(「可視性の罠」)を提示してきました。「可視的な意思決定の物差し」への過度な依存が、攻めのフェーズではかえって逆機能するという仮説です。
このパネル・ディスカッションでは、それぞれに異なった専門分野で仕事をしている一橋大学大学院国際企業戦略研究科の4人、佐山展生氏(専門分野:M&A)、安田隆二氏(成長戦略)、石倉洋子氏(競争戦略)、楠木建氏(イノベーション)が登場し、「見えないものを見る力」という切り口からこれからの企業成長にとって必要となる経営力の本質について議論を深めます。
講師紹介




開催実績



大久保清彦 (株式会社インターナショナル・ラグジュアリー・メディア 取締役
オーシャンズ 兼 ローリングストーン日本版 発行人/編集長
セブンシーズ総研株式会社 取締役副社長)
楠木建 (一橋ビジネススクール教授)
開催日 : 2006/12/07 (木)
オーシャンズ 兼 ローリングストーン日本版 発行人/編集長
セブンシーズ総研株式会社 取締役副社長)
楠木建 (一橋ビジネススクール教授)
開催日 : 2006/12/07 (木)


募集要項
| 日時 |
2007年04月25日
(水)
19:00~21:00 |
|---|---|
| 受講料 |
5,000円 |
| 定員 | 150名 |
| 主催 |
|
| 会場 |
アカデミーヒルズ49(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー49階) ※都合により40階に変更する場合、受講生には直接ご案内いたします。 |
注目の記事
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月07日 (日) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
11月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....