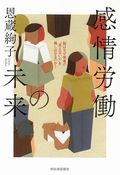記事・レポート
人事労務の法的課題
~マクドナルド判決に学ぶ企業の対応~
更新日 : 2009年03月31日
(火)
第9章 「36協定」で残業代が要らなくなるわけではない

会場からの質問: 出版社で役員をしています。編集者や記者、デザイナーなどクリエーターは、締め切り前は徹夜が当たり前で、土日も出勤という状況です。当社はサブロク協定を結んでいますが、私自身36協定を理解していなくて、これまで「会社は労働者と36協定を締結していますので残業代はない」と言っていました。そこをうまく説明するには、どのようにしたらいいでしょうか。
高谷知佐子: 36協定は、労働者に法定の労働時間を超えて残業していただくための最低限の取り決めで、締結したから残業代が要らないわけではありません。残業の前提として当然のことなので、説明をするまでもないでしょう。
ただ、出版関係ですので多くの社員が専門業務型の裁量労働制だと思います。手続きをきちんとやっているのであれば、平日の残業を気にする必要はありません。しかし休日は関係ありませんので、休日出勤をきちんと把握する注意はしてください。
また、人事や総務、経理などは専門業務型の裁量労働制とはいかないので、そこは別口として管理して残業代を払うことになります。
会場からの質問: 広告会社をしている者です。業務能力はあってもマネジメントをするのが得意じゃないという方に、「部下なし管理職」をしていただいていますが、それは管理監督者になるのでしょうか。
それと、プロジェクトによっては徹夜の業務があって裁量労働制の同意をしたのですけれど、見なしの時間が8時間となっています。ただ、どうひいき目に見ても平均8時間に収まっていない。何か手当が必要でしょうか。
高谷知佐子: 「部下なし管理職」ですが、労基法関連の通達の中には「スタッフ職」として、「会社の企画などに携わる人については、管理監督者と同じように見ていい」というのはあるのですが、それは当てはまらないということですね。
これはよくあるご質問です。今日ご説明した管理監督者の考え方からいくと、その方々は当てはまらないと思います。そういう場合、管理監督者として遇するリスクを認識してそのままいくのか、あるいは専門職で給料も高いと思うので、給料の相当部分については「時間外手当見合い」と最初から言っておき、ある程度のポーションを時間外として確保しておく、という手当をしていただくことが多いです。上場前などで、どうしても管理監督者についてきれいにしなければいけない場合、「時間外のポーションをとる」のが早いし、きれいです。
もう1つ、見なしの時間について。皆さまが実感として「8時間じゃない」と思っているのであれば、それは協定の時間を変えるのが一番正当です。
見なしの時間は通常、その業務を行うのに必要な時間です。でこぼこあるけど大体8時間であればいいですが、「でこぼこあって、やっぱり10時間」なら、10時間で協定をするのがいいと思います。ただ、いろいろな人がいるので、現状を聞いたうえで決定するのがいいでしょう。
会場からの質問: その場合、見なしが10時間となって、増えた2時間分については、追加で割増手当を支払うのですか。
高谷知佐子: そうです。そういう意味では、今よりも人件費は増えざるを得なくなります。でも、毎日全員が徹夜しているのかどうかは一応検証していただいた方がいいのではないかと思います。
(その10に続く、全10回)
高谷知佐子: 36協定は、労働者に法定の労働時間を超えて残業していただくための最低限の取り決めで、締結したから残業代が要らないわけではありません。残業の前提として当然のことなので、説明をするまでもないでしょう。
ただ、出版関係ですので多くの社員が専門業務型の裁量労働制だと思います。手続きをきちんとやっているのであれば、平日の残業を気にする必要はありません。しかし休日は関係ありませんので、休日出勤をきちんと把握する注意はしてください。
また、人事や総務、経理などは専門業務型の裁量労働制とはいかないので、そこは別口として管理して残業代を払うことになります。
会場からの質問: 広告会社をしている者です。業務能力はあってもマネジメントをするのが得意じゃないという方に、「部下なし管理職」をしていただいていますが、それは管理監督者になるのでしょうか。
それと、プロジェクトによっては徹夜の業務があって裁量労働制の同意をしたのですけれど、見なしの時間が8時間となっています。ただ、どうひいき目に見ても平均8時間に収まっていない。何か手当が必要でしょうか。
高谷知佐子: 「部下なし管理職」ですが、労基法関連の通達の中には「スタッフ職」として、「会社の企画などに携わる人については、管理監督者と同じように見ていい」というのはあるのですが、それは当てはまらないということですね。
これはよくあるご質問です。今日ご説明した管理監督者の考え方からいくと、その方々は当てはまらないと思います。そういう場合、管理監督者として遇するリスクを認識してそのままいくのか、あるいは専門職で給料も高いと思うので、給料の相当部分については「時間外手当見合い」と最初から言っておき、ある程度のポーションを時間外として確保しておく、という手当をしていただくことが多いです。上場前などで、どうしても管理監督者についてきれいにしなければいけない場合、「時間外のポーションをとる」のが早いし、きれいです。
もう1つ、見なしの時間について。皆さまが実感として「8時間じゃない」と思っているのであれば、それは協定の時間を変えるのが一番正当です。
見なしの時間は通常、その業務を行うのに必要な時間です。でこぼこあるけど大体8時間であればいいですが、「でこぼこあって、やっぱり10時間」なら、10時間で協定をするのがいいと思います。ただ、いろいろな人がいるので、現状を聞いたうえで決定するのがいいでしょう。
会場からの質問: その場合、見なしが10時間となって、増えた2時間分については、追加で割増手当を支払うのですか。
高谷知佐子: そうです。そういう意味では、今よりも人件費は増えざるを得なくなります。でも、毎日全員が徹夜しているのかどうかは一応検証していただいた方がいいのではないかと思います。
(その10に続く、全10回)
※この原稿は、2008年9月3日にアカデミーヒルズで開催した『ヒューマンリソースマネジメントの舞台裏:人事労務の法的課題~マクドナルド判決に学ぶ企業の対応~』を元に作成したものです。
人事労務の法的課題 インデックス
-
第1章 「マクドナルド判決」の背景にある労働市場環境の変化
2008年12月03日 (水)
-
第2章 法律で明確には定義されていない監督責任者とする判断基準
2008年12月12日 (金)
-
第3章 労働時間の自由裁量に関して違和感の残る裁判所の判断
2009年01月19日 (月)
-
第4章 店長系の責任・権限程度では、管理監督者と言い切れない
2009年02月05日 (木)
-
第5章 役員の1つ下のポジションは、管理監督者性を認める傾向
2009年02月27日 (金)
-
第6章 今の法制度には選択肢がなくフレキシビリティに欠ける
2009年03月06日 (金)
-
第7章 裁判所は鈍感だから方向転換できない。法改正が最良の策
2009年03月13日 (金)
-
第8章 パフォーマンス評価で残業代と賞与のバランスを図る
2009年03月23日 (月)
-
第9章 「36協定」で残業代が要らなくなるわけではない
2009年03月31日 (火)
-
第10章 時間外労働は使用者の命令に基づいて行うのが原則
2009年04月13日 (月)
注目の記事
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月07日 (日) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
11月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....