66ブッククラブ第1回
『ニュー・ダーク・エイジ』を読む
第1章 新しい「雲」を探して
アカデミーヒルズとコンテンツレーベル「黒鳥社」のコラボレーションによって始まった、新しいタイプの読書会「66ブッククラブ」の第1回が4月4日に、アカデミーヒルズで開催された。第1回目として取り上げたのはジェームズ・ブライドルによる問題作『ニュー・ダーク・エイジ』。デジタルネットワークに覆い尽くされた世界に生きる、わたしたち人間の困難を描いた本書は、さまざまな論点・コンテクストが複雑に錯綜した一冊だ。この1冊を導入として、監訳者の久保田晃弘先生、そしてゲスト読者としてデザインシンカーの池田純一さんを招き、黒鳥社コンテンツディレクター若林恵氏のファシリテートのもと参加者のみなさんと大いに議論をしつつ、『ニュー・ダーク・エイジ』から広がる、本の地図を描いてみた。
TEXT BY TAKUYA WADA , KEI WAKABAYASHI
PHOTOGRAPH BY YURI MANABE

久保田晃弘(アーティスト / 研究者)
ジェームズ・ブライドルの『ニュー・ダーク・エイジ』は、一筋縄ではいかない本だ。論点が複雑に錯綜しているため、どういうスタンスで書かれているのか、途中まで判然としない。「情報は石油より原子力に似ている」という帯を一瞥するなら、データというものの危険性を論じた警世の書としての色彩が強くもなりそうだが、単に「気をつけろ」と警告を促すだけでなく、危機を回避することはおろか、予測すらできない状況のなかにわれわれがいることを本書は強く語りかけている。
そうした状況を語るにあたって、本書が「気候変動」をひとつの大きな主題として扱っていることは強く興味を惹く。気候変動とテクノロジーの関係性はあまりに複雑に絡まり合っている。そこに人間社会の営みがあまりに深く関わってしまっているがゆえに、「気候変動に注意しよう」と言ってみたところで意味がない。といって、気候変動がもたらしうる危機を避けるために、人類全てがすべてのテクロジーを電源から引き抜いてしまう、というわけにもいかない。わたしたちの環境は、わたしたちの一挙手一投足の影響を受けて、刻一刻とその姿を変えてしまう。であるがゆえに、その環境を「客観的に計算する」ということが、もはや不可能な状態になっている。
そして、その気候変動をめぐる状況は、ネットワーク化されたコンピューターとそこを行き交う情報をめぐる環境の実態にピッタリのアナロジーだ。そうであればこそ、警世の書は、単に「データを注意して扱おう」という小手先の警告よりも、さらに踏み込んだ哲学的な色合いを帯びていくこととなる。

本書の監訳者である久保田晃弘先生は、ブッククラブに集った30−40人の参加者に向けて、こう語った。
「自然と人間を二元論的に切り離すことができないように、人が生み出したテクノロジーは、人間の一部であると共に、自然の一部でもあるわけです。本著は、テクノロジーをどう使うかではなく、自然に耳を傾けるのと同じようにテクノロジーにも耳を傾け、それが我々に何を伝えようとしているのかを読み解くための本なんです」
世界がますます捉えにくく、かつ、かつて信じられていたように「計算可能」なものではなくなっているなかで(気象というものの不確実性を乗り越え、それを征服すべくコンピュータというものが生み出され、やがて、デジタルテクノロジーが地球全体を覆うようになったことで、ますます気象が異常化し、計算が困難な状況が生まれてしまったというのはなんとも皮肉ななり行きだ)、わたしたちはいま「いったい何について考えたらよいのか」という根源的な疑問に直面している。久保田先生は、本書の価値は、「わからないものを考えることを促すところにある」と主張し、わからないものを考えるための方法として、「メタファー」の役割が本書のなかで幾度となく指摘されていることを強調する。久保田先生は、ここで、美術史家のユベール・ダミッシュの『雲の理論』という本を引き合いに出し、美術史において、「雲」というメタファーがいかに使用されてきたかを紹介する。
「19世紀初頭まで、空に浮かぶ雲を指し示す言葉は、西洋には『雲』しか存在しませんでした。けれども、観察と発見、分類や体系化とを繰り返しながら、雲は『積雲』や『層雲』などに分類、命名され、つまり発明されていったんです。美術家たちも雲にさまざまな意味を与えていくことで、自然と人を繋げていったんですね。そうした記号やメタファーの問題は、それが身近なものになってしまうと、今度はそれが逆に人の思考を固定してしまうことなんです。ですから大事なのは、そうしたメタファーを絶えず更新していくことで、それが未来につながるんです」

また、ますます不可知に、予測不可能になっていく世の中においては、「リスク」というものに対する考え方にも更新が必要だという観点から、久保田先生は2冊の本を紹介した。『悲劇的なデザイン』と『最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか』だ。
「最悪の事故や悲劇の多くは、実際は不可避でも予測不可能なものでもない場合が多いんです。むしろ、予測はできていたし、事故の明確な予兆があったにもかかわらず、人がそうした情報を故意に無視したり、認識していたのにも関わらず、何のアクションも起こさなかったことに問題があったということを、この2冊は多様な事例で紹介しつつ、また、そうした事態をいかに回避しうるかを考察してもいます。特に『悲劇的なデザイン』では、こうした人災を乗り越えていくためにデザインという領域がどういう可能性を持ちうるかを語っており、学ぶべきことが多いと思います」
『ニュー・ダーク・エイジ』はたしかに「警世の書」であり、いかにわたしたちが、困難な時代を生きているかを明かしてはいる。けれども、ブライドルが語っている通り、暗闇は「自由と可能性と平等の場所」でもある。予測不可能な世界に恐れ慄くばかりでは事態はむしろ悪くなるばかりだ。いまなにを考え、なにに取り組むべきかを、久保田先生が挙げてくださった3冊の本は、教えてくれる。
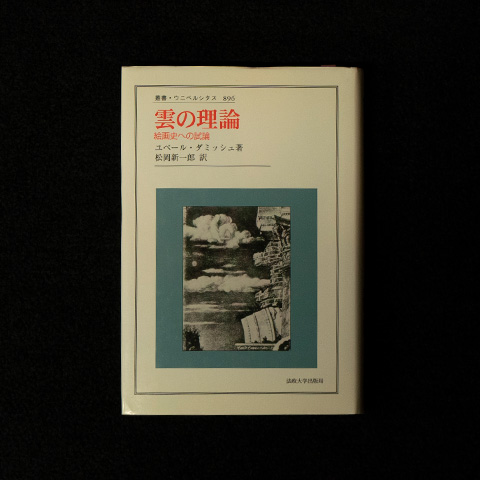
『雲の理論』
ユベール・ダミッシュ 美術史家であるユベール・ダミッシュが、絵画や彫刻、建築、写真、映画、文学などの作品を研究対象に、美術史、記号論、精神分析、人類学など多様な領域における雲の意味論を解き明かす。「『気象』と『計算』というキーワードを軸に、雲で始まり雲で終わる『ニュー・ダーク・エイジ』を語る上で、この本はとても象徴的な意味をもっています」と久保田先生。
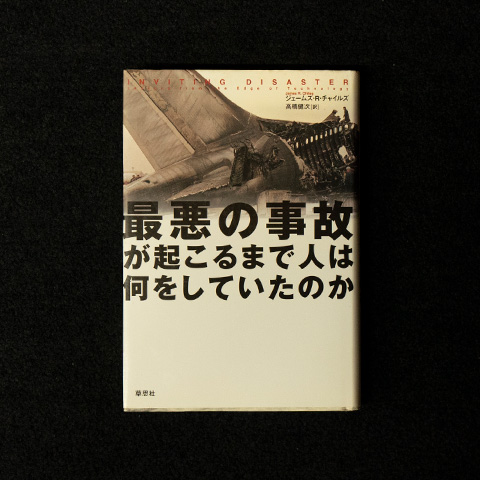
『最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか』
ジェームズ・チャイルズ ルワンダ虐殺やチェルノブイリ、スレブレニッツァなどの巨大事故のケースをもとに、それを引き起こした人的・組織的要因に迫る。「ブライドルが『ルワンダやスレブレニッツァに欠けていたのは残虐行為の証拠ではなく、それに従って行動する意志だった』と語るように、多くの悲劇は実際は人災だということを忘れてはいけないと思います」。
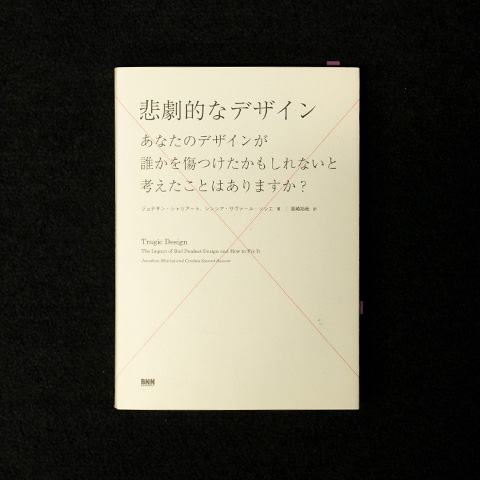
『悲劇的なデザイン』
ジョナサン・シャリアート、シンシア・サヴァール・ソシエ 2016年、米国では医療ミスにより25万人の患者がなくなっているという。そしてそこにはデザインの不備に起因する避けられた死も多く含まれている。デザインというものがもたらす公的なリスクと、それを改善するための可能性を、具体的な事例を通じて論じる。「私企業のエゴのための商業デザインでも、独りよがりな問題解決のためのデザインでもない、人間の本質を直視することで、現状を変化させるようなデザインの可能性にこそ、いま目を向けるべきなのだと思います」。
<66ブッククラブ 第3回>
<66ブッククラブ 第2回>
66ブッククラブ第1回 インデックス
-
第1章 新しい「雲」を探して
2019年05月28日 (火)
-
第2章 デジタル世界のためのエコロジー
2019年05月31日 (金)
-
第3章 空の眺め方
~『ニュー・ダーク・エイジ』からの随想~2019年07月16日 (火)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













