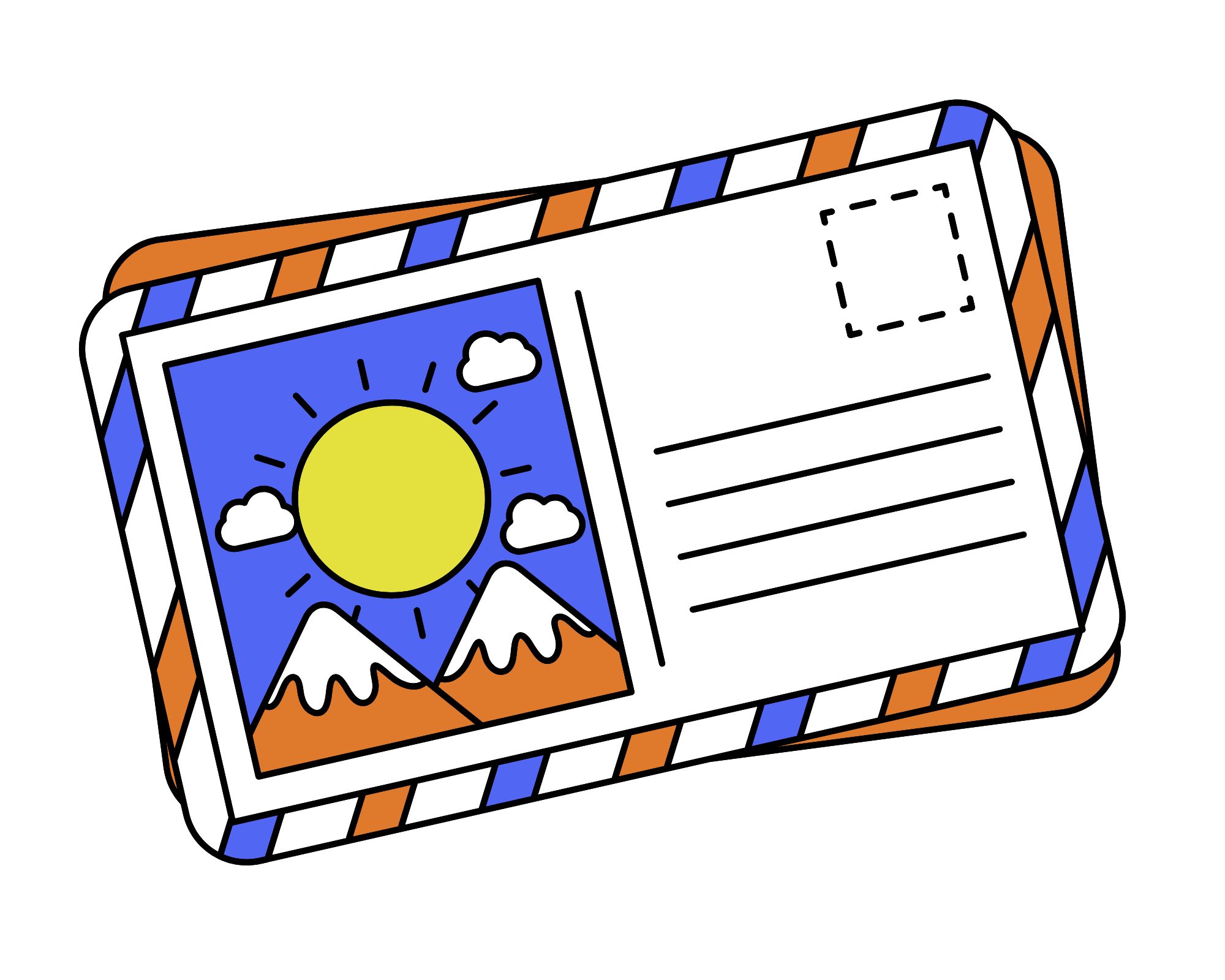記事・レポート
aiaiのなんか気になる社会のこと
【第13回】オワコンで紡ぎなおす地域の記憶と人の縁
更新日 : 2025年07月22日
(火)
【第13回】オワコンで紡ぎなおす地域の記憶と人の縁

スタートアップの祭典でオワコンを語る会
先日、京都で「日本最大級のスタートアップカンファレンス」IVSが開催された。開催期間はちょうど大学院の「現代社会起業研究」の授業がある日とも重なっていたので、学生と一緒に社会見学に出かけることにした。とはいえ入場パスは学生割で4800円、正規だとその10倍なので、数時間だけ見に行くにはハードルが高すぎると思っていたら、無料で行けるというサイドイベントを発見。キラキラのアントレプレナーが集まるこのIVSで、あえて「オワコン」ビジネスについて語ろうという異色の内容だった。「余白にこそ価値がある。京都で再考する『終わり』の先にあるビジネス」と銘打たれたこのサイドイベントは、「短期間で上場して時価総額を上げるゲーム」とは一線を画した「小さな支え合いから生まれる価値」を見直そうという、ある意味でとても京都らしい企画だ。司会は経営学者の入山章栄さん。パネリストには「オワコンプレナー」として喫茶店経営者、銭湯経営者、書店経営者、そしてオワコンプレナーへのツッコミ担当として「稼ぐことが大好き」というベンチャー投資家が招かれ、地域に根差した小商いの限界と可能性についてざっくばらんに語るという会だった。
「稼ぐ」ためではなく「残す」ために働く
オワコンプレナーたちの話は、自然とコミュニティの話になった。オワコンビジネスの多くは家族経営が基本で、コミュニティの関係性のなかで成立してきた小商いだ。オワコン化した背景には地域コミュニティの衰退や人口の流出がある。であればそのオワコンを復活させるにはコミュニティの外、例えばインバウンドを含めた拡大市場を形成することが有効なのではないか。当然ながらそういう議論も出た。お金の流れをつくるということではそれが正解なのだろう。そもそも円安なのだし、財布の紐がゆるい京都大好きのインバウンドは多少の値上げなど気にしないに違いない。しかし、この日集まったオワコンプレナーたちはその意見に与しなかった。自らを銭湯活動家と称する湊三次郎さんは「お金を稼ぎたくてやっているのではなく、銭湯というものを日本に残したくてやっている」と言い切った。湊さんは2015年に京都市下京区の「サウナの梅湯」を継業し、現在は日本各地で10軒の廃業寸前だった銭湯を経営するゆとなみ社の代表を務めている。同社のモットーは「銭湯を日本から消さない」。銭湯はそもそも公共浴場であり、入浴料さえ払えば誰でも、何も問われることなくひと風呂あびてさっぱりできる。湊さんが残したいのはそういう場所だ。そもそも入浴料は物価統制令によって規制されているが、この先値上がりするとしても「最低賃金より低く保たれるべき」と湊さんは言う。
山崎三四郎裕崇(ご本名だそうです)さんの経営する喫茶マドラグは京都では名の知られた名店だが、1963年創業の喫茶店〈セブン〉を引き継ぐかたちで始まった。この店を含めて四店舗を直営していた会社は、2023年前にサンマルク傘下に入った。山崎さんはその後もマドラグの経営に携わっている。サンマルクからは「なぜ値上げをしないのか」とプレッシャーをかけられているが、のらりくらりとやり過ごしているという。要は値上げをしたくないのだ。山崎さんは「街に残していきたい喫茶店」を守り、受け継いで行くために「京都喫茶文化遺産チーム」を結成して高齢の喫茶店オーナーの後継者探しの支援なども行っている。
私的な商いを公的に開いていく
8月に東京の大塚で書店をオープンする宇野常寛さんは「値上げするくらいなら店をやめる、という選択肢はあってもいい」という考えだ。「本屋も普通にやると潰れるしかないオワコンだけど、本の販売で採算をとらなくてもすむようなやり方がある」。「宇野書店」はオフィスビルに共用施設として入居し、ビルのあるエリア全体の付加価値を高めるというエリアマネジメント的な発想で経営するという。本を売る以外の書店の存在価値を純粋に突き詰めたビジネスモデルだ。すでに価値がなくなったとされるものを無理やり延命させるのではなく、その「精神」を受け継いでいくことがオワコンプラナーの仕事では、と宇野さんは問うた。残すべきは建物や店そのものというより「自称クリエーターが小商いを自由に始められる土壌ではないのか」と。京都市はもっとそのあたり(土壌づくり)がんばれ、という話にもなり、私的な商いを公的に開いていくことの重要性が語られた。イベントの途中からは僧侶や庭師も議論に参加して盛り上がっていくのだが、イベントレポートはこの辺までにして、ここからは少し私的なオワコン考におつきあいいただきたい。
30年目の命日に持ち寄られた「思い出の品」
2週間ほど前、30年前に亡くなった職場の後輩M君の「偲ぶ会」があった。M君は25歳という残酷な若さで亡くなったが、出会った誰もに強烈な印象を残す個性の持ち主だった。イギリスで幼年期をすごした帰国子女。日本の大学卒業後、英文ジャーナリストを目指して英字新聞の記者になった。私が彼に出会ったのはその頃だ。とにかくアイコニックな存在だった。どこで身に付けたのか知らないが、若さに似合わず自分のスタイルが確立していた。着る服、酒煙草などの嗜み、読む本、聴いている音楽、乗っている車などいちいちお洒落で、皆口には出さないが「こいつ、何者?」と思っていた。だいたい、1990年代の日本の新聞社で、定時でサクっと切り上げて、革リュックのなかからポーチを取り出し、リップクリームとまつ毛カーラーで整えて遊びに出かける男子なんてM君くらいだっただろう。それでいて嫌味がなく人懐っこくて、みんなから愛された。M君の弟、幼馴染み、大学の同級生、元同僚、元上司ら13人で富士霊園にあるお墓にお参りしてから、近くのホテルの一室でM君の思い出を語り合った。事前にこの偲ぶ会の企画者であるM君の親友のJ君から、彼にまつわる物や写真、音楽などがあればお持ちくださいという呼びかけがあったので、実家のクローゼットから汗だくになって写真や葉書を発掘して持って行った。M君の大学の同級生たちはイギリスを旅行したときの写真や、学生のときの年賀状などを持ってきた。J君はそのイギリス旅行のときにM君が出したという絵葉書を持ってきた。M君はJ君に絵葉書を送るときはなぜかいつも英語で書いていた。大学時代の友人であるSさんは、スウェーデン製のリールを持ってきた。M君は色違いを持っていて、二人でよく釣りにいったそうだ。
その日、全員が「自分とM君との関係性」という点においてのみ自己紹介をした。それがすがすがしかった。元同僚のNさんは、一緒に遊びにいったり、一緒に飲みにいったりしたことはなく、彼のことをそこまで知っているというわけではないけれど、みんなの話をきいて、彼に改めて出会ったような気持ちになったと話した。人は亡くなってもまた出会うことができるのだ。その場にいた誰もが自分の知らなかったM君の素顔に触れ、それぞれにM君と出会いなおしたのだった。
誰か1人のためのメッセージと時間
このときに感じたのは「モノ」や「場所」のもつ記憶を喚起する力だ。お墓という物理的な場所がなければ、わたしたちはこんなふうには集まれなかった。もちろん貸し会議室などでやることは可能だけれど、天候を気にしながら霊園まで向かい、墓石を磨き、花を捧げ、墓前で祈ったり歌をうたったりといった一連の儀式は、冷房の効いた部屋の中では無機質で形式的なものになってしまう気がする。思い出の品でいちばん多かったのがプリント写真だ。当時はフィルム式の写真で、「映える」という意識もなく、みんな無防備な表情で写っている。トリミングも修正もしていない色褪せた写真には、記憶をよびさます強烈なパワーがあった。そして葉書。筆跡、誤字脱字、その頃の住所、そこに記された固有名詞や言葉遣い、それらが総合的に一つの時間のかたまりとなってそこにある。「P.S. おまえ留年するの?」という葉書の余白ぎりぎりに書き込まれた一言。30年間判読されなかったほど難解な英語の走り書き。デジタルのメッセージにはないざらざらした情報が30年経ってもそこにある。そしてなにより絵葉書というのは誰か1人にあてた言葉と時間をとどめたモノであることにいまさら感動を覚えた。SNSで、誰だか思い出せないような薄いつながりの人間にまで「こんな素晴らしいところに来ています、私!」と映える写真を発信する時代に、絵葉書は完全にオワコンだ。スマホが社会インフラとなった今の時代に故人の写真を持ち寄ることになったら、仲のいい人たちからたちまち何十枚、もしかしたら何百枚という写真が集まるだろう。しかしそれを全部あわせても、色褪せたプリントの写真や、意味の分からない走り書きのあるポケットアルバムや、宛名の漢字を間違えた絵葉書以上のことを伝えることができるだろうか。
場所やモノから立ち上る本質
デジタルがアナログにとってかわって、フィルム写真や絵葉書や手紙は完全にオワコンになって久しい。家族単位のお墓もオワコンかもしれない。でもこれらの手触りのあるモノを真ん中において人が集い、語り合うとき、なにかデジタルでは表現できない存在が立ち上るような気がする。場所やモノはなくなっても、そこに宿っている「精神」が残っていけばよいという考え方は、ひとつの希望ではあるが、場所やモノが残っているからこそそこから醸し出される本質のようなものもある。ただこの「偲ぶ会」が実現したのも、SNSでのメッセージのやりとりが可能だったからこそで、これが昔ながらの「手紙」でのやりとりだったら、没後30年の命日当日に13人もの人が一堂に会することはできなかっただろう。オワコンは、ただ終わっているのではなくて、テクノロジーの力もかりながら、終わらせられないものにうまく再接続できたときに息を吹き返すのではないだろうか。
執筆者:中嶋 愛
Glass Rockプログラムディレクター。編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。
Glass Rock ~ Social Action Community ~
Glass Rockは、クロスセクターの連携と共創により社会課題の解決を目指す会員制拠点です。コミュニティ運営の専門家が支える「つながる」場、実践的な学びや対話を生み出す「まなぶ」仕掛け、そしてギャラリーやスタジオなどから「ひろげる」発信機能を有します。これらの「場」と「仕掛け」を通じてクロスセクターの連携と共創を促進し、「社会課題解決」に向けたイノベーションの創出と持続可能な社会の実現に貢献します。
https://www.glass-rock.com/index.html

aiaiのなんか気になる社会のこと インデックス
-
【第1回】ドラッカー曰く「世界最古のNPOは日本のお寺?!」
2024年07月23日 (火)
-
【第2回】「コンヴィヴィアリティ」の視点で、厳しい暑さを乗り切るには?
2024年08月21日 (水)
-
【第3回】美術館は誰のもの?「正の外部性」から考えてみる
2024年09月24日 (火)
-
【第4回】「15分都市」という選択 住み心地のいい街の条件とは?
2024年10月22日 (火)
-
【第5回】私たちは「コモングッド」を取り戻せるか
2024年11月20日 (水)
-
【第6回】世の中は「虚構」で成り立っているという衝撃
2024年12月24日 (火)
-
【第7回】政治の話は嫌いですか ~ポリティカルイノベーション事始め~
2025年01月21日 (火)
-
【第8回】「コーヒーの一生」から見えてくる風景
2025年02月25日 (火)
-
【第9回】なぜ日本の学校では子どもたちが掃除をするのか
2025年03月25日 (火)
-
【第10回】柳宗悦の蒐集論がおしえてくれること
私欲が利他に転換するとき
2025年04月22日 (火)
-
【第11回】「最強のパスポート」を持っているということ
命をかけなくても越境できる「特権」
2025年05月27日 (火)
-
【第12回】履き古したランニングシューズはどうしたものか
2025年06月24日 (火)
-
【第13回】オワコンで紡ぎなおす地域の記憶と人の縁
2025年07月22日 (火)
-
第14回 私たちは「物語的不正義」にどう立ち向かうのか ~他者の語りに人生を絡めとられないために~
2025年08月25日 (月)
-
第15回 なぜクマ問題はみんなの問題なのか ~駆除か共生かの二項対立を越えて~
2025年09月22日 (月)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....