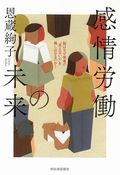記事・レポート
「世界の都市総合ランキング 2011」で4位だった東京の将来性は?
~東京の磁力を回復し、優秀な人材や企業を惹きつけろ~
東京政治・経済・国際経営戦略
更新日 : 2012年04月16日
(月)
第8章 世界に類を見ない「東京モデル」の行方

市川宏雄: なぜ私が皆さんと若干違って「来年(2012年)のランキングも今年と同じ4位だろう」と考えたのか、その理由をご説明いたします。
東京は、最初はロンドンの、次にニューヨークのまねをして政策をやってきて、今は世界にモデルのない「東京モデル」をつくっています。東京都市圏の人口3,500万人というのは先進国で最大で、ほかに例がないのです。この巨大な都市圏を若干の問題はあっても、一応淡々と運営しているわけです。このノウハウこそ輸出すればいいと私は思います。東京はそういうすごい都市なのです。ですから現在第2グループのシンガポールなどが迫ってきているといっても、来年ぐらいは決して負けないと思います。だから「来年も4位」を選んだのです。
では、なぜこの東京がうまくいっているかというと、東京に関わるすべての人が、それぞれ自分の役割を担ってきたからだと私は思います。都市計画や都市運営については行政が、開発は民間会社が一所懸命考えてやってきたのです。その結果、先ほどの大縄跳びではありませんが、みんなバラバラに考えていたけれど、総体としてうまくやってこれたのです。
問題は、このモデルが今後も続くかどうかです。世界の都市間競争の中で「東京モデルは果たして可能か」ということです。この先抜かれるとすれば、このモデルが崩壊するか、あるいは別のモデルが現れて抜かれるか、どちらかしかありません。それがいつ来るかです。
猪瀬直樹: 市川さんのお話につなげて、今度はさっきと逆のことを言います。日本は戦争をやらずに来たことで、仕事をゆっくり緻密にできる時間を得られました。
例えば約270年続いた江戸時代には、大阪の堂島で米の先物取引が行われていました。これはデリバティブのもとになったものです。また、江戸時代には水道がすでにありました。多摩川の水を引いて、江戸市中に水を行き渡らせていたんです。その水路である玉川上水は全長43km、標高差はわずか92mです。これほど緩い勾配で40km以上も水を引くわけですから、非常に緻密な技術です。
こうした技術やものの考え方は、270年間かけて積み重ねてきたものですから、第二次世界大戦後に独立した国々の都市とは近代化の歴史が違います。だからアジアの都市が、いくら今からやっても多分追いつくことはできません。上海が地下鉄をつくるスピードは確かに早いのですが、成熟度という面では、東京のそれは世界に類を見ないものです。そこは誇りと自信を持っていいんです。
竹中平蔵: きょうは「多様性」というキーワードが登場しました。東京は多様な魅力と、多様な問題を抱えているということだと思います。
猪瀬さんのお話にもありましたが、江戸の街は本当にすごいんです。例えば排泄物を集めて下肥として農家に売り、農家はそれを使って農業の生産性を高めていました。こうしたシステムが回る社会だったのです。その後、鉄道をつくりはじめ、1925年に山手線の環状運転が始まったときには、当初から10分おきぐらいに電車を走らせることができました。これは非常に高いオペレーション能力です。そういう大きなものの上に成り立っている東京が、さまざまな魅力をつくり出しているというのは事実だと思います。しかしその一方で、東京で再開発が行われている所というのは、ほとんどが旧日本国有鉄道清算事業団で吐き出された土地で、それ以上の再開発は本当に進んでいないという面もあるわけです。
「これさえやれば解決する」という打ち出の小槌のような方策はありません。解決策はこれからみんなで考えていかなければならないのです。是非、きょうの議論を今後の東京を考える1つのきっかけにしていただければと思います。
——最後に再び会場の参加者にアンケートを実施し、「希望ではなく、現実的な問題として東京のランキングを上げることができると思いますか?」と聞いたところ、101名が「できる」と回答しました。
東京は、最初はロンドンの、次にニューヨークのまねをして政策をやってきて、今は世界にモデルのない「東京モデル」をつくっています。東京都市圏の人口3,500万人というのは先進国で最大で、ほかに例がないのです。この巨大な都市圏を若干の問題はあっても、一応淡々と運営しているわけです。このノウハウこそ輸出すればいいと私は思います。東京はそういうすごい都市なのです。ですから現在第2グループのシンガポールなどが迫ってきているといっても、来年ぐらいは決して負けないと思います。だから「来年も4位」を選んだのです。
では、なぜこの東京がうまくいっているかというと、東京に関わるすべての人が、それぞれ自分の役割を担ってきたからだと私は思います。都市計画や都市運営については行政が、開発は民間会社が一所懸命考えてやってきたのです。その結果、先ほどの大縄跳びではありませんが、みんなバラバラに考えていたけれど、総体としてうまくやってこれたのです。
問題は、このモデルが今後も続くかどうかです。世界の都市間競争の中で「東京モデルは果たして可能か」ということです。この先抜かれるとすれば、このモデルが崩壊するか、あるいは別のモデルが現れて抜かれるか、どちらかしかありません。それがいつ来るかです。
猪瀬直樹: 市川さんのお話につなげて、今度はさっきと逆のことを言います。日本は戦争をやらずに来たことで、仕事をゆっくり緻密にできる時間を得られました。
例えば約270年続いた江戸時代には、大阪の堂島で米の先物取引が行われていました。これはデリバティブのもとになったものです。また、江戸時代には水道がすでにありました。多摩川の水を引いて、江戸市中に水を行き渡らせていたんです。その水路である玉川上水は全長43km、標高差はわずか92mです。これほど緩い勾配で40km以上も水を引くわけですから、非常に緻密な技術です。
こうした技術やものの考え方は、270年間かけて積み重ねてきたものですから、第二次世界大戦後に独立した国々の都市とは近代化の歴史が違います。だからアジアの都市が、いくら今からやっても多分追いつくことはできません。上海が地下鉄をつくるスピードは確かに早いのですが、成熟度という面では、東京のそれは世界に類を見ないものです。そこは誇りと自信を持っていいんです。
竹中平蔵: きょうは「多様性」というキーワードが登場しました。東京は多様な魅力と、多様な問題を抱えているということだと思います。
猪瀬さんのお話にもありましたが、江戸の街は本当にすごいんです。例えば排泄物を集めて下肥として農家に売り、農家はそれを使って農業の生産性を高めていました。こうしたシステムが回る社会だったのです。その後、鉄道をつくりはじめ、1925年に山手線の環状運転が始まったときには、当初から10分おきぐらいに電車を走らせることができました。これは非常に高いオペレーション能力です。そういう大きなものの上に成り立っている東京が、さまざまな魅力をつくり出しているというのは事実だと思います。しかしその一方で、東京で再開発が行われている所というのは、ほとんどが旧日本国有鉄道清算事業団で吐き出された土地で、それ以上の再開発は本当に進んでいないという面もあるわけです。
「これさえやれば解決する」という打ち出の小槌のような方策はありません。解決策はこれからみんなで考えていかなければならないのです。是非、きょうの議論を今後の東京を考える1つのきっかけにしていただければと思います。
——最後に再び会場の参加者にアンケートを実施し、「希望ではなく、現実的な問題として東京のランキングを上げることができると思いますか?」と聞いたところ、101名が「できる」と回答しました。
「世界の都市総合ランキング 2011」で4位だった東京の将来性は? インデックス
-
第1章 都市の“磁力”が優秀な人材や企業を惹きつける
2012年04月03日 (火)
-
第2章 東京は経営者からの評価が低い
2012年04月05日 (木)
-
第3章 迫り来るアジアの都市
2012年04月06日 (金)
-
第4章 東京の実力と将来性~水道技術と天然ガス発電所~
2012年04月09日 (月)
-
第5章 日本はグローバル競争に対する危機感が足りない
2012年04月10日 (火)
-
第6章 東京の弱点を克服する方法
2012年04月12日 (木)
-
第7章 東京のブレークスルー・ポイント~例えば多様性~
2012年04月13日 (金)
-
第8章 世界に類を見ない「東京モデル」の行方
2012年04月16日 (月)
該当講座
東京の磁力を回復する
~「世界の都市総合力ランキングGPCI-2011」からみた東京の未来展望~
猪瀬直樹 (東京都副知事・作家)
GLEN S. FUKUSHIMA (エアバス・ジャパン株式会社 取締役会長 元在日米国商工会議所会頭 )
竹中平蔵 (アカデミーヒルズ理事長/慶應義塾大学名誉教授)
市川宏雄 (明治大学専門職大学院長 公共政策大学院ガバナンス研究科長・教授 )
GLEN S. FUKUSHIMA (エアバス・ジャパン株式会社 取締役会長 元在日米国商工会議所会頭 )
竹中平蔵 (アカデミーヒルズ理事長/慶應義塾大学名誉教授)
市川宏雄 (明治大学専門職大学院長 公共政策大学院ガバナンス研究科長・教授 )
猪瀬 直樹(東京都副知事)グレン・S・フクシマ(エアバス・ジャパン㈱取締役会長)竹中平蔵(慶應義塾大学教授)市川 宏雄(明治大学専門職大学院長)
東京」の磁力を回復させ世界から人々を呼び込むために、何が課題で、何をすべきかを明確にすることは、日本全体の未来を考えるうえで、必須命題ではないでしょうか。『都市総合力ランキング』という客観的データを基に、多面的な視点からの意見を交わし、日本そしてグローバル・シティ「東京」が緊急に解決すべき課題を明らかにします。
東京
政治・経済・国際 経営戦略

注目の記事
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月07日 (日) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
11月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....