記事・レポート
aiaiのなんか気になる社会のこと
【第14回】私たちは「物語的不正義」にどう立ち向かうのか
~他者の語りに人生を絡めとられないために~
更新日 : 2025年08月25日
(月)
第14回 私たちは「物語的不正義」にどう立ち向かうのか ~他者の語りに人生を絡めとられないために~
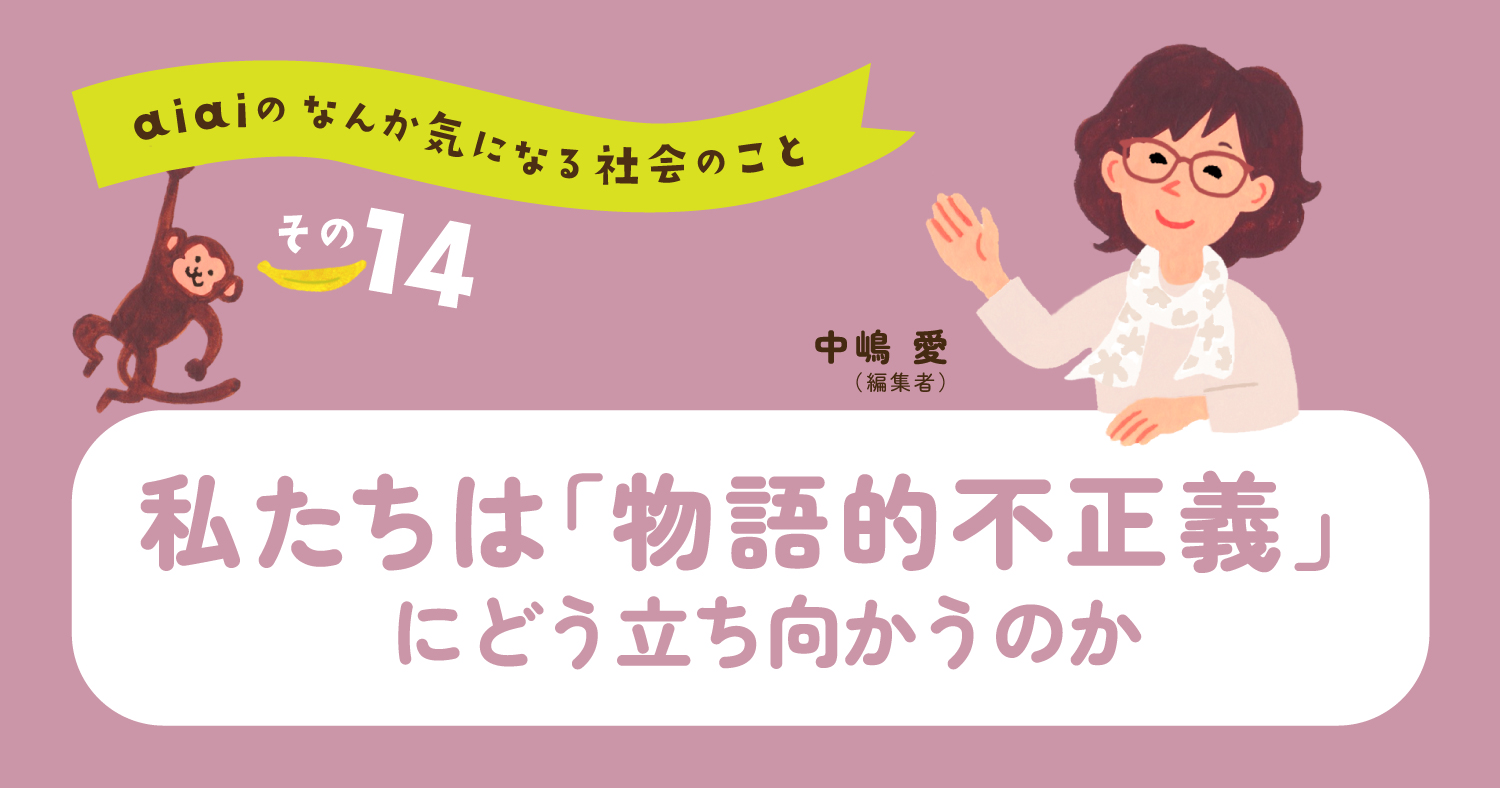
ヘラルボニーという会社がある。障がい者のアートをグローバル市場で取引するギャラリーは、大企業や有名ブランドと組んだプロジェクトも多々あり、公式オンラインストアでは服や雑貨なども売っている。社名を知らない人でもどこかでヘラルボニーの作家の作品を目にしたことがあるだろう。ヘラルボニーの成功要因のひとつは、ブランドストーリーの秀逸さだ。創業者の松田文登・崇弥の双子の兄弟は、自閉症である自分たちの兄の作品を売り出すことを目的にした会社を、兄の造語である「ヘラルボニー」と名付けた。彼らにとって兄はまず兄であって、障がい者というレッテルは社会が勝手につけたものだった。
ヘラルボニーが書き換えた古い「障がい者」の物語
「障がい者でありながら素晴らしい創造性がある」という「障がい者はできなくてあたりまえ」という無意識の偏見をひっくり返したくて、「普通の」芸術作品として勝負する。ヘラルボニーの作家を障がい者扱いしない姿勢は、障がい者を福祉という既存の文脈から外に出すという意味で主流だった物語を書き換えた。この新しい物語は多くの支援者、投資家の心に刺さった。それは支援する側とされる側という居心地の悪い関係に楔をうつ考え方であると同時に、施しではなく投資や事業提携という対等の関係の前提にもなったからだ。当然、投資のほうが出せる金額も出したいという人も多くなる。いまやヘラルボニーは海外にも進出し、自社主催のアワードなども創設してますます注目を集めている。もちろんヘラルボニーの成功は物語を裏打ちする実を伴うものであったからに違いないが、これまでも障がい者に対して社会が押し付けてくる物語を上書きしようという試みはあった。たとえば「障がいの社会モデル」という考え方がある。これは、障がいは個人の身体的・精神的な機能不全に起因する問題という考え方(障がいの医学モデル)から、障がいは社会の制度的設計や文化的な受容度に起因する問題であるという考え方への転換だった。障がいの社会モデルは学術界、国連などの国際機関、障がい者運動の現場では常識となっているが、一般社会においては医学モデルが根強く残っている。
ヘラルボニーの物語はその溝を一気に乗り越えるような力を持っている。それはアートというものの力にもよるのかもしれない。一方で、彼らの新しい物語があまりにも鮮やかでパワフルであるがゆえに、障がい者と支援者、障がい者とアートをめぐる他の物語を意図せず周縁化してしまう可能性もある。
なぜ物語がこれほどの力を持つようになったのか
物語はときとして効きすぎる薬にもなる。あまりにも強い物語は、最悪の場合、人から幸福を奪ってしまうのではないか。そんな警鐘を鳴らすのが『物語批判の哲学』を書いた美学者の難波優輝だ。本書は「あらゆるところで『物語』がもてはやされている。私はそれが不愉快である」という挑発的な文章で始まる。難波は物語の作者でもあり研究者でもあり、物語のもつ力と可能性を信じてきた人だが、昨今の物語の盛り上がりを見て、それが「もっぱら悪い方に作用しているのではないか」と感じ始めた。なぜ物語がこれほどの力を持つようになったのか。本書では3つの仮説をあげている。1.お互いに自分が誰であるかを説明する必要性
2.他者に影響力を与えたいという欲望
3.自分を他者と差別化したいという願望
これらと関連して、いわゆる「大きな物語」が後退することによる「小さな物語」の拡散とそれによる物語のコモディティ化という現象もあるだろう。その結果、より「強い」「エモい」「怖い」物語が志向されるようになった。物語はアテンションエコノミーを勝ち抜くための基本装備である。
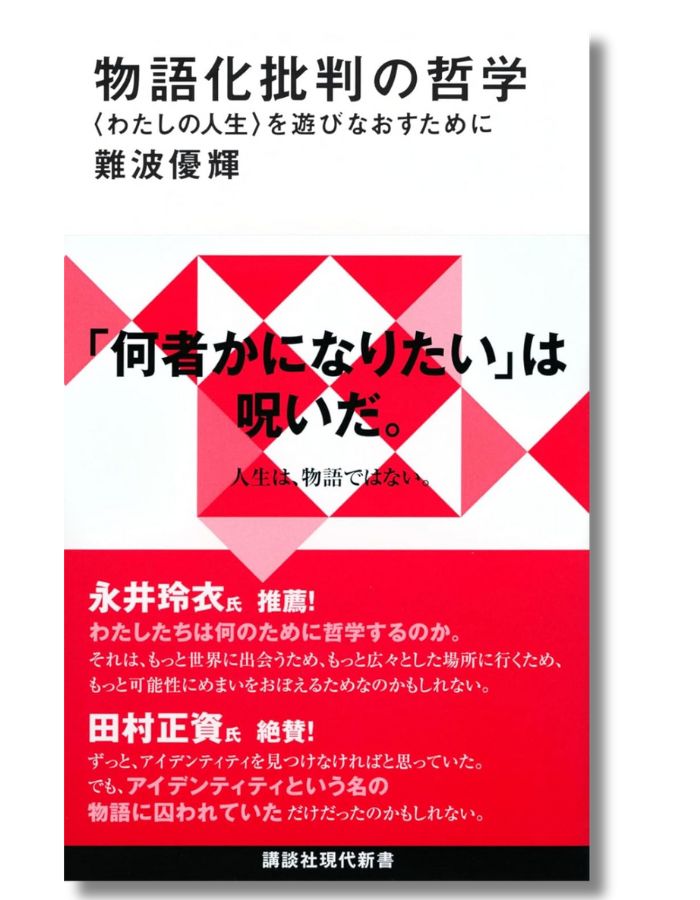
他人語りによる「物語的不正義」
自分の欲望や願望を物語の力をとおしてかなえようとする行為には、弊害を伴うことがある、と難波は指摘する。理解し合うという名目での物語の押し付け合い。他人に何かをさせるための物語による情動の上書き。そして理想の自分の物語にこだわることによる硬直したアイデンティティ。物語への需要の高まりと相まってこうした副作用が顕著になっていることを、物語のプロでもある難波は「何かがおかしい」と表現する。伝統的なコミュニティで一生を終えるのではなくデジタル空間も含めてさまざまなコミュニティに生きるようになった私たちは、自分の物語を発信しながら生きることが日常的な行為となった。難波によれば、この自分語りには「改訂排除性」と「目的閉塞性」という2つの罠が潜んでいる。話の内容を他者から修正されることもなく、自分が好きなように意味付けできるため、独善的なものになりやすいということだ。ただ自分のことをどう語ろうと基本的には自由だし、時と場合に応じて語り分けることも悪いことではない。問題は「自己語りの枠組み」で「他人語り」をすることだ。物語の最大の弊害はそこにあるといっていい。なぜなら他人語りをすることで「他人が他人自身を解釈する自由を奪い、解釈を一方的に決めてしまうような危害を与える可能性」があるからだ。難波はこれを「物語的不正義」と呼ぶ。
この背景には「人々は、しばしば、物語的に他人を理解することで気持ちよくなってしまう」ことがある。他人の問題について自分のほうがより明確に見えている、わかっているという錯覚、いわゆる「明晰さの誘惑(C・ティ・グエン)」である。難波は言う。「この気持ちよさに抗い、相手を理解できないものとして尊重すること、それが物語的徳である」。
「地域活性化」の現場は誰の言葉で語られているか
「自己語りの枠組みで他者語りをする」ことがなかば当たりまえになっているのが地方創生の現場ではないだろうか。秋田県でサステイナビリティの研究と実践にとりくむ工藤尚悟(国際教養大学准教授)は、新著『〈わたし〉からはじめる地方論』の冒頭でこんなふうに述べている。「地域は『限界』をむかえており、『活性化』でこれを防がなければならないーー。
あまりにもあたりまえに語られるこうした言葉には、圧倒的に欠けているものがある。
それは、その地域に暮らしている一人ひとりの〈わたし〉の視点である」
この本は「中央によってつくられた言葉で描かれてきた地方像をときほぐし、地方側からの言葉を使いながら、地域の将来像を語るという作業」として書かれた。地方創生や災害復興にありがちな当事者不在の問題は、人的、経済的リソースの都市への偏在が根底にある。リソースの偏在はやむをえないとしても、「語り」まで依存することがよいのか、という問題提起だ。
工藤はこの本で「地域を語る言葉」の行き詰まりを指摘している。「限界集落」はもともと学術的な概念の一部であったものが社会課題とその対策という文脈で拡大解釈して使われるようになった。「地域活性化」という言葉は、外からやってくる活性化の専門家と、活性化「される」側の非対称的な力関係の象徴になっている。「関係人口」という言葉は、地方の外からやってきて地域を解決する人という一方向的な視点に立っている。一人称の〈わたし〉で地方のこれからを議論していくことは、こうした行き詰まりを乗り越えるための一歩である。と同時にそれは「物語不正義」への抵抗にもなりうる。
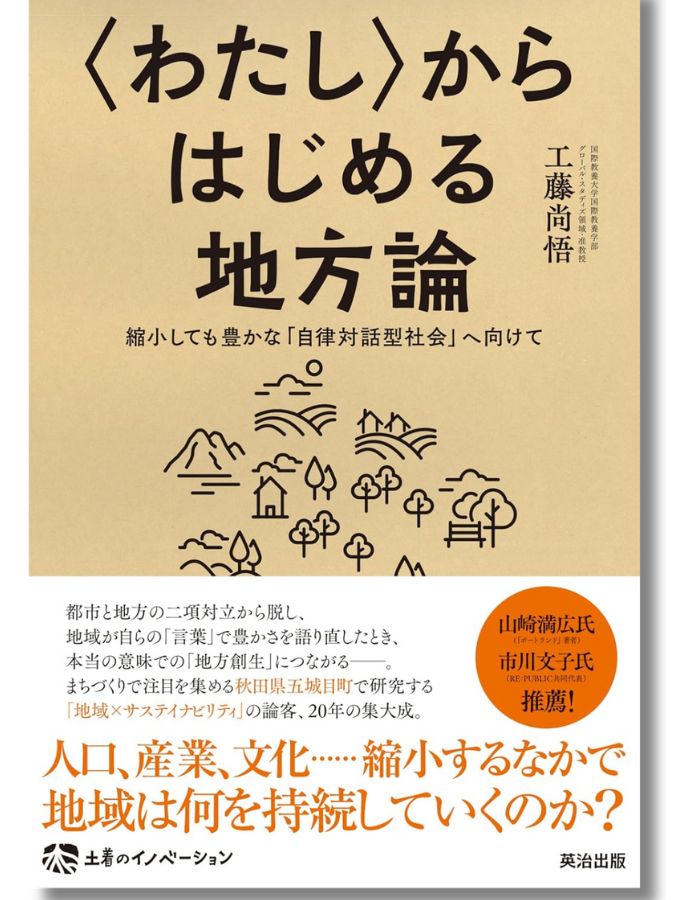
理解できないことを無理に理解しようとしない勇気
人口減少を「解決すべき課題」ととらえ、「成功事例」や「優良事例」といった物語に落とし込むという流れは、前出の難波が言うところの「マスタープロット(世間に広く受け入れられている物語)」をなぞる行為だ。これに対抗する「カウンタープロット」をつくるためにはなにが必要だろうか。工藤にいわせればそれは「地域の内側から湧き出てくる言葉を用いて、自分たちの将来について語る」ことだ。課題解決という文脈ではなく、日常のなかで「地域について語る時間」をもつこと、そこに地域住民同士の会話と外から関わるひとたちとの会話がいい塩梅で交じりあっていることが、工藤の提案している「自律対話型社会」のひとつの指標である。この「自律対話型社会」の模索は、工藤がフィールドとする秋田県五城目町(ごじょうめまち)も含めて、いたるところで始まっている。こうした対話を通じて、たとえば「人口減による地方の衰退」といった外側から見た「社会課題」が解体され、地域の具体的な問題として再構築されていくことが期待できる。ただしその前提として、難波の提唱する「物語的徳」が対話のなかで実践される必要がある。以下はその要諦だ。
1.不必要に他人を物語的に理解するのでなく、いまの自分の理解を手放し、相手を物語叙述の世界に閉じ込めないこと
2.いつ物語的理解を行うべきで、いつ行うべきでないかを判断する能力を身に付けること
3.物語的には理解不可能な相手を相手の言い分を聞くことで理解しようとすること
「理解できないことを無理に『理解しようとしない』勇気。物語に還元できない断片的な声を『断片のまま』受容する創造力」を養う。これはこのまま、AIによる物語に絡み取られないための智恵としても読めるのではないだろうか。
執筆者:中嶋 愛
Glass Rockプログラムディレクター。編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。
参考文献
物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために
難波優輝講談社
〈わたし〉からはじめる地方論——縮小しても豊かな「自律対話型社会」へ向けて
工藤尚悟英治出版
Glass Rock ~ Social Action Community ~
Glass Rockは、クロスセクターの連携と共創により社会課題の解決を目指す会員制拠点です。コミュニティ運営の専門家が支える「つながる」場、実践的な学びや対話を生み出す「まなぶ」仕掛け、そしてギャラリーやスタジオなどから「ひろげる」発信機能を有します。これらの「場」と「仕掛け」を通じてクロスセクターの連携と共創を促進し、「社会課題解決」に向けたイノベーションの創出と持続可能な社会の実現に貢献します。
https://www.glass-rock.com/index.html

aiaiのなんか気になる社会のこと インデックス
-
【第1回】ドラッカー曰く「世界最古のNPOは日本のお寺?!」
2024年07月23日 (火)
-
【第2回】「コンヴィヴィアリティ」の視点で、厳しい暑さを乗り切るには?
2024年08月21日 (水)
-
【第3回】美術館は誰のもの?「正の外部性」から考えてみる
2024年09月24日 (火)
-
【第4回】「15分都市」という選択 住み心地のいい街の条件とは?
2024年10月22日 (火)
-
【第5回】私たちは「コモングッド」を取り戻せるか
2024年11月20日 (水)
-
【第6回】世の中は「虚構」で成り立っているという衝撃
2024年12月24日 (火)
-
【第7回】政治の話は嫌いですか ~ポリティカルイノベーション事始め~
2025年01月21日 (火)
-
【第8回】「コーヒーの一生」から見えてくる風景
2025年02月25日 (火)
-
【第9回】なぜ日本の学校では子どもたちが掃除をするのか
2025年03月25日 (火)
-
【第10回】柳宗悦の蒐集論がおしえてくれること
私欲が利他に転換するとき
2025年04月22日 (火)
-
【第11回】「最強のパスポート」を持っているということ
命をかけなくても越境できる「特権」
2025年05月27日 (火)
-
【第12回】履き古したランニングシューズはどうしたものか
2025年06月24日 (火)
-
【第13回】オワコンで紡ぎなおす地域の記憶と人の縁
2025年07月22日 (火)
-
第14回 私たちは「物語的不正義」にどう立ち向かうのか ~他者の語りに人生を絡めとられないために~
2025年08月25日 (月)
-
第15回 なぜクマ問題はみんなの問題なのか ~駆除か共生かの二項対立を越えて~
2025年09月22日 (月)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













