記事・レポート
日本発「無印良品」から世界の「MUJI」へ
~ケロッグ経営大学院 モーニングセッションより
地球規模で「消費の未来」を見通す
更新日 : 2015年10月07日
(水)
第1章 消費社会に対するアンチテーゼ
1991年、ロンドンに海外第1号店をオープンし、現在は25カ国・地域に約300店舗以上を展開する「無印良品」。ケロッグ経営大学院の卒業生であり、無印良品を展開する株式会社良品計画の取締役・執行役員を務める鈴木啓氏は、8年半にわたり欧州事業を統括するなど、同社の海外展開を牽引されてきた方です。鈴木氏に無印良品の誕生秘話から、グローバル展開の歴史、同社のコンセプトを具現化した社会貢献活動まで解説していただきました。
スピーカー:鈴木啓 (株式会社 良品計画 取締役・執行役員/生活雑貨部長)

鈴木啓 (株式会社 良品計画 取締役・執行役員/生活雑貨部長)
スタートは1980年
鈴木啓: ケロッグ経営大学院で学んだ2年間は、私にとって何ものにも変えがたい日々でした。そうしたケロッグのコミュニティに対し、以前から何か恩返しができないかと考えていたため、このような機会をいただき、非常に嬉しく感じております。
さて、私達は皆さんにもおなじみの「無印良品」というお店を展開しています。正式な会社名は、「株式会社良品計画」といいます。1989年に設立し、2014年末の段階では国内で約400、海外で25カ国・地域に約300店舗を展開しており、従業員数は社員・パート・アルバイトを含め国内5,951名、海外5,082名です。主な事業は、無印良品を中心とした専門店事業のほか、住宅事業、飲食事業、キャンプ場の運営なども手掛けています。
設立は1989年ですが、コンセプトは1980年に誕生しています。当初は西友のプライベートブランドとして、事業とは言えないほどの小さな規模から始まりました。一般的な企業の場合、会社が設立され、その後にコンセプトが市場で認知され、浸透していきます。しかし、我々の場合は最初から明確なコンセプトがあり、それを起点として西友の自社開発が始まり、事業部に発展し、独立会社となりました。一般的な企業とは真逆のルートで発展してきた点が大きな特徴です。
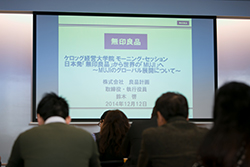
自然と人とモノの関係を常に考える
鈴木啓: 無印良品は、2人の人物の想いから始まりました。セゾングループを率いた堤清二さんと、日本を代表するグラフィックデザイナーである田中一光さんです。
1980年当時、日本社会の潮流は大量生産・大量消費のど真ん中にあり、需要よりも供給が大きく上回っていました。そのため、多くの企業は狭義の意味でのデザインを毎年のように改変し、狭義の意味でのマーケティング、ブランディング手法を駆使して、無理やりのようにモノを売っていました。
堤さんは小売業界を牽引する存在でありながら、一方では文化に対する造詣が深く、社会課題に対する意識も非常に強い方でした。また、グラフィックデザイナーとして多方面で活躍されていた田中さんは、狭義のデザインをするのではなく、社会や人間のあるべき姿や方向性を鋭く洞察し、それを形にされていました。
資本主義の論理が優先され、人間の本質的な論理が置き去りにされた状況に危機感を覚えた2人が出会い、「消費社会に対するアンチテーゼ」として生み出したもの。それが無印良品です。田中先生は、「我々が行うべきは、自然と人とモノの関係を常に考えることであり、商いを通じた社会貢献だ」と言っておられました。
普段は社外に出さないのですが、事業の立ち上げに際して書かれたメモがあります。この中に、今もなお我々の根底に流れる想いが凝縮されています。
・商業主義による、狭義のデザインの氾濫に対するアンチテーゼ。
・大量生産、大量消費、大量廃棄への批評。
・一人ひとりの個性を尊重し、コマーシャリズムの要素や無駄を排除することで、個性をユーザーに委ねる。
・消費をブランド名やデザイナー名で誘導しない。
・地球環境や生産者への配慮を含め、「最良の生活者」を探求する。
無印良品では、透明なガラスのコップを販売しています。しかし、棚に付けられた商品名は「ガラス器」です。つまり、「売る側で使い方を限定しない」というメッセージです。ガラス器ならコップだけでなく、花瓶、ペン立てなど、使い方はお客様の自由です。
もう1つ、創業当初の商品タグと現在のタグでは異なる点があります。創業当初のタグには、ブランド名が一切入っていませんでした。田中さんは徹底して「無印」にこだわり、小さな商品タグにすらブランド名を入れたくないと言われていました。
当時は、ブランドのマークを付けて価格を高くしているような商品もたくさんありました。消費者にとって価値をなさないブランド名を付け、消費を誘導することはおかしい。ノーブランド(無印)でありながらも、消費者にとって本当に価値のある良い商品をつくろう。そうした想いから無印良品という名前が生まれました。当時は横文字やカタカナのブランド名が流行していましたが、私達の想いをストレートに伝えるため、あえて日本語の名前を付けたそうです。
なお、近年はコピー商品も数多く出回るようになったため、知的財産権を守る意味から商品タグにブランド名を小さく記載しており、洗濯表示のタグも法律で企業名を入れることになっています。しかし、それ以外、商品のどこにもブランド名は記載されていません。文具や家具も、商品タグのシールをはがせば、ブランド名がなくなります。創業以来、こうした非常に細かい点にまで一つひとつこだわってきました。
該当講座

日本発「無印良品」から世界の「MUJI」へ ~MUJIのグローバル展開に学ぶ~
鈴木 啓(株式会社 良品計画 取締役・執行役員/生活雑貨部長)8年半にわたる海外事業の第一線でのご経験を交えながら、良品計画のグローバル展開についてご紹介いただきます。
日本発「無印良品」から世界の「MUJI」へ
~ケロッグ経営大学院 モーニングセッションより
インデックス
-
第1章 消費社会に対するアンチテーゼ
2015年10月07日 (水)
-
第2章 「わけあって、安い」に込めた想い
2015年10月07日 (水)
-
第3章 「木・金・土」でつくられた第1号店
2015年10月07日 (水)
-
第4章 海外第1号店はロンドンに
2015年10月14日 (水)
-
第5章 日本から世界の「MUJI」へ
2015年10月14日 (水)
-
第6章 欧州で感じた日本との違い
2015年10月14日 (水)
-
第7章 グローバル人材を育てる仕組み
2015年10月21日 (水)
-
第8章 なぜ、グローバルを目指すのか?
2015年10月21日 (水)
-
第9章 「商いを通じた社会貢献」を世界規模で
2015年10月21日 (水)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













