研究者たちの往復書簡 ~未来像の更新~
建築学 × 文化人類学
vol.3 建築の公共性と、民主的であることの違いは?

本シリーズ「研究者たちの往復書簡」では、アカデミーヒルズ発刊書籍『人は明日どう生きるのかー未来像の更新』をきっかけに、その著者たちが、分野を越えて意見や質問を取り交わします。第3回目となる今回は、東京大学建築学専攻 准教授の小渕祐介さんが京都大学人文科学研究所准教授の石井美保さんに返信する最終回<建築と文化人類学の交差点>をお届けします。

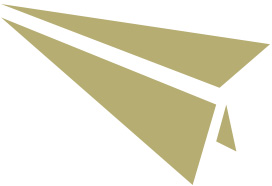
建築と文化人類学の交差点
小渕さんから石井さんへの書簡
ご返事のお手紙ありがとうございます。
SNS コミュニケーションが主流の時代ですが、「手紙」の可能性を実感しながら拝読いたしました。コロナ状況の渦の中で、LINEでササッと送るメッセージやZoomのインターネット上での対話で多くのことが間に合ってしまうような気になっていましたが、手紙独特の複雑な次元と情報量の奥行きに新鮮さを感じました。石井先生が塀の上を駆け回っている姿や、アフリカの現地の人々との共同生活など、これまでの出来事が一直線で時間軸上に流れると同時に、時間軸とは違ったポイントポイントの繋がりとその間の余白を僕なりに想像しておりました。
石井先生のお手紙を読んで、文化人類学者はアーティストであることに気がつきました。美術作品を作ると言う意味でのアーティストではなく、生き方そのものがアートであるように感じました。美術作品は、物理的·非物理的を含めてモノとして存在し、アーティストの身体と密接な関係を持ってはいても通常は切り離されていますので、普通の生活を送りながら作品制作に没頭することができると思います。しかし、石井先生の言葉の「フィールド的身体」と「身体的フィールド」は、アーティスト自身がアートであり、また、フィールド的身体を取り巻く生活空間と一体化することで、近代社会の中で排除されてきた文化と人の関係を物理的存在として視覚化できるのかと感じました。それは、村上慧さんの「家を背負って歩く」と似ているのではないでしょうか? 村上慧さんの場合は、アーティストと外部空間の境界がぼやけて、「殻」のように背負った家がアート作品ではなく、家を背負って歩き続ける生き方そのものがアートであるように。
お伺いした文化人類学の可能性に対して、「のっぺりとした近代という時空間に、穴や隙間を穿っていくこと」と聞き、共感しました。僕は建築が専門領域なので、建物、または建築設計を人々に提供する立場ではありますが、建物を作ることが最終目的ではなく、それはあくまでもひとつの表現媒体であると思っています。近代技術の発展に伴って生まれた機械的な均一空間に対して、人それぞれが持つ個性を活かした建築のあり方を探っていますが、それは、生産的に作り出される現代の生活空間に対する批評であると共に、この時代に生きる人々に与えられた可能性の追究でもあると思っています。
「建築の民主化」ということに対して、「いつのまにか押しつけられていた空間の一元的な意味や用途をカッコに入れて、自分たちの手でいっときの居場所をつくりだすという意味で、ややもするとアナーキーな様相を帯びてくるものなのかもしれません」と言っていただいたことにも100%共感します!私は海外生活が長いせいもあり、日本での日常生活において「どうしてこうなの?」と思うことがいつもあります。「建築の民主化」の発想も、10年前に日本で生活を始めた頃から考え始めました。日本で生まれ育ったので日本の常識はわかっていたつもりでしたが、現実とはかなり違うことに少しずつ気づかされました。たとえば、帰国直後にマンションを借りた時、不動産屋さんから内装の壁に傷や汚れをつけたら保証金から差し引いて修理します、と言われてちょっと驚いたのを覚えています。アメリカやロンドンで借りていたところは、退去時に自分で壁にペンキを塗れば良いことでしたの、壁の色を変えたり釘を打ったりして自分で使いやすいように生活環境を作ることが当たり前でした。なので、東京で家族と一緒に生活を始めるにあたり、当時まだ2歳だった息子が壁に落書きをしないか?汚さないか?みたいな心配が多く、我が家というよりホテルにいるような気分でした。そんなこともあって、今では「自分の住む場所は自分で作る」という考えを持つようになりました。
「建築の民主化」についてですが、そもそも民主化とは何か? 自分なりに考えてみました。誰でもわかっていることのようですが、もしかしたらそれほど明確な概念ではないかもしれない。僕は英語圏での生活が長かったこともあって、抽象概念はついつい英語で考えてしまいます。日本語で「民主化」と言うと少しピンとこないのですが、Democratic というと実感できます。この違いは上手く説明できないのですが、強いて言えば、味覚に近いです。概念としての味と、口に入れた時の味の違いのように。英語で democratic と言っても、時代によってその意味合いは変わっています。democracyの制度は紀元前6世紀のギリシャのアテネから始まったと言われていますが、女性、奴隷、外国人には市民権がありませんでしたので、現代のdemocracyとは少し異なります。日本では、民主化の概念は産業革命と同時に西洋から入ってきましたが、紀元前のギリシャと同じように第二次世界大戦後までは女性に選挙権はなく、国民全員(18歳以上)が生活の場を作る仕組みに介入できることになったのは、歴史的に見るとごく最近のことです。ここ数年、インクルーシブ(inclusiveness)という言葉を日常の生活の中でもよく使うようになりましたが、誰もが社会という共同体の中で自分なりの生き方を持って生活できることが、いま求められていると思います。まだまだ排他的な環境も多く存在しますが、全体として見れば、ゆっくりとではあっても、民主的な社会の方向に進んでいるのではないかと思います。
このように、民主化の歴史は、特定の少人数による権力から全員参加型へと、社会制度的には進化してきましたが、では建築の場合はどうなのか?と言うと、逆の流れになっているように思います。近代化において施工や生産技術が進化し、建物の質が向上し、利便性や安全性は激的に改善されたにもかかわらず、生き方を軸にした生活環境は必ずしも良い方向に向かっていない気がします。もともと庶民の建築空間は、身体と環境が一体化したものであり、生活そのものが生き方の姿でした。それは、社会的または経済的に地位が低ければ自分の生活を自分で賄わなけれならないサバイバルな環境でもあり、現代社会の目線からは苦を強いられた生活と考えられますが、そこには、近代の社会からは消えてしまった自由な人間の存在があったのではないかと思います。
具体的に思いついたのは、昨年閉館してしまった浅草のアミューズ ミュージアムで展示されていた「ぼろ」<BORO展>、何世代にも渡って補修されながら使われた農家の古着です。

アミューズミュージアムで展示されていた「農家の古着」
建築においても同じようなことが言えます。たとえば、戦前の多くの庶民の生活の場には、寄せ集めた古材を再利用して建てられた民家が多く存在していました。それは経済的な理由だけでなく、モノに対しての価値が経済的価値とは違った次元で理解されていたからだと思います。私の勝手な推測ですが、戦前の日本の産業はほぼ50%が農業であり、作物の価値は需要と供給の枠の中だけで決められるのではなく、手間隙をかけた身体と環境が一体となったモノの延長上にあったのではないでしょうか。古材とは、人が手間隙かけて丸太を角材に切り出し、それをまた別の寸法に合わせて作り変え、まるで作物のようなモノであったと僕なりに考えます。それは経済的な物差しで測れる付加価値ではなく、モノとの繋がりを表す身体的な価値だと思います。建築の民主化とは、自分の生活環境を消費するのではなく、生産できることであり、さらに、そこで生まれる個性的な生活空間を社会の中で活かしていくことを目指しています。
「音で建築をつくる」プロジェクトも建築の民主化の実験的試みです。音は誰もが同じように聞こえるのではなく、みんな違った風に聞こえています。歳をとると耳が悪くなっていくのは誰もが知っていることですが、音の方向、音色も、人それぞれに違って聞こえています。たとえば大勢の人がコンサートホールのような同じ音響空間にいても、実はそれぞれに違った「音」を聞いているのです。その自分が聞いている音を頼りに建築を作ると、その空間は最も身体的に繋がりがある、という仮説です。
さて、ご質問の「建築の公共性と、民主的であることの違いについて」ですが、この二つの概念は似たように解釈されがちですね。僕が思うには、公共性とは象徴性とも言い換えられるのではないでしょうか。誰もが使える実用的な建物というより、誰もがそれなりに共感できる。行政の建物や大勢の人たちに使われる公共の建物は、人々の生活のインフラ的空間、あるいは空間的なコミニュケーションのデバイスだと思います。一方「民主的」とは、先ほども述べたように、人と人を繋ぐというよりは、人が持つ可能性を最大限に発揮できる環境のあり方だと僕なりに解釈しています。人をカテゴリーにまとめてしまうのではなく、それぞれの個性を活かした生き方をサポートするのが民主的な社会を築く建築のあり方だと思います。
「建築学と文化人類学が共同で何ができるか?またどんな可能性があるのか?」というご質問ですが、建築学も文化人類学も似たような目標に向かっていることに気づき、一緒にいろいろな研究ができるのではないかと少し期待してしまいました。それは、近代社会が細分化した人々の生活のあり方や生き方を、ホリスティックに見直すことになるのではないかと思います。では具体的にどんなことがありえるかというと、たとえば、エンターテイメントの概念のルーツを辿ってみるとか? 現代のエンターテイメントは、息抜き、暇つぶし、現実逃避のように、日常生活から切り離された存在であり、社会の中で無限に生産·消費されるモノであると思います。しかし、そのルーツはどうなのか?憩いの場と人の生活はどのように関わっていたのか?非常に興味があります。
 たとえば、祭りは世界中どこにでもありますが、地域ごどにどのように成り立っているのか、または成り立っていたのか。日本の盆踊りが農作業の体の動きを抽象化したものであるなら、お盆という先祖の霊と一緒に過ごす季節に、生きている人々だけでだけでなく、祖先とも一緒に踊る。そうして豊作を祈る。または、体で覚えている農作業の動きを楽しむ。もしそうだとすると、農業の機械化が進んだ現代ではすっかり意味合いが変わってしまい、踊りが形式化してしまっていますが、ルーツを辿ってみると新しい価値観が見えてくるような気もします。
たとえば、祭りは世界中どこにでもありますが、地域ごどにどのように成り立っているのか、または成り立っていたのか。日本の盆踊りが農作業の体の動きを抽象化したものであるなら、お盆という先祖の霊と一緒に過ごす季節に、生きている人々だけでだけでなく、祖先とも一緒に踊る。そうして豊作を祈る。または、体で覚えている農作業の動きを楽しむ。もしそうだとすると、農業の機械化が進んだ現代ではすっかり意味合いが変わってしまい、踊りが形式化してしまっていますが、ルーツを辿ってみると新しい価値観が見えてくるような気もします。またまとまりのない独り言のような返信になってしまいましたが、つまみ食い的に読んでいただけると幸いです。
小渕祐介さんと石井美保さんの往復書簡いかがでしたでしょうか?

プロフィール

2010年より東京大学建築学科にて小渕研究室を主宰する。また、アドバンスト・デザイン・スタディーズ・プログラムの共同創設ディレクターでもある。これまで、2005年から2010年の間はロンドンの英国建築協会 (AA) にてデザイン・リサーチ・ラボの共同ディレクターを務め、2003年から2005年の間、同協会でコースマスターとユニットマスターを務めてきた。プリンストン大学、南カリフォルニア建築大学、トロント大学で建築学を専攻し、プリンストン大学、ハーバード大学デザイン大学院、香港大学、ケンタッキー大学、ニュージャージー工科大学で教鞭を執った。 小渕准教授の今までの研究プロジェクトは、ニューヨークのクーパー・ヒューイット・ミュージアム、パリのポンピドゥー・センター、北京建築ビエンナーレ、ロッテルダム建築ビエンナーレ、チューリッヒ・デザイン美術館、バルセロナ・デザイン美術館など、世界中で展示・出版されてきた。

文化人類学者。タンザニア、ガーナ、インドをフィールドとして宗教実践や環境運動についての調査を行っている。著書に『精霊たちのフロンティア』(世界思想社, 2007年)、『環世界の人類学』(京都大学学術出版会, 2017年)、『めぐりながれるものの人類学』(青土社, 2019年)など。
人は明日どう生きるのか - 未来像の更新
南條史生 アカデミーヒルズNTT出版
研究者たちの往復書簡 ~未来像の更新~
建築学 × 文化人類学 インデックス
-
vol.1 すべてが情報化・消費される今、文化人類学の可能性って何ですか?
2020年09月15日 (火)
-
vol.2 現代における文化人類学の可能性
2020年10月20日 (火)
-
vol.3 建築の公共性と、民主的であることの違いは?
2020年11月17日 (火)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....















