研究者たちの往復書簡 ~未来像の更新~
建築学 × 文化人類学
vol.2 現代における文化人類学の可能性

感染症の拡大や気候変動など、世界が同時に同じ脅威に直面する今、領域を横断してダイナミックに議論し、新しい知性を紡ぎ出す力が求められています。かつて、リーダーや研究者たちは頻繁に文を送り合い、情報交換を行い、交流を深めてきました。
本シリーズは、アカデミーヒルズ発刊書籍『人は明日どう生きるのかー未来像の更新』をきっかけに、その著者たちが、分野を越え往復書簡を取り交わします。
書簡を送り合うのは、東京大学建築学専攻 准教授の小渕祐介さんと京都大学人文科学研究所准教授の石井美保さん。vol.2となる今回は文化人類学者・石井さんが気鋭の建築家小渕さんのお手紙に返信します。

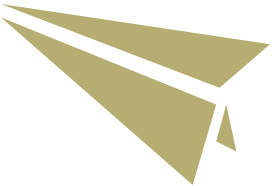
石井美保さんから
小渕祐介さんへの書簡
小渕祐介さま
こんにちは、文化人類学者の石井美保です。いただいたお手紙、とても楽しく拝読させていただきました。かねてから、建築学と文化人類学は深い関係にあると思っていましたので、この往復書簡の企画にはワクワクしています。
いただいたお手紙によれば、小渕さんはなんと16歳の頃から北米を放浪されていたのですね。そうした旅の中で、人と建築、都市空間に興味をもたれたとのこと。私が大学生のときに文化人類学を専攻したのも、行ったことのない場所に赴いて、経験したことのないような暮らしをしてみたいという憧れが大きな動機だったような気がします。大学院の修士課程では東アフリカのタンザニアで、路上で商いをしている若者たちと一緒に暮らし、博士課程では西アフリカのガーナで、精霊に仕える司祭の家に住みこんで調査をしていました。ここ十年ほどは南インドをフィールドに、神霊祭祀と環境運動についての調査をしています。いろんな場所で調査をしてきましたが、人々の生きる日常の中に、ふだんの「現実」に落としこめない異界的なものが含まれていて、それが人々の生を動かしている。その面白さと不思議さに惹かれて、調査をつづけているように思います。

神霊の祭り/水田の傍らの祠(インド)
さて、お手紙の中にあった、小渕さんが若かりし頃に野宿をしながら放浪されていたというエピソードと、目下実践されている「建築の民主化」というアイデアに、とても興味を惹かれました。そのふたつは、どこかでつながっているように思えます。
小渕さんのお手紙を拝読したとき、最初に私の頭に浮かんだのは、村上慧さんの「家を背負って歩く」(※1)という実験的な生活のことでした 。手作りの家を背負って(より正確には、家をかぶって)歩き、行き着いた町の片隅に家を置かせてもらって眠り、また家を背負って歩きつづけるという暮らし。この場合の家とは、固定された建造物ではなくて、モバイルな自分の「殻」のようなものといえるでしょうか。自分自身の意思だけでなく、偶然の出会いや、その日の天気や地形などに影響されながら、絶えず変わっていく流動的でミニマムな住みかのかたち。それはテント暮らしの身軽さや自由さ、心細さにも通じるものではと想像します。
そしてまた、「音で建築をつくる」という小渕さんのプロジェクトにも驚かされました。小渕さんのプロジェクトは、音で指示されるターゲットに向かって、学生たちが資材のココナツ繊維を「バズーカ」で打ち出すという斬新なものですが、そこまで複雑な仕組みではなくても、音そのものが独特な空間をつくりだすということは、たしかに日常の中にもみられますよね。
先にふれた、熱帯林に住む狩猟採集民はポリフォニックな歌声の素晴らしさで有名ですが、私が暮らしていたガーナ南部の森林地帯に住む人々も、多声的な合唱にくわえて、さまざまなドラムの演奏に長けていました。歌声やドラムの音と振動がつくりだし、そこにいる人たちをすっぽりと包みこむ音響空間は、みんなの身体を通して即興的に生みだされる、ゆらぎのある生きた「家」のようなものなのかもしれません。

ブッシュに落ちる夕日/太鼓奏者(ガーナ)
こんなふうに考えるとき、生きている身体と、それを包む環境とのあいだの可変的でありながら相即的な関係に考えが波及していきます。
いま、世界中の至るところでCOVID-19が猛威をふるっています。この問題について考えるために、このところウイルスについての本を読みかじっていたのですが、その中の一冊である『ウイルスは生きている』という本に、面白いことが書かれていました 。この本の著者である中屋敷均さん(※3)は、「ウイルスは生物ではない。なぜなら代謝をしないからだ」という主張に対して、つぎのように問い返します。
「それならヒトだって、生命に必要な代謝系のすべてを保有しているといえるだろうか?」
答えは否。中屋敷さんによれば、生命の維持に不可欠なアミノ酸を、他の生物を捕食することで補っているヒトもまた、ウイルスと同じように代謝系の一部を外部環境に依存しているのだそうです。とすれば著者の問いは、つぎのように言い換えることができるかもしれません。————外部環境から完全に区別される「自己」といったものはありえるのだろうか?
このように、外部環境が自己の代謝系をなしているという考え方は、身のまわりの環境が自己の身体と相即しているという「環世界」の考え方にも通じるように思います 。そんなふうに考えると、狩猟採集民にとっての住まいである森や、歌声によって即興的に生みだされる「家」のような音響空間もまた、自己の身体と切り離せない、ひとつの環世界としてみえてきます。(※4)
ところで、ちょうど小渕さんからのお手紙をいただいた頃、文化人類学の雑誌に建築学者が書いた論文を読む機会がありました 。そこには、こんなエピソードが描かれていました。彼女はあるとき、文化人類学者と一緒にネパール・パタンの入り組んだ路地を歩いていたそうです。そのときに同行の文化人類学者が口にした、「ここの人たちは路地的身体を生きているんだね」という言葉を、彼女は「身体的路地」と聞き間違え、その後もしばらく、そのように思い込んでいたというのです。彼女はこのエピソードを、空間を基点にものごとを考える建築学と、人を基点としてものごとをみる文化人類学の違いとして論じているのですが、いずれにしても、両者が着眼したのは路地という空間と、そこに暮らす人々の身体が相互的に形成され、絡みあっているような状況でした。(※5)
ある路地には、その場所に何世代も暮らしてきた人たちの記憶や歴史が堆積し、そこを通る人々の足取りが刻みこまれていきます。その一方で、毎日のようにその路地を歩き、道端に佇み、通りに面した石段に腰掛ける人びとの身体もまた、路地に慣れ親しみ、そこを自在に使うわざを身につけていく。そこには、人の身体の動きが空間にさまざまな相貌を与えると同時に、空間のあり方が身体の新しい動きを生みだすという相即的な関係があるように思えます。
この路地のエピソードを読んで、ふと、自分自身の幼い頃の記憶が蘇ってきました。たしか8歳の頃だったと思いますが、私は当時、自分の家と近隣の家々のまわりに張りめぐらされたブロック塀によじのぼり、その上を駆けめぐるという遊びに夢中になっていました。幅の狭い塀の上を猫のように伝って走りまわるうち、普段とは違った視点や足の運び、平衡感覚が培われていきます。塀という「道」によって新しい身体感覚が形成されていくと同時に、その上を駆けまわる私の行為を通して、塀のもつ「道」としての新たな可能性が発見された、といってもいいかもしれません(少しおおげさですが)。その名残か、今でも平均台は得意です。
こうした連想や発想を経て、あらためていま、小渕さんが提起された「建築の民主化」というアイデアの面白さと奥深さに気づかされます。そこで想定されている「民主的であること」とは、直感的に、「公共性」とは似て非なるものであるような気がします。建築の公共性とは、おそらくはあえて掲げるまでもない大前提であり、なおかつ建築の近代性や目的合理性とかかわっているのではないかと想像します。
 それでは、建築が民主的であるとは、どのようなことを意味するのでしょうか? これについて、私なりに少し考えてみますと、たとえば先述した「身体的路地」は、そこに暮らす人々の身体行為によって作られてきたものであり、同時にまた、住民たちの身体技法や身体感覚を培ってきたものだといえます。そのとき、路地という物理的空間とそれぞれの住民の身体とは、親密でユニークな関係性によって結ばれているのでしょう。しかもそれは、不変的な構造をもつ建築物に人々が適応するといったものではなく、個別の状況や時勢に応じて移り変わっていく、可変的な関係性でもあるでしょう。
それでは、建築が民主的であるとは、どのようなことを意味するのでしょうか? これについて、私なりに少し考えてみますと、たとえば先述した「身体的路地」は、そこに暮らす人々の身体行為によって作られてきたものであり、同時にまた、住民たちの身体技法や身体感覚を培ってきたものだといえます。そのとき、路地という物理的空間とそれぞれの住民の身体とは、親密でユニークな関係性によって結ばれているのでしょう。しかもそれは、不変的な構造をもつ建築物に人々が適応するといったものではなく、個別の状況や時勢に応じて移り変わっていく、可変的な関係性でもあるでしょう。ある場所や空間をいくつもの身体が動きまわり、互いにやりとりしながら居座ったり離れたりし、そうした行為を通して空間の相貌が変化していくとともに、場所の意味が組み替えられていく。そうしたことが可能であることが、建築が「民主的であること」なのかもしれないと、そんな風に感じます。ある場所−空間の形成と変容に、自分が身をもって参与している感覚、といってもいいかもしれません。
そうした「民主的」な場所−空間は都市においてもさまざまな場面で見いだされ、興味深いことに、それらは日常の風景の中に非日常的なスポットをつくりだしています。たとえば、都市の建物の隙間にゲリラ的に作られた菜園であったり、オキュパイ運動の中で即興的に作られたキッチンやライブラリであったり、あるいはいっとき、京都大学の立派な石垣の上に自生したかのように居座っていた、あばらやのような「石垣カフェ」であったり。
こんな風にみていくと、建築や場所や空間を「民主化する」ということは、いつのまにか押しつけられていた空間の一元的な意味や用途をカッコに入れて、自分たちの手でいっときの居場所をつくりだすという意味で、ややもするとアナーキーな様相を帯びてくるものなのかもしれません。のっぺりとした、もう手を加える余地はないかのようにみえる完成された都市の空間に穴をあけて、身体を潜り込ませる隙間をつくりだす、そんな偶然的で冒険的な試みのひとつとして。
ここから、小渕さんからいただいたご質問への回答につながっていくのですが、現代における文化人類学の可能性のひとつは、日常の中にそうした隙間を発見し、その多彩なありようを伝えていくことではないかと考えています。そしてまた、さまざまな場所での、いろんな身体やモノや環境のユニークな絡まりあいと、その思いがけない変化を描くことを通して、のっぺりとした近代という時空間に、穴や隙間を穿っていくことだと。私自身が、現代を生きる人々の日常と、精霊や神霊のように異界的なものとの絡みあいをテーマにしているのも、その一例といっていいかもしれません。
このとき、文化人類学の強みはその「具体性」にあります。実際にその土地を歩き、そこにいっとき根を下ろして、自分のあらゆる身体感覚を駆使しながら生活することを通して、別な世界のアクチュアリティがしだいに自分の中に浸透していくといいましょうか。慣れ親しんだものとは異なる環世界に身を浸すことで、さっきの言葉をもじれば、新しい「フィールド的身体」が生まれてくると同時に、思いがけない「身体的フィールド」の様相が立ち現れてくる。そのプロセスそのものが、人類学者に気づきを与えると同時に、別様でもありうる世界の可能性を描く、その著作に説得力を与えているのだと思います。
こんな連想と空想の数々を経て、小渕さんにぜひお伺いしてみたいことは……
建築の公共性と、民主的であることの違いについて、どのようにお考えでしょうか。また、建築学と文化人類学が共同で何かできるとしたら、どんな可能性があるとお考えでしょうか。そして、これからの建築のかたちについて、現時点でのアイデアや理想をお伺いできれば嬉しいです。
お返事を楽しみにお待ちしています。
※2)市川光雄 n.d.「森と人の共存世界:中央アフリカ、イトゥリの森のムブティの生活」『中部アフリカ小辞典』、中部アフリカ研究 in Kyoto.
※3)中屋敷均 2016『ウイルスは生きている』講談社現代新書。
※4)石井美保 2017『環世界の人類学——南インドにおける野生・近代・神霊祭祀』京都大学学術出版会。
※5)狩野朋子・郷田桃代 2020「レジリエントな空間と防災——ネパール・パタン、中国・麗江、トルコ・ベルガマの世界遺産エリアの事例から」『文化人類学』85(2): 254-271。
書籍『人は明日どう生きるのかー未来像の更新』

都市とライフスタイルの未来を議論する国際会議「Innovative City Forum 2019(ICF)」における議論を、南條史生氏と森美術館、そして27名の登壇者と共に発刊した『人は明日どう生きるのかー未来像の更新』 。
「都市と建築の新陳代謝」「ライフスタイルと身体の拡張」「資本主義と幸福の変容」という3つのテーマで多彩な議論を収録したアカデミーヒルズ発刊の論集です。
小渕祐介さん執筆 バラバラであることと、つながること (P.24~) 【要約】
 次回は、vol.3は 【建築学と文化人類学の交差点】をお届けいたします。石井さんの質問に、小渕さんはどのような書簡を返信するのでしょうか?
次回は、vol.3は 【建築学と文化人類学の交差点】をお届けいたします。石井さんの質問に、小渕さんはどのような書簡を返信するのでしょうか?どうぞお楽しみに!
メッセージは、執筆者にお伝えいたします。
<書籍プレゼント!>
コメントを下さった方の中から、抽選で3名様に
書籍『人は明日どう生きるのかー未来像の更新』をプレゼントします。
※プレゼント応募締切:2020年10月31日(土)まで
プロフィール

2010年より東京大学建築学科にて小渕研究室を主宰する。また、アドバンスト・デザイン・スタディーズ・プログラムの共同創設ディレクターでもある。これまで、2005年から2010年の間はロンドンの英国建築協会 (AA) にてデザイン・リサーチ・ラボの共同ディレクターを務め、2003年から2005年の間、同協会でコースマスターとユニットマスターを務めてきた。プリンストン大学、南カリフォルニア建築大学、トロント大学で建築学を専攻し、プリンストン大学、ハーバード大学デザイン大学院、香港大学、ケンタッキー大学、ニュージャージー工科大学で教鞭を執った。 小渕准教授の今までの研究プロジェクトは、ニューヨークのクーパー・ヒューイット・ミュージアム、パリのポンピドゥー・センター、北京建築ビエンナーレ、ロッテルダム建築ビエンナーレ、チューリッヒ・デザイン美術館、バルセロナ・デザイン美術館など、世界中で展示・出版されてきた。

文化人類学者。タンザニア、ガーナ、インドをフィールドとして宗教実践や環境運動についての調査を行っている。著書に『精霊たちのフロンティア』(世界思想社, 2007年)、『環世界の人類学』(京都大学学術出版会, 2017年)、『めぐりながれるものの人類学』(青土社, 2019年)など。
人は明日どう生きるのか - 未来像の更新
南條史生 アカデミーヒルズNTT出版
研究者たちの往復書簡 ~未来像の更新~
建築学 × 文化人類学 インデックス
-
vol.1 すべてが情報化・消費される今、文化人類学の可能性って何ですか?
2020年09月15日 (火)
-
vol.2 現代における文化人類学の可能性
2020年10月20日 (火)
-
vol.3 建築の公共性と、民主的であることの違いは?
2020年11月17日 (火)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













