記事・レポート
66ブッククラブ 第3回
『三体』を読む
更新日 : 2020年02月18日
(火)
第3章 最も不安な読書
アカデミーヒルズとコンテンツレーベル「黒鳥社」のコラボレーションによって始まった、新しいタイプの読書会「66ブッククラブ」。8月6日に開かれた第3回では、「中国SF」をテーマに、劉慈欣の『三体』を取り上げた。本作は、既存のSF作品の作法から大きく逸脱した「超怪作」。読後に誰もしが戸惑った、この中国SF史上最も成功を収めた本作に対する感覚は一体なんなのか? 日本版『三体』を翻訳した翻訳者・大森望氏、デザインシンカーの池田純一氏をゲストに招き、黒鳥社 コンテンツディレクター若林恵氏のファシリテートのもと、単なる「とんでもSF」では片付けられない、『三体』から滲み出る「中国SFの作法」の輪郭を明らかにする。
TEXT BY KEI WAKABAYASHI
PHOTOGRAPH BY YURI MANABE

若林 恵 (黒鳥社 コンテンツディレクター)
『三体』について初めて知ったのは、ベルリン在住のメディア美学者の武邑光裕先生を通してだった。3年くらい前のことだったと思う。先生は、「三体問題」という未解決の数理問題を、「西洋」と「東洋」と「デジタル界」の三つの世界をめぐるアナロジーとして語り、この3つの世界のバランスこそが現代社会における最難問となっていることを語ってくださった。「そりゃあ面白そうだ」と早速英語版を買い求めたが、案の定本棚のどこかに放置されることとなった。
日本版が晴れて出版されたことで、ようやく腰を据えて読むこととなったのだが、文化大革命のなかで起きた悲劇を格調高い文体で描き出した冒頭にまずは魅了された。「文革」というものについて、ここまで自由に書くことが許されていることに新鮮な驚きを感じながら、ぐいぐい読み進めた。ところが、読み進めていくと、そのように"文学的"なのはあくまでも冒頭だけで、その先、語り口や世界観は次々と乱脈に変化していく。ときにハードボイルドであったりスラップスティックであったり、突然観念的であったりする乱暴にも思える小説作法は、読む側を大いに困惑させる。一気に最後まで読んでしまえたので、たしかにそれは面白い作品には違いないのだが、「『三体』っていいの?」と聞かれると大いに困る。それを判断する基軸が自分のなかにまるでないからだ。
判断の基軸というのは、言い方を変えるとコンテクストがわからないということでもある。文芸作品というものは、明確に歴史的な産物で、個人の好き勝手に文脈もなく中空に浮いているものではないはずだ。小説というジャンルにも、その一ジャンルであるはずのSF小説にも起源はあり、時代のなかでのさまざまなアップデートがあり、メディア産業構造のあり方や、政治、経済がもたらす影響などを受けながら、地域地域によってさまざまな進展の仕方を遂げてきた。ある作品や作家の影響が大きく作用して、その道筋が突然大きく動くことなどもある。
文学の勉強が、まずは「文学の歴史」を学ぶことを意味しているのは、文字を使って何かを書く、その「書き方」や、それを読む「読み方」というものが、同じ人間であれば時代や地域に関わらず人類みな同じ、というものでもないからで、「読み書き」のやり方は、歴史のなかで変化しながらしていく。過去をある程度わかって置かないと、いま、なぜ、それがこうなっているのかがわからなくなってしまう。

そう考えたとき『三体』は、本当に取り付く島がないほどまでに「わからない」作品として目の前に姿を表す。『三体』を読むという行為は、自分にとっては延々と「わからないこと」をリスト化していくようなものだった。以下列記してみよう。
・中国において「作家」という職業がどういう位置付けにあるのかわからない。
・出版ビジネスがどうなってるのかわからない。
・どの程度、諸外国の本が読めるのかわからない。
・そもそも文学や文芸の社会的位置付けがわからない。
・中国でいまなお重要とされている文学がどんなものかわからない。
・文学教育、というものがあるのかどうかもわからない。
・SF作品が成り立つ前提として、「科学」「技術」というものがどう認識されているのかわからない。
・書き手も、読者も、リテラシーレベルがいまひとつわからない。
・歴史的な「古典」と近代以降の「文芸」の連続性/非連続性がわからない。
・etc.etc.
もちろん海外の文学作品に接するたびに、こうしたコンテクストをいちいち理解した上で読むわけではないし、大方の場合、そんなことは気にもかけないのだが、それを気にかけずにいられるのは、「細かい違いはあったとしても、だいたいの状況や条件は、自分たちと変わらないはずだ」という了解があるからで、近代以降の世界において「作家」や「文学作品」というものが社会的にどういう存在なのかは、そこまで変わることがないとタカを括っていられるからこそ、わたしたちは海外文学を平気で受容することができる。
けれども、『三体』が改めて浮き彫りにするのは、その了解が、現代・中国において通用するのかどうかが、さっぱり確信がもてないということだった。共産党の長きにわたる徹底した情報統制によって、社会とそこに暮らす人びとの姿が見えなくなってしまったおかげで、どこまでが「世界のどこでも似たようなものだよね」と言えて、どこからが「やっぱ共産党中国は特殊だね」と言えるのか、どうにも自信がもてない。結果、いざ『三体』を読むとしても、作品のなかに現れている特徴を、作家の個性に帰するべきなのか、あるいは中国の伝統に帰するべきなのか、あるいは現代中国SFに見られる傾向に帰することができるのかが判断できずに、絶えずモヤモヤしてしまう。もちろん、そのことで作品の面白さが減じるわけではないにせよ、焦点が合わないというか、自分が合わせた焦点に自信がもてないというのはとにかく不安だ。

こんなにも不安な読書体験というのも珍しいが、それは逆に言えば、わたしたちがいかに安定的な了解のなかで、文章というもの、本というものを受容しているかを表してもいる。そうした安定的な了解がないことには本や小説が商売になるべくもないのだから、それを否定したところではじまらないが、そうやって、自分たちが気づかずにどっぷりと浸ってしまっている「当たり前」を、こんなふうに疑わせてくれるものは、そのことだけをしてでも存在価値が大きい。
自分としては、中国という国、社会、文化の、あまりのわからなさ、知らなさに圧倒されたこと自体が『三体』を通して得た最も大きな学びだった。さて、どこから手をつけたものだろう、とあたりをつけてみたのが、日本との関係において中国の歴史を振り返る、與那覇潤の『中国化する日本 日中「文明の衝突」一千年史』、中国のものの見方や理解の仕方を現代的な意義もふまえながらわかりやすく紹介する金谷治の『中国思想を考える—未来を開く伝統 』、そして世界に先駆けて「官僚制」を導入したのが中国であるという事実の面白さから、「官僚制」のというものに引っかかりを覚えて手にしたデイヴィッド・グレーバーの『官僚制のユートピア』の3冊だ。
言うまでもなく、これらは『三体』を読む上で参照すべき本では決してなく、自分なりに「中国」という巨大で謎めいた概念を、手触りのある実体へと変えて行くための第一歩でしかないのだが、それにしても、この先学ばなくてはならないことがどれほどあるのかと思うと、その途方もなさに萎えてしまわなくもない。
長大な歴史、広大な国土、多様な民族と文化をもつ文明が、隣にずっとありながら、それが自分たちの知る「世界」のなかでこれほどまでに巨大な空白となっていたことに改めて驚いてしまう。アメリカについて自分たちが知っていたり、イメージしたりできることの量と比べてみたら、その情報量の少なさは明らかだ。わたしたちが世界を捉え、理解するスコープとレンズが決してニュートラルなものではなく、強烈な偏向をもっていることを改めて思わずにはいられない。その歪みを是正する必要があると感じるかどうかは人それぞれだろうけれど、いったんそれを歪みとして感じはじめてしまうと、その視界のバランスの悪さは、どうしたって気になってきてしまうのだ。

『中国化する日本 日中「文明の衝突」
一 千年史』 與那覇 潤 (著)
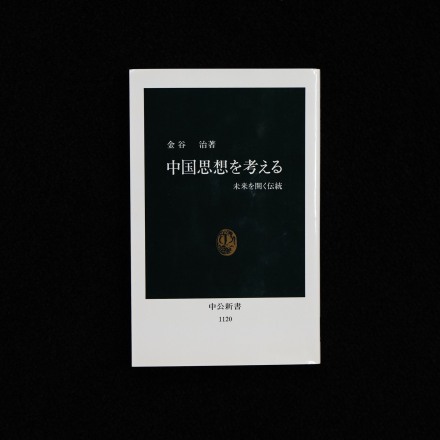
『中国思想を考える—未来を開く伝統 』 金谷 治 (著)

『官僚制のユートピア』 デヴィッド・グレーバー (著), 酒井 隆史 (翻訳)
<66ブッククラブ 第6回はこちら>
66ブッククラブ 第3回 インデックス
-
第1章 「蛮勇の産物」をときほぐす
2019年09月17日 (火)
-
第2章 中国文学お家芸の源泉
2019年09月19日 (木)
-
第3章 最も不安な読書
2020年02月18日 (火)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....














