記事・レポート
66ブッククラブ第2回
『暗号通貨VS.国家』を読む
更新日 : 2019年08月01日
(木)
第3章 制度設計は「ものづくり」
アカデミーヒルズとコンテンツレーベル「黒鳥社」のコラボレーションによって始まった、新しいタイプの読書会「66ブッククラブ」。6月6日に開かれた第2回では、気鋭の経済学者・坂井豊貴氏による『暗号通貨VS.国家』を取り上げた。社会選択理論やマーケットデザインの研究で知られる坂井氏が、なぜいま「暗号通貨」なのか? その秘密は、どうやら暗号通貨が実現している新たな「制度」にあるらしい。坂井氏本人とデザインシンカーの池田純一氏をゲストに招き、黒鳥社 コンテンツディレクター若林恵氏のファシリテートのもと議論を繰り広げた読書会は、この本が単なる「暗号通貨」の本でも「経済」の本でもないことを明らかにした。
TEXT BY KEI WAKABAYASHI
PHOTOGRAPH BY MASAMI IHARA

若林 恵(黒鳥社 コンテンツディレクター)
『暗号通貨 vs. 国家』の著者である坂井豊貴先生は、マーケットデザインもしくは社会選択理論という学問の専門家だ。その先生が「ビットコイン」に関する本を出されたときに感じた違和感は、おそらくはそのタイトルに起因する。
「暗号通貨vs.国家」というものものしいタイトルは、それこそビットコイン界隈で語られがちな、いかにもリバタリアンな政治信条をそのままなぞっているように感じられる。「政府なんかいらない」といったいささか乱暴なありがちな極論と、先生が専門としている「マーケットデザイン」や「社会選択理論」という学問の拠って立つところは、なんだか乖離があるようにも思えたのだ。
数年前に坂井先生にインタビューをしたことがある。そこで先生は、「マーケットデザイン」と「社会選択理論」をこんなふうに説明してくださった。
<わたしたちが暮らす社会では、主に2種類の「大きな計算箱」を使っています。そのひとつが「投票」で、もうひとつが「市場」です。どういうことかというと、「投票」は、投票用紙を入れたら、選挙結果が出てくる計算箱。「市場」は、需要や供給をインプットしたら、資源配分がアウトプットとして出てくる計算箱、ですね。両方ともたくさんの個人の情報を入力して、ひとつの「社会的決定」を出力する「計算箱」です。そう捉えると市場も投票も、同一の数理モデルで扱うことができます。
ぼくはミクロ経済学から派生した学際領域である「メカニズムデザイン」を専門にしています。メカニズムとは「計算箱」のことだと思ってください。その設計をするのがメカニズムデザイン。投票や市場はメカニズムの一種です。もちろんよいメカニズムを設計したいのですが、「よさ」の基準はさまざまです。例えば投票だと人々の意思を上手く反映させること、市場だと効率や収益を高めることが、よさの基準になります。
粗い言い方ですが、メカニズムデザインの知見や方法論で投票制度の設計を考察すると「社会的選択理論」になるし、市場制度の設計を考察すると「マーケットデザイン」になります。ぼく自身は、近年は社会的選択理論に軸足を置いて、研究や活動をしています>
wired.jp/2016/10/15/toyotaka-sakai/
経済学というものが総じてあまり好きではないのに、なぜかマーケットデザインには惹かれるものがあった。社会選択理論の祖とされるケネス・アローの著作も、内容はいまひとつよくわからないのだけれども面白いと感じた。その面白みは、煎じ詰めると「わたしたちが当たり前と思ってそのなかで生きている社会システムは、もうちょっと精緻に設計しデザインすることができる」ということを、これらの学問が明かしてくれていたからだと思う。
坂井先生の名を広く世間に知らしめた『多数決を疑う』という本もそうだ。多数決にも色んなやり方があって、過半数取ったものが勝つというやり方以外に、もう少しキメ細やかに民意なら民意を反映させる方法があることを、この本は懇切丁寧に解き明かしてくれる。
それは選挙制度そのものの是非を問うてイデオロギー論争に陥る手前で、「現状の制度でも、もうちょっといいやり方があるから」と教えてくれる。粗雑なイデオロギーや胡乱な未来論にとかく右往左往しがちな世の中にあって、実践的でプラグマティックな処方箋は、いっそ清々しい。
マーケットデザインの名著と言われるジョン・マクミランの『市場を創る』は好きな一冊だ。この本が面白いのは、市場というものを、そのときの社会の課題や問題を乗り越えるための創意工夫やデザインが積み重なったアイデアの宝庫と見ているからだ。多様な事例を通して語られる市場というものは、生き生きとした活力がある。
マーケットデザインという学問の態度と立ち位置を、下記のマクミランの文章はよく表しているはずだ。

「市場が正しいとか、根本的に悪であるとするような半宗教的な観点に対して、私は市場に対してプラグマティックなアプローチをとることを主張してきた。市場システムはそれ自体が目的なのではなく、生活水準を引き上げるための不完全な手段の1つである。市場は魔法ではないし、非道徳的なものでもない。市場は目覚ましい成果を生み出してきた一方で、うまく機能しないこともありうる。特定の市場がうまく機能するかどうかは、その設計にかかっているのである」
おそらく坂井先生がビットコインに興味を抱いたのは、そうした態度を通してではなかっただろうか。通貨と国家との関係を劇的に揺さぶる何かであるということよりも、まずは、その「設計」の妙、創意工夫の痕跡に魅せられて執筆された本であるように自分には読めた。そして実際、タイトルに含意された反国家的な装いは読み始めた早々に覆される。
「昔は通貨の管理って大変だったから、国家にカネを払ってやらせていた。でも、もうそんなことはしなくていい。ブロックチェーンの技術が開発されて、個人たちが分散的に通貨を管理できるようになったからだ。反国家でも反権力でもなく、ただ、適材適所でいこうよということだ」
『暗号通貨 vs. 国家』は、反国家・反権力を標榜することよりも、その設計の面白さ、デザインの妙を語ることに費やされている。坂井先生の論点が最も集約されている一文があるとしたら下記の一文ではなかろうか。
「『ものづくり』という言葉があるが、物理的なもののみならず、制度も人間が作る『もの』であって、そこには入念な工夫がいる。ビットコインはブロックチェーンによる技術的な仕組みが上手く作られている。しかし仕様変更のための制度も『もの』であって、これについては上出来とは言いがたい。技術だけでなく、制度をも含めて暗号通貨の『ものづくり』だ」
この一文にハッさせられるのは、「制度」という「もの」について、それをあたかも外から与えられて渋々と従わざるを得ない何かでしかありえないということを、わたしたちが知らぬ間に信じてしまっていることを突いているからだ。
制度は「国家」や「政府」の管轄、自分たちは不十分に思えて仕方がない選挙制度によって、そこにちょっと関わるくらいしかできない。そう思い込んでしまっているアタマをこの一文はぐらりと揺さぶる。
制度というものは、自分たちの手でよりましに機能するものとしてリデザインし、作りかえることができる。その発想をもとに『暗号通貨 vs. 国家』を読み進めていくと、本書は、「制度」というものを、地道な創意工夫の積み重ねである「ものづくり」の対象として、いま一度自分たちの手に取り戻すことの意義を謳った本と読めてくる。ビットコインは、その目覚ましいサンプルのひとつとして、ここでは題材になっているだけなのかもしれない。
デザインシンカーの池田純一さんは、『暗号通貨 vs. 国家』に連なるテーマを内包した一冊として、デイビッド・グレイバーの『アナーキスト人類学のための断章』を紹介した。
そこで池田さんは、グレーバーの語る「アナーキズム」は単なるカオスとしての「無政府」ではないと指摘する。政府管轄の「制度」がまったく機能しない状態のなかでも、共同体のなかに保持されていた、暗黙的な「制度」が作動して社会そのものが自発的に回っている状態を、グレーバーは「アナーキー」と呼んでいると言うのだ。グレーバーはそうしたアナーキーな状況をマダガスカルでのフィールドリサーチをもとに報告しているそうだ。
驚くべき指摘ではないだろうか。アナーキーといえばとにかく「自由」、爆発をともなう激越な「自由」をイメージしがちだ。制度なんてクソだ。中指立てろ、と。けれども、おそらくそうした古き良き「アナーキー観」は更新されてしまっている。国家が管轄する制度が破綻したとしても、自生的でホームメイドな制度が社会を機能させる。自治や相互扶助が自発的に作動している状態としてのアナーキー。
この指摘が面白いのは、そうしたアナーキズムは、あろうことか、自生的秩序を謳った経済学者のハイエクの思想を経由しながら、いまミレニアル世代やZ世代を席巻していると言われる「リバタリアニズム」の志向性と通じあってしまっているように見えるところだ。

坂井先生がブッククラブのなかで「次に読む本」として紹介した、社会人類学者・渡辺靖さんの著書『リバタリアニズム』は、現在のリバタリアニズムの「通奏低音」となっているいくつかの特徴をこう綴っている。
「自己所有権が重視されている」
「暴力を抑制する存在として政府の役割を一定程度認める」
「中央政府よりも市民に近い地方政府を、そして政府よりも市場メカニズムを信頼する」
「かといって資本主義の現状を全面肯定しているわけでも過去に黄金時代が存在したと考えているわけでも、ましてや市場そのものを万能と見なしているわけでもない」
「最も暴力性が低いのは、共同体のなかで培われてきた暗黙知や自生的秩序(ルールとロールとツール)を尊重することである」
「強制によらない、自発的な協力や取引に基づく社会」
「それこそが自己と他者の自由や幸福が不可分に結びついたユートピアを可能にすると考える」
列記してみると、「リバタリアニズム」が、「右」とも「左」とも振り分けることが難しい立場であることがわかる。そして本書のあとがきで著者は、右だ左だ、保守だリベラルだという古き良き二項対立にきっぱりと引導を渡す。
「拙著はリバタリアニズムの喧伝を企図したものではない。(中略)各人が切磋琢磨し、できることを持ち寄り、ともに豊かになる場としての自由市場。公権力に依存しない市民社会の自律と自助を保証する存在としての最小国家。他者の自由を侵さない限り、個人の自由を最大限容認しようとする社会的寛容。こうした理念について各人が反芻し、少しでも多くの選択肢が認められる社会に近づくことができればと思う。こうした態度がリバタリアンなのか、保守なのか、リベラルなのかは、私にとってどうでもよい話である」
一方で、こうした態度が、ビットコインやマーケットデザインに内包された志向になぜ親和的であるのかも改めて見えてくる。自発的な協力や取引を可能にするルールやツール。暗黙知や自生的秩序の尊重とそれを活かしたデザインへの期待。
坂井先生は、ブッククラブのなかでこう語った。
「左右の分類をするよりもまず、ガバナンスの仕組みを考えたほうがいい。人間の集団はある種の“人工物”なので、それをあたかも人間のように動かすためにはガバナンスの仕組みが必要なんです。そのときにリバタリアン的に国家を小さくすることもリベラルに大きな政府をつくることもできる。その点、暗号通貨はどんなガバナンスにすればうまくいくかみんなが試行錯誤しているのが面白いんですよね」
先に紹介したジョン・マクミランの本の原題は、「Reinventing The Bazaar:A Natural History of Markets」(バザールを再発明する:市場の博物学)というものだ。そのタイトルには、どこか人をワクワクさせる響きがある。
「制度をつくる」という、いかにも堅苦しく思える行為を魅力的かつクリエイティブな行為として自分たちの手のうちにいかに取り戻すことができるのか。そして、なぜそれがいま求められていることなのか。政治と経済をめぐるふたつの「大きな計算箱」がともに機能不全に陥っているなか、ブッククラブのなかで取り上げられた本が授けてくれるヒントは多い。
制度設計という「ものづくり」を、ただ国家まかせにしているだけでは社会はよくはならないし、むしろ悪くなるだけだ。自治や相互扶助の制度を自分たちの手で。そんなメッセージとしての「vs.国家」であるなら、自分も大賛成だ。

『エンデの遺言━根源からお金を問うこと 』
河邑 厚徳 (著), グループ現代 (著)

『市場を創る—バザールからネット取引まで』
ジョン マクミラン (著), John McMillan (原著), 瀧澤 弘和 (翻訳), 木村 友二 (翻訳)
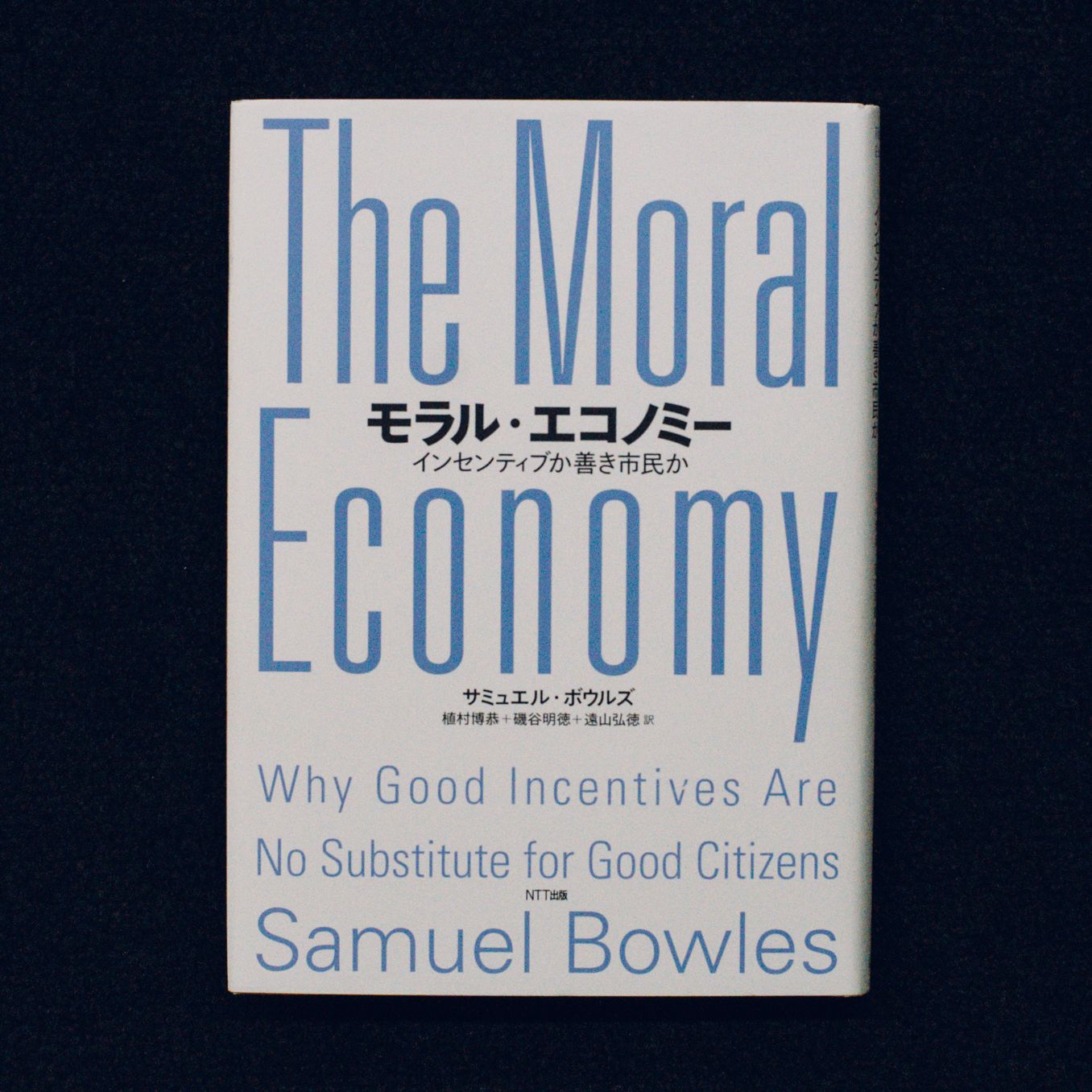
『モラル・エコノミー : インセンティブか善き市民か』
サミュエル・ボウルズ (著), 植村博恭 (翻訳), 磯谷明徳 (翻訳), 遠山弘徳 (翻訳)
<66ブッククラブ 第3回はこちら>
66ブッククラブ第2回 インデックス
-
第1章 自由を実現する「フォーク」
2019年07月16日 (火)
-
第2章 身体モデルから遠くはなれて
2019年07月16日 (火)
-
第3章 制度設計は「ものづくり」
2019年08月01日 (木)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













