記事・レポート
時の彼方の空遠く~縄文人、私たちの祖先
私たちのアイデンティティに迫る本
更新日 : 2019年05月14日
(火)
第4回 縄文人はどのような人たちだったのか?
縄文時代のライフスタイル
澁川雅俊:縄文人はどんな姿で、どんな家に住んでいたのか。何を食べていたのか。どんなことばで意思疎通をしていたのか。全体の人口はどれくらいで、どれほど長生きしたのか。縄文時代に興味を持つと、こうした疑問が次々とわいてきます。先に挙げた本を読み深めると、縄文時代の食糧事情や住居、家族、人口と平均年齢、衣服、顔形などについて、より具体的に知ることができます。例えば食糧は、獣肉(イノシシ、ノウサギ、タヌキ、アナグマなど)、木の実(ドングリ、トチノミ、クリ、クルミなど)、果物・野草、魚介類(タイ、マグロ、スズキ、イワシなど海魚/コイ、フナ、ウナギなどの川魚/シジミ、カキ、ハマグリ、アサリなどの貝類)が主であり、弥生時代に近い終末期には穀類(キビ、アワ、陸稲など)の栽培も始まっていたようです。
狩りには犬を伴っており、その犬は柴犬であったことが『柴犬~よみがえる縄文犬』〔福田豊、なかのひろみ、照井光夫/河出書房新社〕で語られています。縄文時代の子どもたちは幼い頃から遊びを通じて犬との絆を深め、将来の狩りに備えていたのかもしれません。
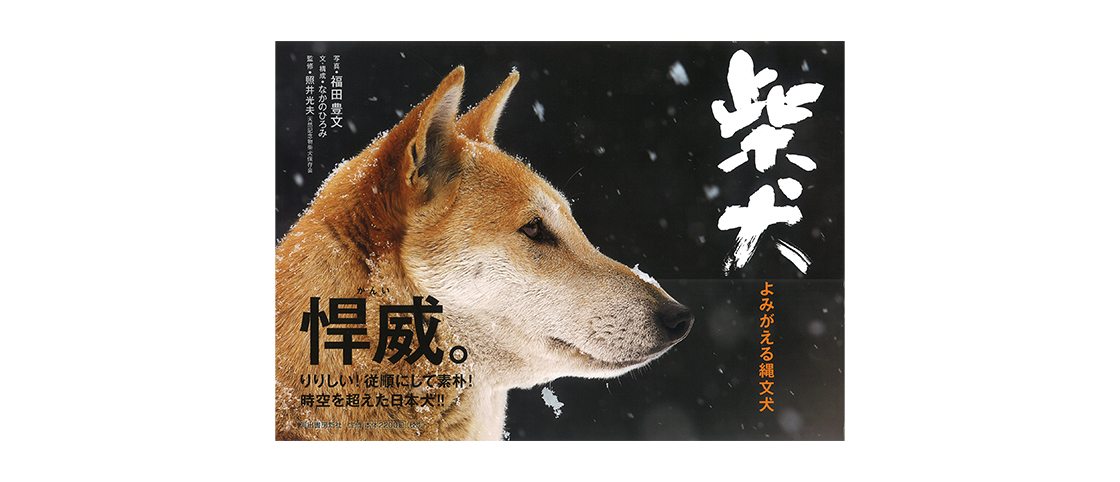
住居については、先に挙げたどの本にも家屋や集落の遺跡、復元された茅葺きの竪穴式住居が掲載されていますが、『火と縄文人』〔高田和徳/同成社〕では、調理や暖房、照明などに使われた火と炉の配置、祭祀での活用などについて詳しく解説されています。
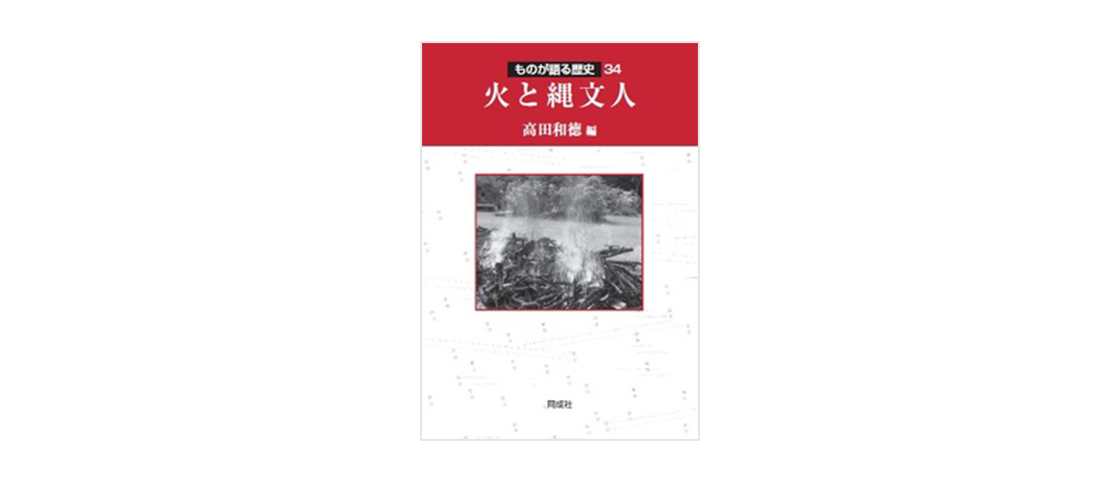
竪穴式住居に同居していたのは5~6人程度、夫婦と子どもたち、祖父母といったイメージでしょうか。家族の中心は夫の母、もしくは妻で、総じて母系中心の形態であり、その縁戚が環状集落を形成していたと考えられています。また、平均寿命は40歳程度で、13歳頃から大人として活動していたこと、体つきはがっちりしていたものの、男女とも155cm前後と短躯で、顔つきはいかつく、彫りが深くて鼻が高いことが特徴だったようです。
普段着は、植物の繊維を骨製の針で編んだ簡素な服で、冬は獲物からはいだ毛皮を着ていたこと、髪は土偶に見られる髷(まげ)を結っていたと考えられています。死後の埋葬については、副葬品などを一緒に収めた遺跡が発掘されており、当時から死生観のようなものがあったと推測できます。
縄文人のことばとこころ
澁川雅俊:縄文人の意思疎通については、まだよくわかっていません。ある学説では、日本語はウラル・アルタイ(ロシア・ウラル山脈からアルタイ山脈に囲まれた広大な地域)語系の言語であり、そのことばを話す人々が日本列島にやってきた弥生時代に日本語の原型が形成された、としています。他方で、『縄文文化が日本人の未来を拓く』〔小林達雄/徳間書店〕では、縄文人は〈原大和ことば〉と呼ばれるべき話し言葉で意思疎通を図っていたと推測しています。例えば、日本語には「春の小川はサラサラ流れ」「ツクツクボウシ」など、多種多様なオノマトペがあります。そこから考察すると、自然と共鳴・共感しながら生きていた縄文人がこれらを使っていたという主張も、蓋然性が高いと思われます。
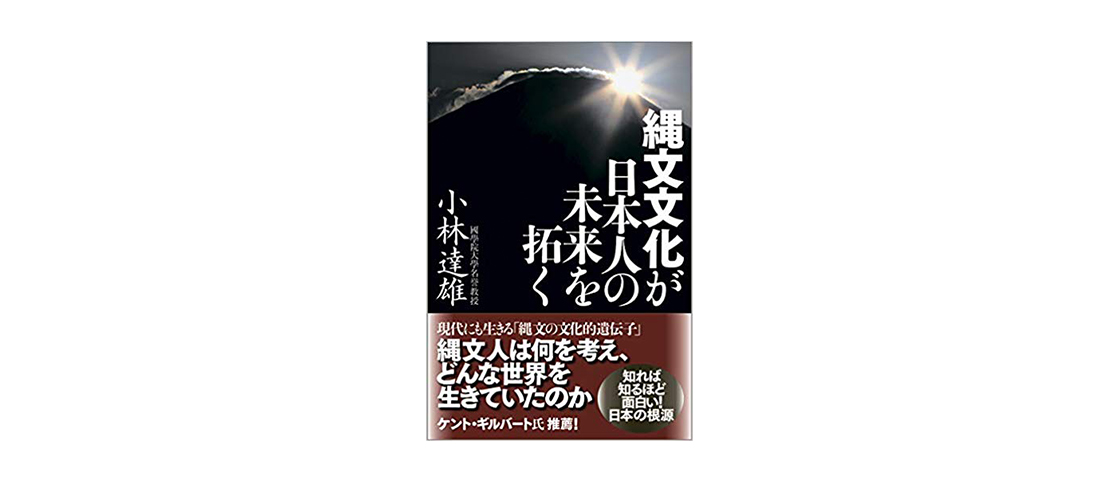
また、この本の著者は、人々の間で伝達される文化的遺伝子としてリチャード・ドーキンスが唱えた「ミーム(meme)」に着目し、縄文人の暮らしの様々な事績を考察しています。その上で、1万年以上にわたって繰り広げられた「人と自然との密なる共存共生」が育んだ精神性、いわば「縄文人のミーム」は現代の私たちのこころにつながっており、それがこれからの未来を拓く重要な鍵になると主張しています。
アイヌの研究者による『縄文の思想』〔瀬川拓郎/講談社〕も、その考えに同調しています。本書では、アイヌや南方の海民を含め、日本に残る神話や伝説から縄文人の思想、すなわち、彼らの生活や行動の規範となったものの見方・考え方を明らかにし、それが後の日本人にどう引き継がれたかについて考察しています。著者が示した縄文人の思想はまさに和魂洋才であり、それが1万数千年の時を経て、私たちのアイデンティティにも深くかかわっているとしています。
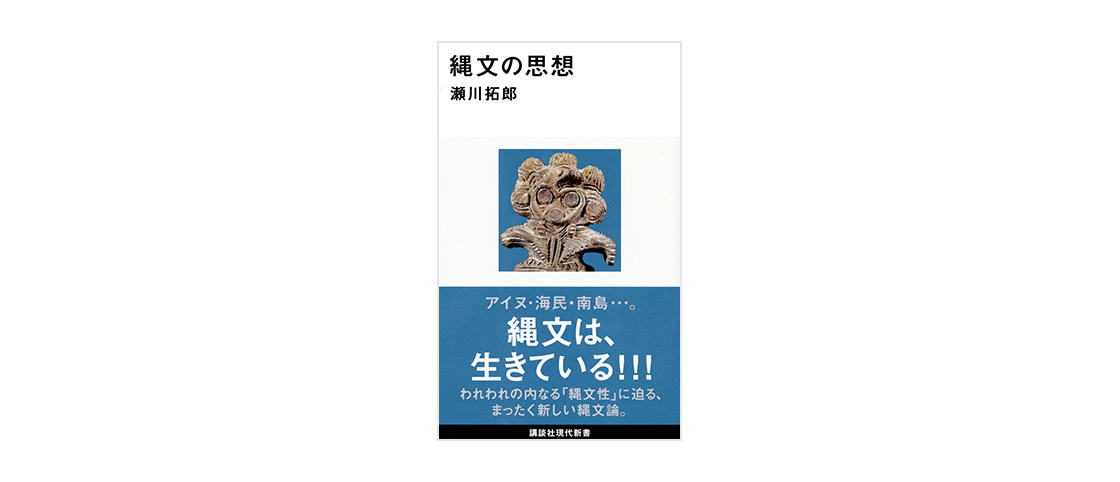
縄文時代末期(3,000年前頃)から、稲作農耕を行う人々が朝鮮半島を経由して日本列島の西南部に渡来し、狩猟採集を基盤とする縄文人を経済・社会・文化的に駆逐したことで弥生時代に移行した。従来、教科書などではこのように説明されていました。
しかし、『文明に抗した弥生の人びと』〔寺前直人/吉川弘文館〕によると、弥生人は1万年以上にわたり繁栄してきた縄文人の社会を簡単に駆逐できたわけではなく、双方の良さを残しつつ、むしろ時間を掛けて透過的に同化していったと述べています。
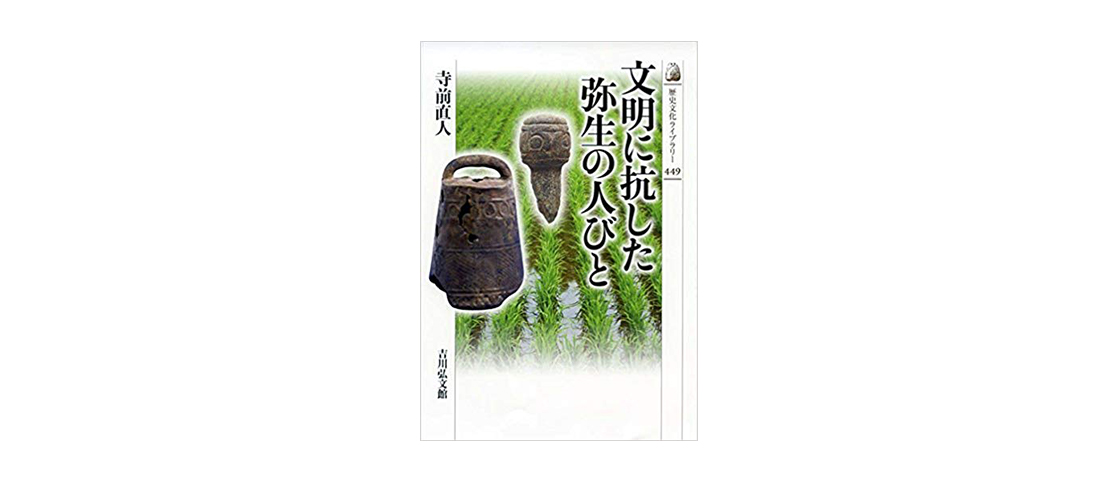
時の彼方の空遠く~縄文人、私たちの祖先 インデックス
-
第1回 「縄文」にロマンを感じる人が急増中
2019年05月14日 (火)
-
第2回 日本人はどこから来たのか?
2019年05月14日 (火)
-
第3回 縄文時代はいつ始まり、どのように発展したのか?
2019年05月14日 (火)
-
第4回 縄文人はどのような人たちだったのか?
2019年05月14日 (火)
-
第5回 現代人を魅了する「土器・土偶」
2019年05月14日 (火)
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....













