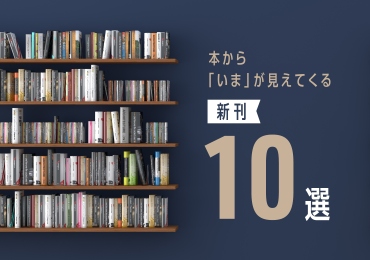セミナー・イベント
混沌(カオス)を生きる <デジタルの日イベント>
デジタルは『ちょうどいい道具』になれるのか
~個人データと自己の関係~
一般ライブラリーメンバー
日時
2021年10月10日
(日)
14:00~18:00

内容
デジタルは『ちょうどいい道具』になれるのか
Covid-19がもたらしたパンデミックは、給付金の支払いから感染者追跡アプリ、ワクチン接種管理など、日本のデジタル化の遅れを露呈しました。2020年に発表された電子政府ランキングでも前回2018年の10位から14位に後退しています。今年9月に発足したデジタル庁はこうした遅れを取り戻し、行政のみならず社会全体のデジタルトランスフォーメーションを進め、誰ひとり取り残さない人にやさしいデジタル化を進めることも期待されています。
一方、デジタルテクノロジーは、日々SNSやあらゆるネット上のサービス上で個人データが蓄積・分析・拡散され、個々のユーザーのネット履歴が即座に広告やECサイトへの誘導に活用されたり、人の注目ばかりを引きつける情報が横行する注意経済(アテンション・エコノミー)が増加したりするなど、デジタル空間における個人の尊厳や自律が危ういものになっています。そうした人々の警戒心が今後のデジタル化を阻む要因にもなっているのも事実です。またSNSやゲームアプリ依存、ネット上の言論空間で起きる炎上や分断、誹謗中傷の問題など、デジタルと付き合う上での課題は山積みともいえます。
それでは、デジタルテクノロジーとのより良い付き合い方とは何なのでしょうか? 前半のトークセッション、後半では個人データを用いたワークショップを通じて、人間とデジタルとの「ちょうどいい関係」を探ります。
デザインエンジニアとして人とテクノロジーの共生を提唱し、『コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ』を今年出版した緒方壽人氏(Takram)、対人認知のバイアスの社会への影響を社会心理学の立場から研究する唐沢かおり氏(東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻教授)、JUNETやWIDE Projectでの活動を通して日本におけるインターネットの発展・普及に貢献してきた砂原秀樹氏(慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授)、「べき則」の観点からデジタルと人間の違いを明らかにしてきた七丈直弘氏(一橋大学 経営管理研究科教授)をお迎えし、人間とデジタルの「ちょうどいい」関係について議論します。
唐沢かおり(東京大学 大学院人文社会系研究科 教授)
砂原秀樹(慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授)
七丈直弘(一橋大学 経営管理研究科 教授)
このワークショップでは、Google Takeoutサービスを活用し、デジタルサービスの利用により蓄積・収集された利用履歴といった個人データを、ユーザー本人がそのまま保有し・再利用する「データポータビリティ」を体験します。後半では、今秋公開予定のアプリ『Personary 2021』を活用し自分のデジタル上のペルソナを可視化します。
柴崎亮介(東京大学 空間情報科学研究センター教授)
(後半)「自分のデジタルペルソナを体験する」
橋田浩一(東京大学大学院情報理工学系研究科 ソーシャルICT研究センター教授)
塚田有那(編集者・キュレーター)
Covid-19がもたらしたパンデミックは、給付金の支払いから感染者追跡アプリ、ワクチン接種管理など、日本のデジタル化の遅れを露呈しました。2020年に発表された電子政府ランキングでも前回2018年の10位から14位に後退しています。今年9月に発足したデジタル庁はこうした遅れを取り戻し、行政のみならず社会全体のデジタルトランスフォーメーションを進め、誰ひとり取り残さない人にやさしいデジタル化を進めることも期待されています。
一方、デジタルテクノロジーは、日々SNSやあらゆるネット上のサービス上で個人データが蓄積・分析・拡散され、個々のユーザーのネット履歴が即座に広告やECサイトへの誘導に活用されたり、人の注目ばかりを引きつける情報が横行する注意経済(アテンション・エコノミー)が増加したりするなど、デジタル空間における個人の尊厳や自律が危ういものになっています。そうした人々の警戒心が今後のデジタル化を阻む要因にもなっているのも事実です。またSNSやゲームアプリ依存、ネット上の言論空間で起きる炎上や分断、誹謗中傷の問題など、デジタルと付き合う上での課題は山積みともいえます。
それでは、デジタルテクノロジーとのより良い付き合い方とは何なのでしょうか? 前半のトークセッション、後半では個人データを用いたワークショップを通じて、人間とデジタルとの「ちょうどいい関係」を探ります。
①【トークセッション】14時00分〜15時30分
タイトル
『デジタルは「ちょうどいい道具」になれるのか?〜現代のコンヴィヴィアリティをめぐって』概要
人間とデジタルやAIの違いを明確にすることで、どのあたりが人とテクノロジーの「ちょうどいい」関係なのかを探るべく、多様なゲストをお迎えして議論します。デザインエンジニアとして人とテクノロジーの共生を提唱し、『コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ』を今年出版した緒方壽人氏(Takram)、対人認知のバイアスの社会への影響を社会心理学の立場から研究する唐沢かおり氏(東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻教授)、JUNETやWIDE Projectでの活動を通して日本におけるインターネットの発展・普及に貢献してきた砂原秀樹氏(慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授)、「べき則」の観点からデジタルと人間の違いを明らかにしてきた七丈直弘氏(一橋大学 経営管理研究科教授)をお迎えし、人間とデジタルの「ちょうどいい」関係について議論します。
登壇者
緒方壽人(Takram デザインエンジニア)唐沢かおり(東京大学 大学院人文社会系研究科 教授)
砂原秀樹(慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授)
七丈直弘(一橋大学 経営管理研究科 教授)
ファシリテーター
塚田有那(編集者/キュレーター)②【ワークショップ】15時45分〜18時00分
タイトル
「デジタルペルソナから『ちょうどいい道具とは何か?』を考える」概要
日々ネットサービスに提供している個人データからは、データ上の「デジタル・ペルソナ」が浮かび上がってきます。データから描き出されるデジタルとしての”自分”は、一体どんな姿をしているのでしょうか?このワークショップでは、Google Takeoutサービスを活用し、デジタルサービスの利用により蓄積・収集された利用履歴といった個人データを、ユーザー本人がそのまま保有し・再利用する「データポータビリティ」を体験します。後半では、今秋公開予定のアプリ『Personary 2021』を活用し自分のデジタル上のペルソナを可視化します。
導入講演
國領二郎(慶應義塾大学総合政策学部 教授)登壇者
(前半)「デジタル情報を自分の手に取り戻す体験をする」柴崎亮介(東京大学 空間情報科学研究センター教授)
(後半)「自分のデジタルペルソナを体験する」
橋田浩一(東京大学大学院情報理工学系研究科 ソーシャルICT研究センター教授)
ファシリテーター
庄司昌彦(武蔵大学社会学部 教授/国際大学GLOCOM主幹研究員)塚田有那(編集者・キュレーター)
講師紹介





スピーカー
砂原秀樹 (すなはら・ひでき)
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授
情報処理学会監事
WebDINO理事
WIDE Project Board Member
デバイス WebAPI コンソーシアム 副代表
すべて読む
閉じる





募集要項
| 日時 |
2021年10月10日
(日)
14:00~18:00 |
|---|---|
| 受講対象者 | ライブラリーメンバー、一般 |
| 注意事項 |
■視聴URLのご案内 |
| 主催 | |
| 協力 |
|
※お申込期日:10月10日(日)14:00まで
注目の記事
-
01月26日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月25日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....