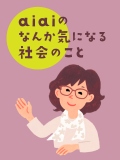記事・レポート
加藤良三氏の「アメリカと野球雑感」
~野球と国際政治を10倍楽しむ方法~
更新日 : 2009年11月20日
(金)
第6章 野球は日本人のDNAになじむスポーツだ

加藤良三: アメリカの話になってしまいましたが、元に戻って野球のいいところをいくつかご紹介したいと思います。まず1つ。これは王さんがおっしゃったことですが、野球というのはラインナップに入れば、大人でも子どもでも必ずチャンスが回ってくる、そういうスポーツです。この点がほかのスポーツと非常に違うところだと思います。
2つめは、野球の目的、ゲームとしての基本性格です。アメリカで60年代70年代に活躍した有名なコメディアン、ジョージ・カーリンは、アメリカで「野球かアメリカンフットボールか」という論争があったときに、「自分は野球派だ」として野球を擁護しました。
今でもビデオに残っている話なのですが、「アメリカンフットボールは戦争そのものだ、でも野球は違う」というのです。アメフトでは「敵陣」や「2 minutes warning」(※編注:前半・後半終了2分前に時計を止めること)という類の言葉がしょっちゅう使われます。野球はそれに対して、「7th inning stretch」。これはラッキーセブンの7回に、みんなで背伸びするというものです。何より、野球の目的は「お家に安全に帰ってくること」(coming home safe)、これがいいと。
野球のゲームにもごまかしやら、小ずるいプレーやら、いろいろありますが、究極的にはお家に安全に生還することを目標とするゲームであるというところなど、日本人のDNAになじむところがあるのではないかと思います。
さらに言えば、日本の野球は実感として「洋食」の味です。フランス料理、イタリア料理、それぞれ最高の料理ですが、多くの日本人にとってどこか肩肘張っているところがあるのではないかと思うのです。でも野球はロールキャベツやカキフライやカツカレー、あるいはハンバーグに上から卵を落として食べる、それをご飯と一緒に食べる、あるいはビフカツにスパゲティナポリタンやポテトサラダがついてくる。こうしたことがごく自然で、服装にもマナーにも気を使わず食べられる。そういう意味で、私は、野球には日本人に基本的に好まれる要素、「洋食的要素」が含まれているような気がいたします。
ただ、日本の野球の将来像を描くことは容易ではありません。私はメジャーリーグにどんどん日本の選手が出て行く状況を、ある意味では憂えています。「当然」とは申しませんが、「自然」なことだとも思っております。それを止めるためには、日本の野球をより魅力的なものにするしか本質的解決法はありません。
それでは、より魅力的なものにするにはどうするか。それは第一に、日本流の野球がアジア大洋州地区をはじめ、そのほかの地域にも浸透することです。日本がその中でリーダーシップをとる、盟主としての地位を保つこと、これが第一です。
第二に女性をより多く惹きつけること。北海道日本ハムファイターズが咋シーズン(2008年)、なかなかいい観客動員数を示しましたが、その6割が女性でした。大いにこの傾向は伸ばしたい。
私は女子野球も支援しています。日本の女子野球は去年の8月、松山の「坊ちゃんスタジアム」で開催された女子野球ワールドカップで優勝し、世界一になりました。野球を男のものということではなくて、お父さん、お母さん、息子さん、娘さん、みんなのものにしたいと思います。
しかしこのとき日本の野球がMLB(米国大リーグ)と違うのは、球団が球場を持っていないことです。例えば、球団の思うように球場を改装できないのです。女性ファンをより多く惹きつけるためには、アメリカの球場のように、きれいなレストルームを数多くつくることが大事なのですが、そういう改装が日本では許されないことが多いのです。非常に下世話な話ですが、そういうことがあります。女性が応援団になった場合には、今の応援の仕方と違った応援のマナーも生まれてくるだろうと思います。
最後に。プロ・アマの垣根は低くしたいと思っています。日本では、野球はエリートのスポーツとして始まり、それから社会に浸透していきましたから、アマチュアの方がプロより上だという感覚がいまだにあります。高校野球もしかりです。歴史的な要因を踏まえない議論というのはあり得ないと思いますが、さはさりながら、プロ野球の今の人気というのを考えると、日本の野球の裾野を広げるためにも、そして日本がアジア地域でリーダーシップをとり続けていくためにも、プロ・アマの垣根は話合いを通じて低くして、才能の開発に努めたいと思っております。(終)
2つめは、野球の目的、ゲームとしての基本性格です。アメリカで60年代70年代に活躍した有名なコメディアン、ジョージ・カーリンは、アメリカで「野球かアメリカンフットボールか」という論争があったときに、「自分は野球派だ」として野球を擁護しました。
今でもビデオに残っている話なのですが、「アメリカンフットボールは戦争そのものだ、でも野球は違う」というのです。アメフトでは「敵陣」や「2 minutes warning」(※編注:前半・後半終了2分前に時計を止めること)という類の言葉がしょっちゅう使われます。野球はそれに対して、「7th inning stretch」。これはラッキーセブンの7回に、みんなで背伸びするというものです。何より、野球の目的は「お家に安全に帰ってくること」(coming home safe)、これがいいと。
野球のゲームにもごまかしやら、小ずるいプレーやら、いろいろありますが、究極的にはお家に安全に生還することを目標とするゲームであるというところなど、日本人のDNAになじむところがあるのではないかと思います。
さらに言えば、日本の野球は実感として「洋食」の味です。フランス料理、イタリア料理、それぞれ最高の料理ですが、多くの日本人にとってどこか肩肘張っているところがあるのではないかと思うのです。でも野球はロールキャベツやカキフライやカツカレー、あるいはハンバーグに上から卵を落として食べる、それをご飯と一緒に食べる、あるいはビフカツにスパゲティナポリタンやポテトサラダがついてくる。こうしたことがごく自然で、服装にもマナーにも気を使わず食べられる。そういう意味で、私は、野球には日本人に基本的に好まれる要素、「洋食的要素」が含まれているような気がいたします。
ただ、日本の野球の将来像を描くことは容易ではありません。私はメジャーリーグにどんどん日本の選手が出て行く状況を、ある意味では憂えています。「当然」とは申しませんが、「自然」なことだとも思っております。それを止めるためには、日本の野球をより魅力的なものにするしか本質的解決法はありません。
それでは、より魅力的なものにするにはどうするか。それは第一に、日本流の野球がアジア大洋州地区をはじめ、そのほかの地域にも浸透することです。日本がその中でリーダーシップをとる、盟主としての地位を保つこと、これが第一です。
第二に女性をより多く惹きつけること。北海道日本ハムファイターズが咋シーズン(2008年)、なかなかいい観客動員数を示しましたが、その6割が女性でした。大いにこの傾向は伸ばしたい。
私は女子野球も支援しています。日本の女子野球は去年の8月、松山の「坊ちゃんスタジアム」で開催された女子野球ワールドカップで優勝し、世界一になりました。野球を男のものということではなくて、お父さん、お母さん、息子さん、娘さん、みんなのものにしたいと思います。
しかしこのとき日本の野球がMLB(米国大リーグ)と違うのは、球団が球場を持っていないことです。例えば、球団の思うように球場を改装できないのです。女性ファンをより多く惹きつけるためには、アメリカの球場のように、きれいなレストルームを数多くつくることが大事なのですが、そういう改装が日本では許されないことが多いのです。非常に下世話な話ですが、そういうことがあります。女性が応援団になった場合には、今の応援の仕方と違った応援のマナーも生まれてくるだろうと思います。
最後に。プロ・アマの垣根は低くしたいと思っています。日本では、野球はエリートのスポーツとして始まり、それから社会に浸透していきましたから、アマチュアの方がプロより上だという感覚がいまだにあります。高校野球もしかりです。歴史的な要因を踏まえない議論というのはあり得ないと思いますが、さはさりながら、プロ野球の今の人気というのを考えると、日本の野球の裾野を広げるためにも、そして日本がアジア地域でリーダーシップをとり続けていくためにも、プロ・アマの垣根は話合いを通じて低くして、才能の開発に努めたいと思っております。(終)
加藤良三氏の「アメリカと野球雑感」 インデックス
-
第1章 WBCの監督選びが難航した理由
2009年09月30日 (水)
-
第2章 日本野球は問題山積。しかし、大リーグより優れた点もある
2009年10月13日 (火)
-
第3章 プロ野球に「凡ミス」は存在しない
2009年10月20日 (火)
-
第4章 なぜアメリカは世界の課題を解決しようとするのか
2009年10月29日 (木)
-
第5章 農民から大企業へ。政府が組む相手を変えた理由
2009年11月10日 (火)
-
第6章 野球は日本人のDNAになじむスポーツだ
2009年11月20日 (金)
注目の記事
-
08月25日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年8月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
08月25日 (月) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
08月07日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....