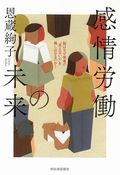記事・レポート
カフェブレイク・ブックトーク「源氏物語千年」
更新日 : 2008年07月16日
(水)
第6章 源氏に書かれている千年前の人々の暮らし
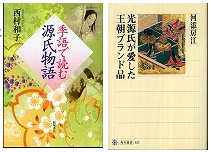
澁川雅俊: 有職故実(ユウソクコジツ)という慣用句があります。それは厳密には古来の、この場合にはそれ以前の先例に基づき、官職・儀式・装束などを研究することですが、源氏の読み方で次に大事なことは、それらを含め千年前の政治・経済・社会体制や自然・文化・生活などのことどもです。別な言い方をするならば、源氏で描かれている風景、建物・造園、室内装飾・調度品、衣装・小物、儀礼、学芸・文具、旅、食べ物、受贈品、病気・医療、信仰、政治体制・権力・財力等々の有り様です。
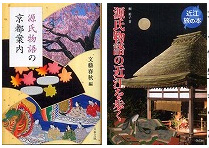
最近出版されている関連の本の中には、そういう側面から源氏を分析したり、考察したりしているものも少なくありません。例えば自然、風景、風習などを四季でみた
『季語で読む源氏物語』(西村和子著、07年飯塚書店刊)があり、室内装飾や道具類あるいは衣装と小物類について源氏本文にしばしば出てくる「唐物」という外来品に関して平安日本の海外交流を調べた
『源氏物語と東アジア世界』(河添房江著、07年日本放送出版協会刊)や
『光源氏が愛した王朝ブランド品』(河添房江著、08角川学芸出版刊)などがあります。
『季語で読む源氏物語』(西村和子著、07年飯塚書店刊)があり、室内装飾や道具類あるいは衣装と小物類について源氏本文にしばしば出てくる「唐物」という外来品に関して平安日本の海外交流を調べた
『源氏物語と東アジア世界』(河添房江著、07年日本放送出版協会刊)や
『光源氏が愛した王朝ブランド品』(河添房江著、08角川学芸出版刊)などがあります。

また光源氏は心ならずも須磨流れの旅に出たり、数奇な運命を終えた夕の娘「玉鬘」は遠く九州に流れたりしますが、物語に登場する主要人物はよく神社詣での 旅に出ます。旅については『源氏物語の近江を歩く』(畑裕子著、08年サンライズ出版刊)が最近出されました。また旅行記ではありませんが、源氏の地理と もいうべき『源氏物語の京都案内』(08年刊文春文庫)、
『京都源氏物語地図』(紫式部顕彰会・角田文衛、07年思文閣出版刊)などもあります。
源氏の時代背景、とりわけ政治権力については多くの中世史がありますが、
『源氏物語の時代— 一条天皇と后たちのものがたり』(山本淳子著、07年朝日新聞社刊)に大変詳しく書かれています。特に源氏を対象にしたものではないのですが、音楽については
『雅楽—時空を超えた遙かな調べ』(鳥居本幸代著、07年春秋社刊)なども関連書としていいでしょう。
『京都源氏物語地図』(紫式部顕彰会・角田文衛、07年思文閣出版刊)などもあります。
源氏の時代背景、とりわけ政治権力については多くの中世史がありますが、
『源氏物語の時代— 一条天皇と后たちのものがたり』(山本淳子著、07年朝日新聞社刊)に大変詳しく書かれています。特に源氏を対象にしたものではないのですが、音楽については
『雅楽—時空を超えた遙かな調べ』(鳥居本幸代著、07年春秋社刊)なども関連書としていいでしょう。

長い物語なので「須磨」あたりで一服したくなります。それはそれでいいのですが、その後読み続けることを失念してしまうことが多いようです。それを「須磨がえり」というようですが、その原因の一つは、あまりにも昔のことどもが多く、それを一々確かめながら読み進める煩わしさにあるようです。そんな煩わしさ の例をひとつだけ例を上げるとこういうことです。
そうしたことどもについて晶子は、始めからそういう方針だったのでしょうか、出来る限り訳文で示そうとしています。注釈としては光源氏の生い立ちから逝去までの年譜とその後の主人公匂宮の年譜、それに物語に登場する主要人物を系統図にまとめた注記のみを下巻末に掲載するだけで、実にあっさりしています。成熟した読み手ならばそれで十分かもしれませんが、初読者には不親切です。
そうしたことどもについて晶子は、始めからそういう方針だったのでしょうか、出来る限り訳文で示そうとしています。注釈としては光源氏の生い立ちから逝去までの年譜とその後の主人公匂宮の年譜、それに物語に登場する主要人物を系統図にまとめた注記のみを下巻末に掲載するだけで、実にあっさりしています。成熟した読み手ならばそれで十分かもしれませんが、初読者には不親切です。
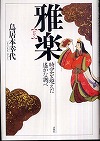
谷崎は、訳文の紙面上部に頭注の欄を置き、文中の人物呼称、有職故実、和歌の解釈などをことこまかく記しています。頭注は、巻末注と異なり読み手にとって簡便ですが、紙面が小うるさい感じを免れません。高校時代の古文の教科書を思い出します。
円地は、先に述べたように、各篇冒頭にその篇の物語の要約と登場人物の紹介とそれらの人物の関係を示す系統図を配し、さらに上中下各巻末に有職故実、官位名、地名などなどの語注、さらに宮中略図や建物構造図などを示しています。
聖子は、光源氏の生涯を中心にして新しい恋愛物語を書こうとしたので、有職故事には格別の注記はまったくありません。
円地は、先に述べたように、各篇冒頭にその篇の物語の要約と登場人物の紹介とそれらの人物の関係を示す系統図を配し、さらに上中下各巻末に有職故実、官位名、地名などなどの語注、さらに宮中略図や建物構造図などを示しています。
聖子は、光源氏の生涯を中心にして新しい恋愛物語を書こうとしたので、有職故事には格別の注記はまったくありません。
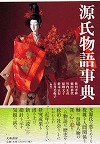
寂聴の訳文はつとめて現代読者がイメージできるように訳出されていますが、注記も各巻末に登場人物の関係を示した系図と丁寧な語句解釈が掲げられていま す。彼女はおそらく一切の注記を省き、訳文本文で処理したいと心をくだいたのではないでしょうか。時代あるいは歴史小説読者もそれを望みますが、そのよう にしていたら全10巻はおそらく全100巻にも及ばざるを得なかったでしょう。それはあまりにも非現実的です。
ところで現代語訳の注記とは別に、『源氏物語事典』(松田孝和ほか編、02年大和書房刊)という本があります。これなどは源氏にまつわる有職故事・歴史・地理・文学に関する参考書で、初学の源氏研究はもとより、一般の源氏読者にも役に立つ参考書です。
ところで現代語訳の注記とは別に、『源氏物語事典』(松田孝和ほか編、02年大和書房刊)という本があります。これなどは源氏にまつわる有職故事・歴史・地理・文学に関する参考書で、初学の源氏研究はもとより、一般の源氏読者にも役に立つ参考書です。
※書籍情報は、株式会社紀伊国屋書店の書籍データからの転載です。
関連書籍
季語で読む源氏物語
西村和子飯塚書店
源氏物語と東アジア世界
河添房江日本放送出版協会
光源氏が愛した王朝ブランド品
河添房江角川学芸出版 角川グループパブリッシング〔発売〕
源氏物語の近江を歩く
畑裕子(彦根)サンライズ出版
源氏物語の京都案内
文藝春秋文藝春秋
京都源氏物語地図
紫式部顕彰会 角田文衛思文閣出版
源氏物語の時代—一条天皇と后たちのものがたり
山本淳子朝日新聞社
雅楽—時空を超えた遙かな調べ
鳥居本幸代春秋社
源氏物語事典
林田孝和 植田恭代 竹内正彦 原岡文子 針本正行 吉井美弥子大和書房
カフェブレイク・ブックトーク「源氏物語千年」 インデックス
-
第1章 源氏物語の始まり
2008年05月28日 (水)
-
第2章 源氏物語千年の伝承~それは写本板本を通じて伝えられてきた~
2008年06月09日 (月)
-
第3章 いま源氏を読む
2008年06月18日 (水)
-
第4章 じっくり楽しむなら寂聴、すばやく読みとりたいなら円地文子
2008年06月27日 (金)
-
第5章 和歌による想いのやりとり
2008年07月07日 (月)
-
第6章 源氏に書かれている千年前の人々の暮らし
2008年07月16日 (水)
-
第7章 源氏は物語絵でも楽しまれた
2008年07月23日 (水)
注目の記事
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月07日 (日) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
11月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....