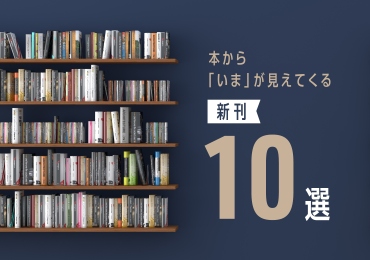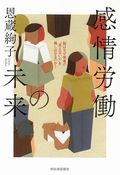六本木ヒルズライブラリー
地図のWikipedia あなたがつくる『みんなの地図、OSM(Open Street Map)』を学ぼう!
天空のマップ・カフェ
メンバーズ・コミュニティ
更新日 : 2014年06月24日
(火)
開催日:2014年4月25日(金)19:15~21:15

今回の定例会では、当初「Open Street Map」を皆で作る予定でしたが、機材の準備が整わず、今回はまず手始めとしてマップコンシェルジュ株式会社代表の古橋大地さんに、地図のWikipediaともいうべき「Open Street Map」について、その現状や実際の利用の仕方などについてお話を話して頂きました。
「Open Street Map」は2004年にイギリスで創設され、日本では2008年頃から参加しているそうです(今年の8月で10周年だそうです)。
Wikipediaの成功に触発され「地図のWikipedia」目指して活動が始まったと言われているとおり、一般の参加者が自由に記述し編集でき使用できる事をその特徴としています。
初めは少数の参加者が航空写真やGPSソフトなどを使用して地道に道路を描いたり、建物を描いたりしていましたが、参加者も世界中で増え、2011年頃にはヨーロッパの地図はコンプリートしたと言われる程になったそうです。
また一つ一つ手作業で作成される地域がある一方、政府機関や自治体などから基本的な地図データを提供してもらい後は修正を加えて日々更新がされていく地域もあるようです。
最近ではスポンサー企業と「マッピングパーティー」と呼ばれるイベントを開催しています。参加者と一緒に地域をハイキングのように歩くことで道路・建物の情報だけでなくどんなお店があるとか、地域の歴史が書き込まれて充実したものになって行きます。
一般の方が自由に参加している分、精度に難があるとも言われて来ましたが、非常に多くの参加者が累積的に参画することによって精度も上がっているようです。それよりも刻々と更新されているので震災や自然災害などのとき迅速に現状が把握できるという点が市販の地図やWeb上の地図サービスなどのパッケージ化されたものとは大きく異なる要素だと思われます。
「Open Street Map」は2004年にイギリスで創設され、日本では2008年頃から参加しているそうです(今年の8月で10周年だそうです)。
Wikipediaの成功に触発され「地図のWikipedia」目指して活動が始まったと言われているとおり、一般の参加者が自由に記述し編集でき使用できる事をその特徴としています。
初めは少数の参加者が航空写真やGPSソフトなどを使用して地道に道路を描いたり、建物を描いたりしていましたが、参加者も世界中で増え、2011年頃にはヨーロッパの地図はコンプリートしたと言われる程になったそうです。
また一つ一つ手作業で作成される地域がある一方、政府機関や自治体などから基本的な地図データを提供してもらい後は修正を加えて日々更新がされていく地域もあるようです。
最近ではスポンサー企業と「マッピングパーティー」と呼ばれるイベントを開催しています。参加者と一緒に地域をハイキングのように歩くことで道路・建物の情報だけでなくどんなお店があるとか、地域の歴史が書き込まれて充実したものになって行きます。
一般の方が自由に参加している分、精度に難があるとも言われて来ましたが、非常に多くの参加者が累積的に参画することによって精度も上がっているようです。それよりも刻々と更新されているので震災や自然災害などのとき迅速に現状が把握できるという点が市販の地図やWeb上の地図サービスなどのパッケージ化されたものとは大きく異なる要素だと思われます。

ところでWeb上の地図サービスというとG社やY社で提供されているものが大変よく知られていて多く利用されていますが、利用者が個人利用の範囲を超えてコピーしたり、あるいは印刷して他人に配布する、提供されているサービスの範囲を超えて情報を書き加えるなどの行為は「著作権の侵害」となるということは意外と知られていないようです。
地図の持っている基本情報のみならず、その情報を見やすくするような編集方法やデザイン性というものは誰かの創作物であるということはうっかりと見落としがちです。
ちなみに古橋氏は海外出張の際にもOpen Street Mapを使用しているそうです。
当日はアカウントの作成の仕方も実演して頂きました。地図好きにとっては当たり前のようにOpen Street Mapを使用している日もすぐそこかもしれません。
次回は、ぜひ「Open Street Map」の作成をしてみたいです。
地図の持っている基本情報のみならず、その情報を見やすくするような編集方法やデザイン性というものは誰かの創作物であるということはうっかりと見落としがちです。
ちなみに古橋氏は海外出張の際にもOpen Street Mapを使用しているそうです。
当日はアカウントの作成の仕方も実演して頂きました。地図好きにとっては当たり前のようにOpen Street Mapを使用している日もすぐそこかもしれません。
次回は、ぜひ「Open Street Map」の作成をしてみたいです。
注目の記事
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月07日 (日) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
11月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....