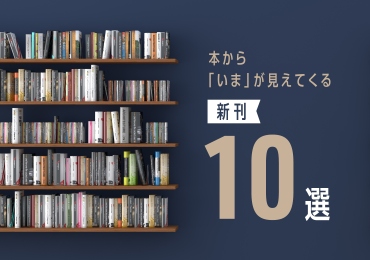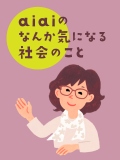六本木ヒルズライブラリー
第12回定例会「医療と情報技術の交差点で、次世代情報システムを模索する」
士業道場 2012年10月の定例会
メンバーズ・コミュニティ
更新日 : 2012年11月05日
(月)
開催日 2012年10月19日(金)19:00~20:30

士業道場の第十二回定例会は、都立広尾病院小児科医長、山本康仁医師に医療現場の情報活用技術について、その先進事例を解説していただきました。
【概要】
誰もがスマートフォンを持ち歩きTwitterやFacebookなどSNSが普通になった昨今、ITと関わらずに生活することの方が難しくなりました。医療現場でも同様に多くの電子機器が利用され、私たちの健康を支えています。今回の定例会では、「医療と情報技術の交差点で、次世代情報システムを模索する」と題して、電子カルテと連携して情報を活用するシステムに関して詳細な解説がありました。
【小児科医について】
小児科医は、各科の医師の中でも特にコミュニケーション能力が必要となる分野です。患児が上手く自分の症状について表現できず、患者の保護者からも症状について聞かなければならないことや、患児の立場で医療を提供しつつも保護者の意向も汲み取る必要が有り、難しい仕事です。
【都立広尾病院の次世代情報システムについて】
都立広尾病院は都立病院の中では災害医療センターとして位置づけられており、独立行政法人国立病院機構災害医療センター(立川市)とともに東京都の基幹災害医療センターとなっています。また、都民の安全安心を図るため、「東京ER」を担い24時間365日医療を提供しているだけではなくDMATなどをはじめとする現場派遣医療チームなど、あらゆる分野で医療サービスを提供しています。また、島しょ医療にも重点を置いており、病院屋上にヘリポートも保有しています。
都立広尾病院は2004年、電子カルテの情報をより有効に活用するために、電子カルテのデータを集約・分析するデータウェアハウスを独自に構築。データベース管理ソフト「FileMaker Pro」をデータベースエンジンに用いて、患者の診察状況をリアルタイムに把握できるシステムとなっています。こうした広尾病院のIT化推進を一手に担っているのが、小児科医長兼IT推進担当の山本康仁氏です。
【都立広尾病院の次世代情報システムの特徴】
院内にある約780台の電子カルテ端末だけではなく、多くの二次システムや各種医療機器から登録される膨大な医療情報をリアルタイムに収集し、患者の診療状況や治療計画などを集約して一覧表示することが可能となっています。膨大な医療情報のリアルタイムデータを基に、院内全体のデータ解析を行うことで、例えば多くの外来患者の症候から、インフルエンザの流行を早期に把握するといったことも可能となっています。また、病院内の抗菌薬使用状況を総合的に監視することで、耐性菌の発現そのものを制御するといった、攻勢的な院内感染制御にも活用されています。
このような電子カルテデータの解析にとどまらず、医師が電子端末にアクセスするデータとPHSの位置情報を活用することにより、院内での医師の動線をある程度把握し、緊急の情報をPHSの自動音声システムで伝達し、医療活動をサポートする仕組みを構築しています。
【システム構築の際に留意した点】
医療の現場においては、膨大な情報が流通しており、CDSS(Clinical Decision Support System)は情報を取捨選択することが重要で、伝達する情報が多くなり過ぎると最終的に情報が無視されてしまいます。
この点、次世代情報システムの構築においては、Ambient Intelligence、つまりは、医療の現場に溶け込み、一体化させることで医療活動を支援する仕組みとして機能させることを重視しています。このため、端末に対する医療者の操作は極力排除し、視覚的な文字情報のみならず、明瞭かつ簡潔な音声伝達を実現するなど、多くの工夫が施されています。
院内の医療活動を支援するシステムの構築に際しては、患者を目の前にして、だれよりも状況を把握している者だけではなく、俯瞰的に情報を収集し、気付きを複数の関係者と共有できるように、システムが医療者のコミュニケーションを引き出します。広尾病院の次世代医療情報システムは、医療情報機器のみならず電話交換機を制御するなど、新たな医療判断支援を提供しています。
【概要】
誰もがスマートフォンを持ち歩きTwitterやFacebookなどSNSが普通になった昨今、ITと関わらずに生活することの方が難しくなりました。医療現場でも同様に多くの電子機器が利用され、私たちの健康を支えています。今回の定例会では、「医療と情報技術の交差点で、次世代情報システムを模索する」と題して、電子カルテと連携して情報を活用するシステムに関して詳細な解説がありました。
【小児科医について】
小児科医は、各科の医師の中でも特にコミュニケーション能力が必要となる分野です。患児が上手く自分の症状について表現できず、患者の保護者からも症状について聞かなければならないことや、患児の立場で医療を提供しつつも保護者の意向も汲み取る必要が有り、難しい仕事です。
【都立広尾病院の次世代情報システムについて】
都立広尾病院は都立病院の中では災害医療センターとして位置づけられており、独立行政法人国立病院機構災害医療センター(立川市)とともに東京都の基幹災害医療センターとなっています。また、都民の安全安心を図るため、「東京ER」を担い24時間365日医療を提供しているだけではなくDMATなどをはじめとする現場派遣医療チームなど、あらゆる分野で医療サービスを提供しています。また、島しょ医療にも重点を置いており、病院屋上にヘリポートも保有しています。
都立広尾病院は2004年、電子カルテの情報をより有効に活用するために、電子カルテのデータを集約・分析するデータウェアハウスを独自に構築。データベース管理ソフト「FileMaker Pro」をデータベースエンジンに用いて、患者の診察状況をリアルタイムに把握できるシステムとなっています。こうした広尾病院のIT化推進を一手に担っているのが、小児科医長兼IT推進担当の山本康仁氏です。
【都立広尾病院の次世代情報システムの特徴】
院内にある約780台の電子カルテ端末だけではなく、多くの二次システムや各種医療機器から登録される膨大な医療情報をリアルタイムに収集し、患者の診療状況や治療計画などを集約して一覧表示することが可能となっています。膨大な医療情報のリアルタイムデータを基に、院内全体のデータ解析を行うことで、例えば多くの外来患者の症候から、インフルエンザの流行を早期に把握するといったことも可能となっています。また、病院内の抗菌薬使用状況を総合的に監視することで、耐性菌の発現そのものを制御するといった、攻勢的な院内感染制御にも活用されています。
このような電子カルテデータの解析にとどまらず、医師が電子端末にアクセスするデータとPHSの位置情報を活用することにより、院内での医師の動線をある程度把握し、緊急の情報をPHSの自動音声システムで伝達し、医療活動をサポートする仕組みを構築しています。
【システム構築の際に留意した点】
医療の現場においては、膨大な情報が流通しており、CDSS(Clinical Decision Support System)は情報を取捨選択することが重要で、伝達する情報が多くなり過ぎると最終的に情報が無視されてしまいます。
この点、次世代情報システムの構築においては、Ambient Intelligence、つまりは、医療の現場に溶け込み、一体化させることで医療活動を支援する仕組みとして機能させることを重視しています。このため、端末に対する医療者の操作は極力排除し、視覚的な文字情報のみならず、明瞭かつ簡潔な音声伝達を実現するなど、多くの工夫が施されています。
院内の医療活動を支援するシステムの構築に際しては、患者を目の前にして、だれよりも状況を把握している者だけではなく、俯瞰的に情報を収集し、気付きを複数の関係者と共有できるように、システムが医療者のコミュニケーションを引き出します。広尾病院の次世代医療情報システムは、医療情報機器のみならず電話交換機を制御するなど、新たな医療判断支援を提供しています。

【山本康仁先生について】
医師(小児科専門医、アレルギー専門医)。都立広尾病院 小児科医長兼IT推進担当。H24厚生労働科研「健康危機事象の早期探知システムの実用化に関する研究」共同研究者。東京マッキントッシュユーザー会会長。
専門分野は、アレルギー一般、喘息、アトピー性皮膚炎など。
医師(小児科専門医、アレルギー専門医)。都立広尾病院 小児科医長兼IT推進担当。H24厚生労働科研「健康危機事象の早期探知システムの実用化に関する研究」共同研究者。東京マッキントッシュユーザー会会長。
専門分野は、アレルギー一般、喘息、アトピー性皮膚炎など。

終了後は、懇親会を行いました
注目の記事
-
08月25日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年8月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
08月25日 (月) 更新
aiaiのなんか気になる社会のこと
「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....
-
08月07日 (木) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....