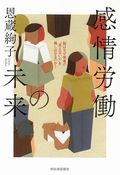記事・レポート
活動レポート
江戸の“粋”を感じる
~「没後150年 歌川国芳展」から~
活動レポート
[アカデミーヒルズ活動レポート]
49階アカデミーヒルズのエントランスショーケースでは、「歌川国芳めでた絵を飾り 一揚来福」 (2011/12/28~2月下旬予定)を展開しています。この展示を眺めていると、もっと「観てみたい!」という欲求に駆られて、“「没後150年 歌川国芳展」(森アーツセンターギャラリー)へ足を延ばしてきました。文/kumada
180年前に、国芳が東京スカイツリーを予言か?
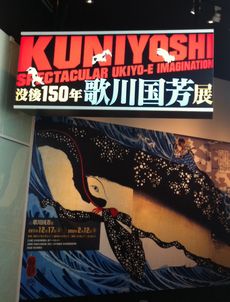
展覧会の入口の様子
昨年12月中旬から始まった「没後150年 歌川国芳展」(森アーツセンターギャラリー)の入場者数が、1月28日(土)に10万人を突破したそうです。ちょうどこの日に会場を覘いたら、閉館1時間前という時間にも関わらず、並ばなければ作品が見れない程に混んでいました。
そして、意外にも20代~30代の若い層が多く来場されていました。
六本木ヒルズという土地柄も関係しているのでしょうか?
または、今から180年前に国芳が描いた「東都三つ股の図」という作品に、東京スカイツリーにそっくりな塔が描かれているというミステリアスな話題も影響しているのでしょうか?(詳細はこちら)
とにかく会場は、国芳の作品を真剣に観る人々でごった返していました。
そして、意外にも20代~30代の若い層が多く来場されていました。
六本木ヒルズという土地柄も関係しているのでしょうか?
または、今から180年前に国芳が描いた「東都三つ股の図」という作品に、東京スカイツリーにそっくりな塔が描かれているというミステリアスな話題も影響しているのでしょうか?(詳細はこちら)
とにかく会場は、国芳の作品を真剣に観る人々でごった返していました。
江戸の粋とは
~二人の浮世絵師(歌川国芳と東洲斎写楽)から感じたとこ~

国芳展と写楽展の図録
歌川国芳(1797~1861)は、武者絵、美人画、役者絵、風景画、風刺絵など幅広いジャンルの作品を残しています。
驚くのは、その作品の斬新さ。21世紀の今見ても新鮮さ感じます。ポップアートやトリックアートなど多彩な作品が多く、当時の有名な浮世絵師達(歌川広重、葛飾北斎、喜多川歌麿)の作品とは一味違った印象、感動を当時の人々に与えたのではないかと想像します。
ところで、国芳の作品を観ていると、昨年(2011/5~6)開催され特別展「写楽」(東京国立博物館)を思い出しました。
写楽は謎の浮世絵師として有名です。国芳が生まれるちょっと前の1794年5月に突然、28枚の黒雲母摺りの大判錦絵でデビュー。その斬新でデフォルメされた役者絵は注目の的でした。しかしたった10か月で表舞台から姿を消したため、写楽はミステリアスな存在になっています。
そこで、国芳と写楽の共通項を探ってみました。
1.ミステリアスな存在
写楽は正に「謎の浮世絵師」としてミステリアスな存在です。また、180年前に東京スカイツリーを彷彿させるような作品を残した国芳もミステリアスな一面を持っているかもしれません。
2.作品を世に出したプロデューサー(版元)の存在
写楽には蔦屋重三郎という版元の存在は欠かせません。そして国芳も版元加賀屋から出版された「風俗水滸伝」シリーズで浮世絵師としての地歩を固めたと言われています。このように目利き、現在のギャラリストの存在も欠かせなかったことも共通しているのではないでしょうか。
3.斬新な作品
そして、何といっても一番の共通点は、作品の斬新さではないでしょうか。写楽と国芳の作品は、21世紀の今観てもまったく古臭くなくポップに映る凄さを持っています。既存にとらわれることなく新しいものにチャレンジする精神を感じます。
この精神が「江戸の粋」を創り上げているのかもしれません。
浮世絵の専門的な知識は持っていませんが、国芳の作品を観ていると上記のような想像が広がり、質と量ともに楽しめた「没後150年 歌川国芳展」でした。
驚くのは、その作品の斬新さ。21世紀の今見ても新鮮さ感じます。ポップアートやトリックアートなど多彩な作品が多く、当時の有名な浮世絵師達(歌川広重、葛飾北斎、喜多川歌麿)の作品とは一味違った印象、感動を当時の人々に与えたのではないかと想像します。
ところで、国芳の作品を観ていると、昨年(2011/5~6)開催され特別展「写楽」(東京国立博物館)を思い出しました。
写楽は謎の浮世絵師として有名です。国芳が生まれるちょっと前の1794年5月に突然、28枚の黒雲母摺りの大判錦絵でデビュー。その斬新でデフォルメされた役者絵は注目の的でした。しかしたった10か月で表舞台から姿を消したため、写楽はミステリアスな存在になっています。
そこで、国芳と写楽の共通項を探ってみました。
1.ミステリアスな存在
写楽は正に「謎の浮世絵師」としてミステリアスな存在です。また、180年前に東京スカイツリーを彷彿させるような作品を残した国芳もミステリアスな一面を持っているかもしれません。
2.作品を世に出したプロデューサー(版元)の存在
写楽には蔦屋重三郎という版元の存在は欠かせません。そして国芳も版元加賀屋から出版された「風俗水滸伝」シリーズで浮世絵師としての地歩を固めたと言われています。このように目利き、現在のギャラリストの存在も欠かせなかったことも共通しているのではないでしょうか。
3.斬新な作品
そして、何といっても一番の共通点は、作品の斬新さではないでしょうか。写楽と国芳の作品は、21世紀の今観てもまったく古臭くなくポップに映る凄さを持っています。既存にとらわれることなく新しいものにチャレンジする精神を感じます。
この精神が「江戸の粋」を創り上げているのかもしれません。
浮世絵の専門的な知識は持っていませんが、国芳の作品を観ていると上記のような想像が広がり、質と量ともに楽しめた「没後150年 歌川国芳展」でした。
もっと、アートを楽しむ機会を!
専門的な知識はなくても、観る側の気持ち次第で、自分なりに楽しめるのもアートの一つの魅力ではないでしょうか?
「日常の生活にもっとアートを感じる機会があってもいいのではないか」、そして「自分にとって、アートってどんなこと?」と問いかけてみると、「毎日の生活がちょっと変わって見えてくるかもしれない」と考え、アカデミーヒルズでは、昨年(2011/11/23)、六本木アートカレッジを開催しました。
2012年は、もっとアートを身近に感じてもらう機会を設けるために「六本木アートカレッジ セミナー」を、定期的に開催する予定です。
こうご期待を!
「日常の生活にもっとアートを感じる機会があってもいいのではないか」、そして「自分にとって、アートってどんなこと?」と問いかけてみると、「毎日の生活がちょっと変わって見えてくるかもしれない」と考え、アカデミーヒルズでは、昨年(2011/11/23)、六本木アートカレッジを開催しました。
2012年は、もっとアートを身近に感じてもらう機会を設けるために「六本木アートカレッジ セミナー」を、定期的に開催する予定です。
こうご期待を!
注目の記事
-
12月23日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
12月07日 (日) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
11月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....