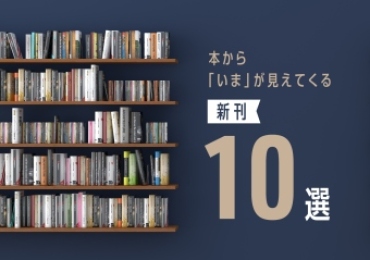本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。
新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介します。
今月の10選は、『感情労働の未来』『ポストヨーロッパ』など。あなたの気になる本は何?
※「本から「いま」が見えてくる新刊10選」をお読みになったご感想など、お気軽にお聞かせください。

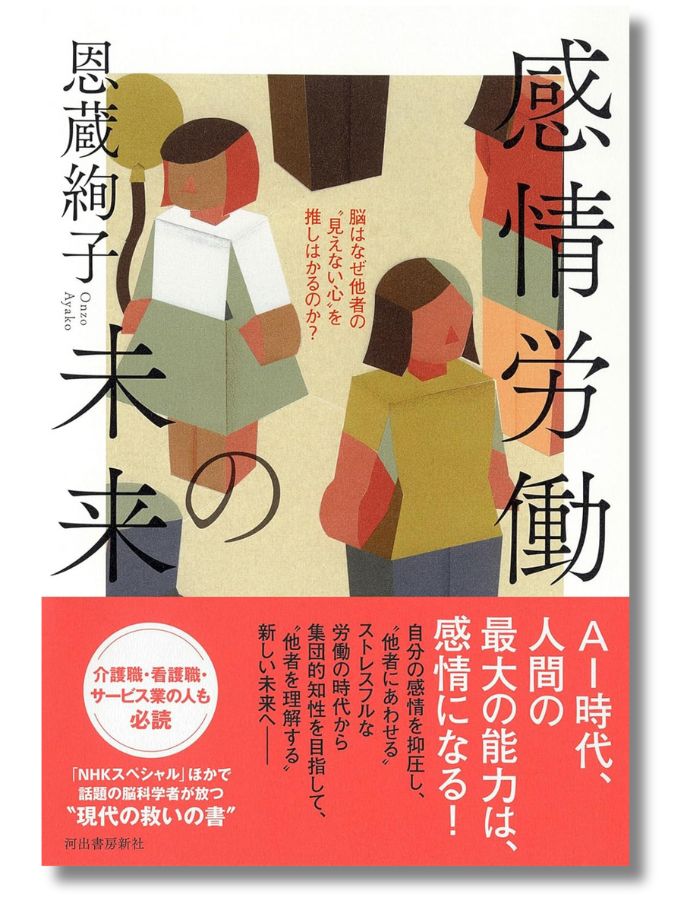
脳はなぜ他者の“見えない心”を推しはかるのか?
ただ、40年以上前に概念化されているにも関わらず、感情労働は社会の中で適切に評価されていないのかもしれません。“感情をコントロールすることは必須だけど、そこで頑張っても評価されない”と著者は指摘します。果たして私たちは感情について、そして感情労働についてどこまで知っているのでしょうか。
本書は脳科学者である著者が、社会学的な文脈で語られていた感情労働を、脳科学的な観点から捉え直した一冊。「(脳科学的に)感情とは何か」から始まり、感情労働を職業的要請によって感情をコントロールする技能という側面だけでなく、他者の心を推しはかり、また、自分自身の心の動きも理解することで人と人が協働する手助けとなる技能として、積極的な面からも再評価していきます。
“感情労働は必ずしも悪いものではなく、自分も他人ももっと幸福にする感情の動かし方があるということなのだ”と著者は書きます。
一日中続くオンライン会議、SNSやメッセージアプリでのテキストのみの会話、Chat GPTに代表される大規模言語モデルとの対話など、コミュニケーション環境の変化の中で、感情労働のあり方もまた変化しています。感情労働を再評価することは、広義の「働きかた」を見直し、仕事と暮らしをよりよくしていくことにつながるかもしれません。
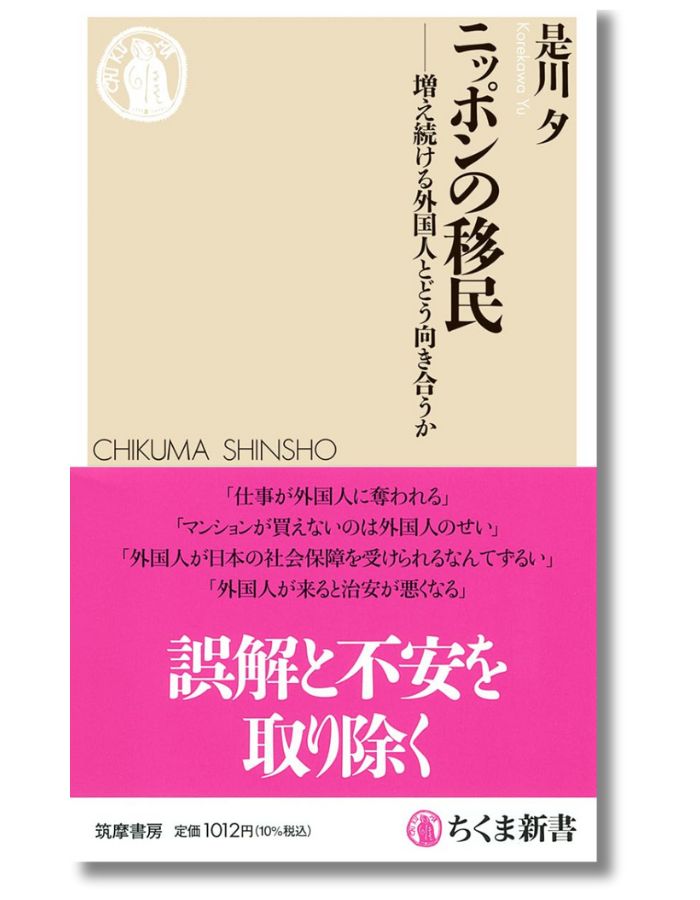
ニッポンの移民
増え続ける外国人とどう向き合うか
昨今テレビやSNSで何かと話題にのぼる移民問題。果たしてそれはどんな「問題」なのか、日本の移民政策について長く研究・提言を続けてきた第一人者である著者が、その実態を丁寧に解説します。国際比較や移民政策の歴史などマクロな視点を背景に、日本ならではの移民との向き合い方を考えていく本書は、印象論や感情論が先行しがちなこの問題の捉え方の地図となるような一冊。人口減少が顕著になっていくこれからの社会を考える上で、避けて通れないテーマの一つと言えるでしょう。
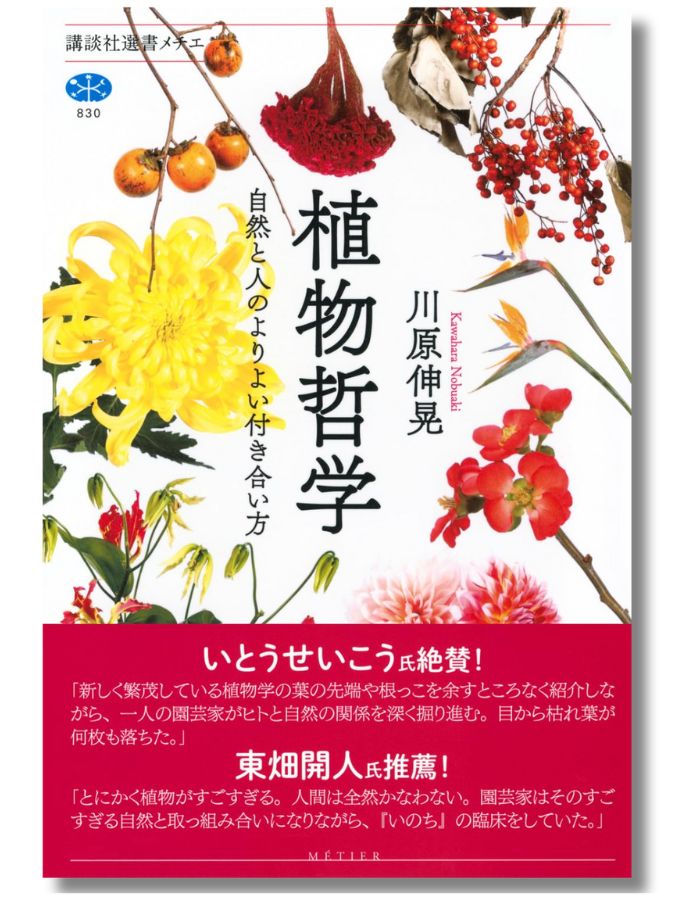
植物哲学
自然と人のよりよい付き合い方
植物のアフターケアサービス「プランツケア」や、役目を終えた植物を再生・再販する「Reborn Plants」などの取り組みで注目される港区三田の植物店「REN」。その店主であり、本書の著者でもある川原伸晃氏は、1919年に同地で創業した園芸店の4代目でもあります。自身の生い立ちを「いけばな生まれ、ガーデニング育ち」と表現するように、幼少期から植物と人の関わり方を目にし、実践してきた中で育まれた独自の「植物哲学」は、まさに人と自然との付き合い方が捉え直されるもの。マンガから哲学書まで様々な本を参照していく語り口もユニークな一冊。
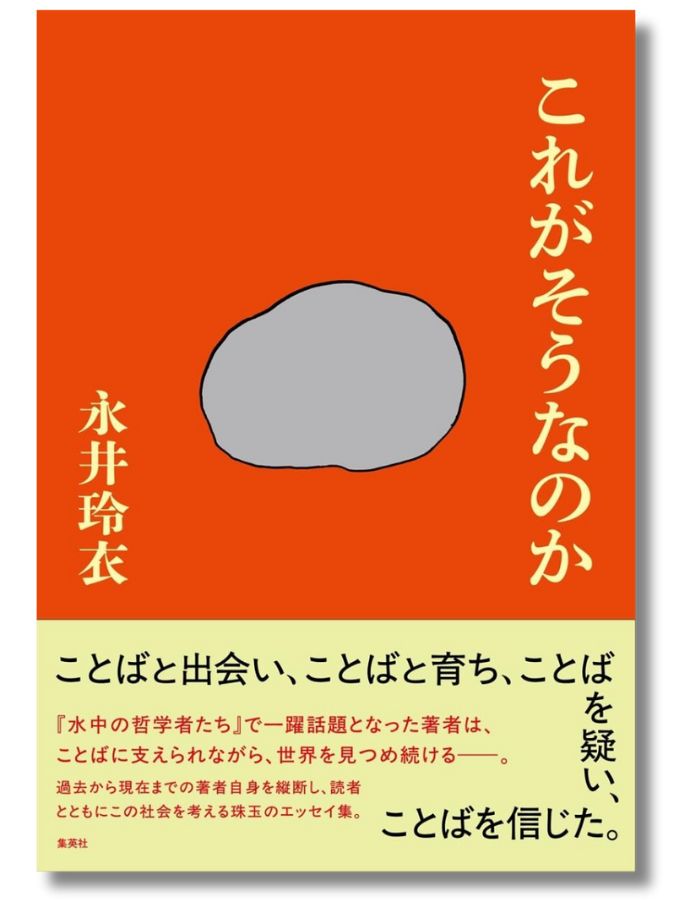
これがそうなのか
学校や企業や自治体などでの哲学対話の場や、政治や戦争について語り合い、聞き合う場をひらく活動を続けている著者が、日々の生活や本の中、哲学対話の場で出会ってきた言葉たちと、そこから立ち上がる「問い」について綴ったエッセイ集。いつの間にか自分が使うようになった、あるいは誰かが使うようになった言葉の前で立ち止まってみると、なぜその言葉が現れたのかという問いが生まれ、それが世の中の何かと繋がっていることに気づかされます。学校で習うような「哲学」や「言語学」ともまた違う、生きた言葉の面白さが詰まった一冊。
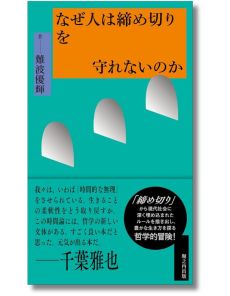
なぜ人は締め切りを守れないのか
タイトルを見た瞬間、ドキッとする人が多そうな本書。冒頭で著者は“〈締め切りの時間〉と私たちが〈生きている時間〉がずれるから、締め切りが守れなくなる”と書いています。つまり、この本は現代社会を生きる私たちに課せられた「時間」について論じた本であると言えます。締め切りを守れないことは個人の能力や努力、あるいは組織の不和の問題という面で語られがちですが、そもそも人間は締め切りを守れる存在なのか…? 哲学論でもあり、仕事論としても読める、若き俊英の注目作。
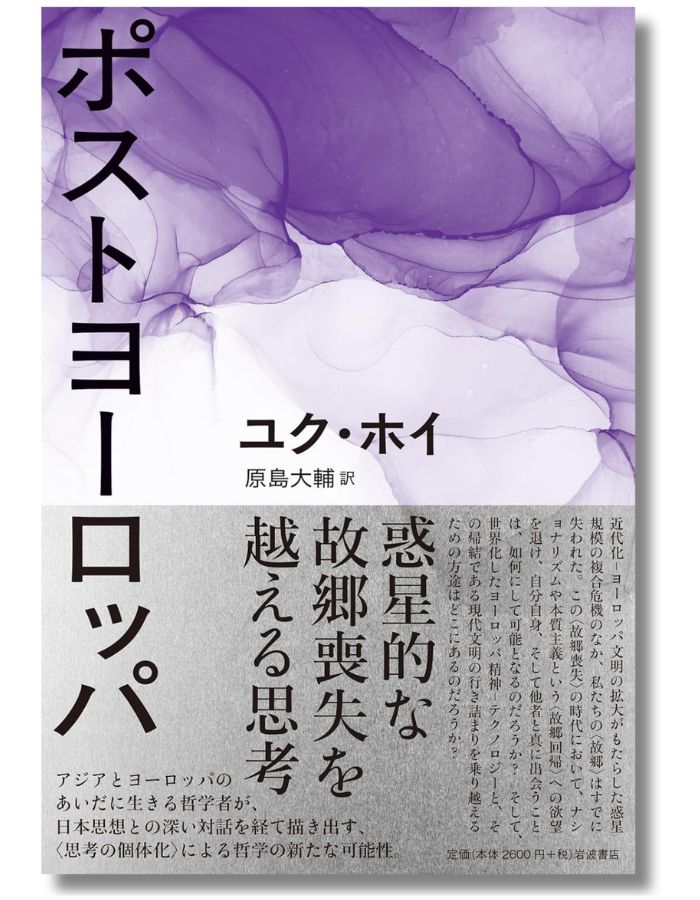
ポストヨーロッパ
テクノロジーとは何か、あるいは人と技術の関係について哲学的に探究する「技術哲学」という分野で昨今注目を集める香港出身の哲学者ユク・ホイ。「ポストヨーロッパ」とは、西洋哲学がテクノロジーのかたちをして世界を覆っているという現状認識のもと、ヨーロッパ中心の技術観・世界観を乗り越え、異なる文化における技術の考え方、捉え方をふまえて、新しい普遍性を見出そうとする試みです。テクノロジーが生活を支える度合いがますます高まっていく中で、その状況を批判的に捉える「技術哲学」という学問そのものにも着目したいところ。
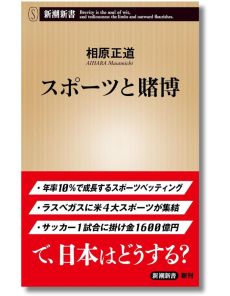
スポーツと賭博
世界で拡大の一途を辿るスポーツベッティングの市場。日本では「賭博罪」の存在によって公営ギャンブル以外は非合法であり、同時にネガティブなイメージが付きまといますが、いわゆる先進国ではほとんどの国で合法化されています。本書では、日本国内にいながらオンラインで海外のスポーツベッティングを利用したことがある人は増加しているというデータも紹介され、「公営」と「違法」が混在する微妙な状況にいるのが現在の日本。経済的、法的、文化的な側面でもその是非をめぐる振り幅が大きなこのテーマは、一人の生活者としても向き合い方を考えさせられます。
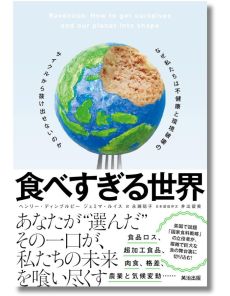
食べすぎる世界
なぜ私たちは不健康と環境破壊のサイクルから抜け出せないのか
イギリスの自然食ファーストフードチェーン〈LEON〉の経営者であり、政府からの依頼で国家食料戦略を主導した著者が描く、現代の「食」の不都合な真実。「私たちの体」「私たちの土地」「私たちの未来」という3章で構成され、食糧の生産・流通・消費の複雑かつ強固なシステムが、人々の身体と地球環境に与えている影響について警鐘を鳴らします。当たり前のようにスーパーやコンビニに食料品が並び、好きな時に好きなものを食べられる状況の背景では何が起きているのか。現在の食の問題に関心がある人には必読と言えそうな一冊です。
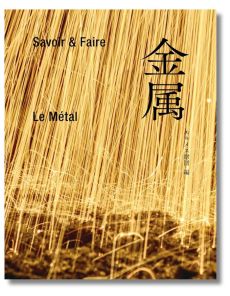
Savoir & Faire 金属
自然素材にまつわる知識や技術の共有を目指すエルメス財団による〈スキル・アカデミー〉の書籍化第3弾。「木」「土」に続いて刊行された今作は「金属」がテーマです。一つの素材を題材に、建築、アート、工芸、歴史学など分野横断的に収録されたエッセイはひとつひとつが読み応え十分。身の回りのものが何でできているか、どんな経緯でここにあるのか。そんな“素材”についての素朴な問いかけは、自然と人間の関係が捉え直される昨今重要性を増しています。本国フランスではすでに10の素材についての本が刊行されており、今後の展開が楽しみなシリーズです。
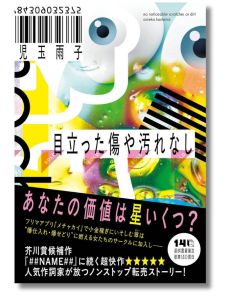
目立った傷や汚れなし
作詞家として活躍しながら小説家としても評価される著者の3作目。夫の休職をきっかけに、フリマアプリ「メチャカイ」に不用品の出品を始めた主人公は、ある日、複数人が協力しながら「メチャカイ」での転売を通じて少額の利益を得る「せどりサークル」に加入することに…。モノからゴミへ、ゴミからモノへと人の手を通じて価値は変化し、また、その価値観をめぐっても絆が生まれたり関係にヒビが入ったりしてゆく。その様子からは、現在の社会がいかに多様なモノに溢れ、それが人間同士の関係にも影響を与えているかを突きつけられます。
感情労働の未来 脳はなぜ他者の“見えない心”を推しはかるのか?
恩蔵絢子河出書房新社
ニッポンの移民 増え続ける外国人とどう向き合うか
是川夕筑摩書房
植物哲学 自然と人のよりよい付き合い方
川原伸晃講談社
これがそうなのか
永井 玲衣集英社
なぜ人は締め切りを守れないのか
難波優希堀之内出版
ポストヨーロッパ
ユク・ホイ岩波書店
スポーツと賭博
相原正道新潮社
食べすぎる世界 なぜ私たちは不健康と環境破壊のサイクルから抜け出せないのか
ヘンリー・ディンブルビー, ジェミマ・ルイス英治出版
Savoir&Faire 金属
エルメス財団 編岩波書店
目立った傷や汚れなし
児玉雨子河出書房新社
注目の記事
-
11月25日 (火) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....
-
11月07日 (金) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
-
10月20日 (月) 更新
本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年10月~
毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....