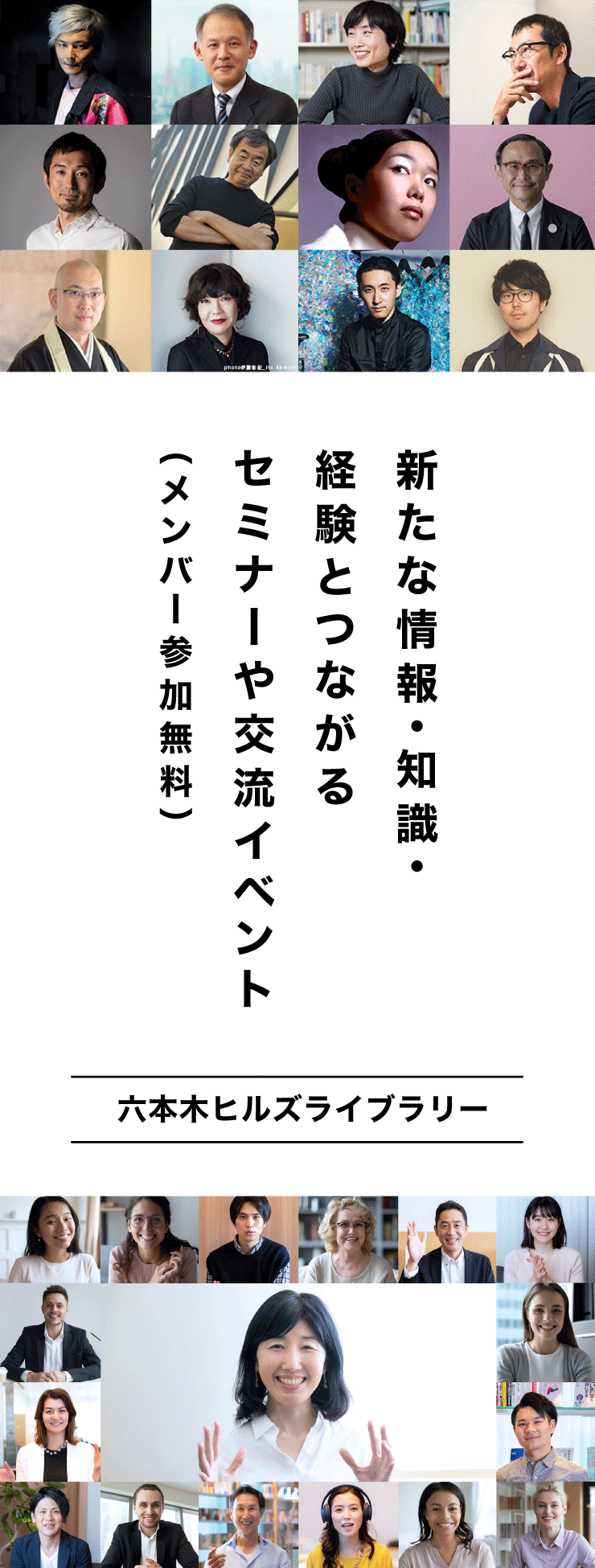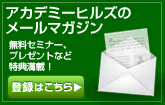記事・レポート
六本木アートカレッジ・セミナー
シリーズ「これからのライフスタイルを考える」第4回
身体の拡張:能楽師・安田登×為末大
能で読み解く、日本人の「こころ」と「からだ」
更新日 : 2017年01月17日
(火)
第3章 能とスポーツの身体的共通点

為末大(元プロ陸上選手)
短距離走と能の「すり足」
為末大: 興味深いお話がたくさん登場しましたが、僕は最近、MIT出身の遠藤謙さんとパラリンピック・アスリートの義足をつくったり、様々な業界の専門家から人工知能(AI)の話を聞いたりしているため、「未来の身体はどうなっていくのか?」という問いが常に頭にあります。
日本の短距離走の世界では1970~80年代にかけ、海外のトップ選手が採用していた「マック式ドリル」というトレーニング法が流行しました。しかし、その頃からなぜか日本の短距離走の記録が伸び悩んでしまったのです。そして1990年代の終わり頃、誰かが「どうもこれは日本人の身体には合わない」と気づいた。ちょうど僕が現役だった時代です。その後、日本人選手の走り方がどうなったかといえば、まさに能のすり足の動きです。意識して足を動かすのではなく、勝手にスッと前に出るようにすると、速く走れるようになったのです。
安田登: 能の所作の基本である「構え」(静止状態)や「運び」(動き)と同じですね。構えは、前方に引っ張られる力、後方に引き戻す力、上に引っ張られる力、それを引き戻すためにグッと地面に踏み込む四方向の力の拮抗状態を作り出します。この状態から、後方に引き戻す力を抜くと自然に足がスッと前に出る。運びはこの連続で行われるのですが、実はこのときに深層筋のひとつである大腰筋によって、腿がかすかに引き上げられているのです。しかし、表層の筋肉はほとんど使われていないために、腿に触れても柔らかい。
為末大: 短距離走のトレーニングにも似たような練習がありますし、「ナンバ走り」で有名な末續慎吾選手も、すり足の動きを参考にしていたそうです。実に興味深い共通点ですね。
見えないものをぼんやり見る
為末大: 能における「境界」は、点や線で明確に区切られているわけではなく、ある一定の広さを持ったあいまいな空間であると言われていました。
安田登: そうですね。能の演目は、大きく「現在能」と「夢幻能(むげんのう)」に分けられます。現在能というのは今の演劇に近い能で、登場人物であるシテやワキはすべて生きている人間です。物語も時間の経過とともに進行します。それに対して夢幻能のシテは、最初は人間として登場しますが、本当は神様や精霊、亡霊、怨霊、鬼、天狗など、この世ならざる存在の化身であり、本来は人の前には姿を現さない不可視の存在です。
夢幻能は、この不可視の存在であるシテを中心に、現実と異界、過去と現在を行き来しつつ、霊的な不可視な存在が、生きている人間に魂の救済を求める形で進みます。相手役のワキは必ず生きている人間なのですが、ふつうの人間はシテの姿を見ることはできません。ワキは人間ではありながら、あちらとこちらの「あわい」に立っている縁側的存在であり、だからこそ異界の存在とも出会うことができるのです。
「お盆」の発生はよくわかっていないようですが、少なくとも中国では死者を弔う祭りだったようです。それが日本に入ってくると、亡くなった方を招き入れ、そして数日間ともに過ごすという行事に変わります。この両者は似ているようで全然違います。日本人にとって、生者と死者とはもともと非常に近しい関係でした。目には見えないけれど、死者が近くにいるような感覚。私たちはそうしたものを大切にしますよね。
為末大: 目には見えないけれど、実感がある。スポーツの分野でも似たようなことがあります。人間は目から様々なデータを入手しますが、最近は何を見てどう反応しているのかを、目の動きを追跡・分析して調べる「アイトラッキング」の研究がなされています。
ボクシングなら、一般的な選手は相手の腕や手元などを注視して、細かく目を動かして反応しています。しかし、熟練者になると、相手の胸のあたりをぼんやりと眺め、ほとんど視点が動かない。表面的な動きにとらわれず、奥にある動く前の“揺らぎ”が起こる瞬間を察知しようとするそうです。
安田登: それは面白いですね。私はワキ方なので能面をつけることはありませんが、能面の目の部分はとても小さくて、ほとんど見えません。そのときに、目が後頭部にあるようなつもりでぼんやりと見ると、よく見えるそうなのです。また、夏目漱石は「小説は筋なんて読むものではない」と言っていますが、能もそうです。能を観るときには、能の演目の中に流れる、緩やかで大きな流れを「ぼんやりと」眺める。一つひとつの音や動きを注視するのではなく、それらの奥にある「ゆったりした流れ」を感じたときに、能は面白くなります。

為末大: いわゆる西洋では、演じる側と観る側は区切られている気がしますが、能は観る側も参加して、一緒に舞台をつくり上げていくわけですね。
安田登: そうなんです。フランスの劇作家ポール・クローデルは、能の舞台を「客席の海に迫り出している舞台」と表現し、能の物語は舞台の上ではなく、「すべてが観客の内部で進行する」と言いました。
たとえば、『道成寺』という能の中に「乱拍子」という不思議な舞があります。シテと小鼓による、まさに真剣勝負です。特に小鼓の流派が幸(こう)流のときがすごい。幸流の乱拍子では、掛け声や鼓の音という「聞こえている音」よりも、「無音」のほうがずっと長いんです。いや、ほとんど無音と言ってもいい。舞だって、動いているときよりも静止が長い。舞台上のほとんどの時間は、シテと小鼓の両者が無音の呼吸を互いに感じ合いながら、じっと静止しています。客席も咳ひとつしません。永遠とも思われるような無音の時間が続きます。
すると突然、裂ぱくの掛け声とともにポンッと小鼓が鳴る。と同時に、シテがスッと足を一歩出す。これは音を聞いてからではダメなのです。同時であることが大切。しかし、互いに互いを見ていません。互いの呼吸を感じる、それで行います。無音が数十秒続くこともあるこの舞(乱拍子)は、数十分間続きます。その間、舞台は息の詰まるような緊張に包まれます。
為末大: まるで放送事故のような(笑)。
安田登: ラジオでやったら、まさに放送事故ですね(笑)。能では、グッと気合を込めるような沈黙の間を「コミ(込)をとる」と言います。ふつうのコミは1秒あるかないかですが、乱拍子ではそのコミが非常に長いのです。無音が非常に長いので、ただ観ているとつまらない。しかし、お客様もコミをとりながら舞台上の息づかいを感じとり、「ここだ!」とやりはじめると途端に面白くなる。能楽堂全体がひとつの大きな呼吸、グワーッという大きなうねりに包まれるのです。無音のグルーブです。
為末大: 究極の“焦らし”ですね(笑)。同じく、大相撲の立ち会いも、互いの呼吸が合った瞬間に立ちますよね。
安田登: 今はテレビやラジオの都合で時間制限がありますが、以前は呼吸が合うまで立たなかった。観客も固唾を飲んでそれを見守り、「ここだ!」という立ち会いの一瞬を楽しんでいたようです。
安田登: そうなんです。フランスの劇作家ポール・クローデルは、能の舞台を「客席の海に迫り出している舞台」と表現し、能の物語は舞台の上ではなく、「すべてが観客の内部で進行する」と言いました。
たとえば、『道成寺』という能の中に「乱拍子」という不思議な舞があります。シテと小鼓による、まさに真剣勝負です。特に小鼓の流派が幸(こう)流のときがすごい。幸流の乱拍子では、掛け声や鼓の音という「聞こえている音」よりも、「無音」のほうがずっと長いんです。いや、ほとんど無音と言ってもいい。舞だって、動いているときよりも静止が長い。舞台上のほとんどの時間は、シテと小鼓の両者が無音の呼吸を互いに感じ合いながら、じっと静止しています。客席も咳ひとつしません。永遠とも思われるような無音の時間が続きます。
すると突然、裂ぱくの掛け声とともにポンッと小鼓が鳴る。と同時に、シテがスッと足を一歩出す。これは音を聞いてからではダメなのです。同時であることが大切。しかし、互いに互いを見ていません。互いの呼吸を感じる、それで行います。無音が数十秒続くこともあるこの舞(乱拍子)は、数十分間続きます。その間、舞台は息の詰まるような緊張に包まれます。
為末大: まるで放送事故のような(笑)。
安田登: ラジオでやったら、まさに放送事故ですね(笑)。能では、グッと気合を込めるような沈黙の間を「コミ(込)をとる」と言います。ふつうのコミは1秒あるかないかですが、乱拍子ではそのコミが非常に長いのです。無音が非常に長いので、ただ観ているとつまらない。しかし、お客様もコミをとりながら舞台上の息づかいを感じとり、「ここだ!」とやりはじめると途端に面白くなる。能楽堂全体がひとつの大きな呼吸、グワーッという大きなうねりに包まれるのです。無音のグルーブです。
為末大: 究極の“焦らし”ですね(笑)。同じく、大相撲の立ち会いも、互いの呼吸が合った瞬間に立ちますよね。
安田登: 今はテレビやラジオの都合で時間制限がありますが、以前は呼吸が合うまで立たなかった。観客も固唾を飲んでそれを見守り、「ここだ!」という立ち会いの一瞬を楽しんでいたようです。
該当講座

六本木アートカレッジ 伝統を未来へどう伝えるか
安田登(能楽師)×為末大(元プロ陸上選手)
ロボットスーツの登場、VR,AR、そして人工知能などのテクノロジーが進化する未来において、人間の身体性はどのように変わっていくのでしょうか。そのとき、我々はどのような生活を送っているのでしょうか。『日本人の身体』著者の安田登氏と、パラリンピアの育成に努める為末大氏による対談セミナー。
六本木アートカレッジ・セミナー
シリーズ「これからのライフスタイルを考える」第4回
身体の拡張:能楽師・安田登×為末大
インデックス
-
第1章「初心」とイノベーション
2017年01月17日 (火)
-
第2章 風景に溶け出していく、こころとからだ
2017年01月17日 (火)
-
第3章 能とスポーツの身体的共通点
2017年01月17日 (火)
-
第4章 動き、意識、言葉の深い関係
2017年01月17日 (火)
注目の記事
-
03月26日 (火) 更新
動的書房 ~生物学者・福岡伸一の書棚
目利きの読み手でもある生物学者の福岡伸一による、六本木ヒルズライブラリーのための選書書棚「動的書房」。2024年3月に新たに21冊が並びまし....
-
03月26日 (火) 更新
本には、人生を変え、時代を創るパワーがある!
2023年4月から2024年2月まで全6回で開催したシリーズ「編集者の視点〜時代を共に創る〜」。モデレーターの干場弓子さんと何度も企画会....
シリーズ編集者の視点〜時代を共に創る〜 <編集後記>
-
03月26日 (火) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月08日 (水) 19:00~20:30
多様な個性が育むナラティブパワー
「⾃分の物語(ナラティブ)」を語り、社会との関係性や「私たち」の目指す世界につなげていくことで、何か問題があっても、人々の共感を得て社会を変....
-
開催日 : 05月21日 (火) 12:00~12:45 / 05月21日 (火) 19:00~19:45
ゆる~くつながろう!メンバー雑談
テーマなし!年齢制限なし!ライブラリーメンバーなら誰でも参加できる雑談イベントです。肩の力を抜いて楽しく、そしてリラックスした45分を過ごし....
-
開催日 : 04月23日 (火) 19:00~20:30
「欲望」以外が資本主義のエンジンとなり得るのか?
ミクロとマクロの視点、日本と世界の視点を行き来しながら、持続可能な社会のために私たちがいまできることを考えます。スピーカーは、ファッション産....