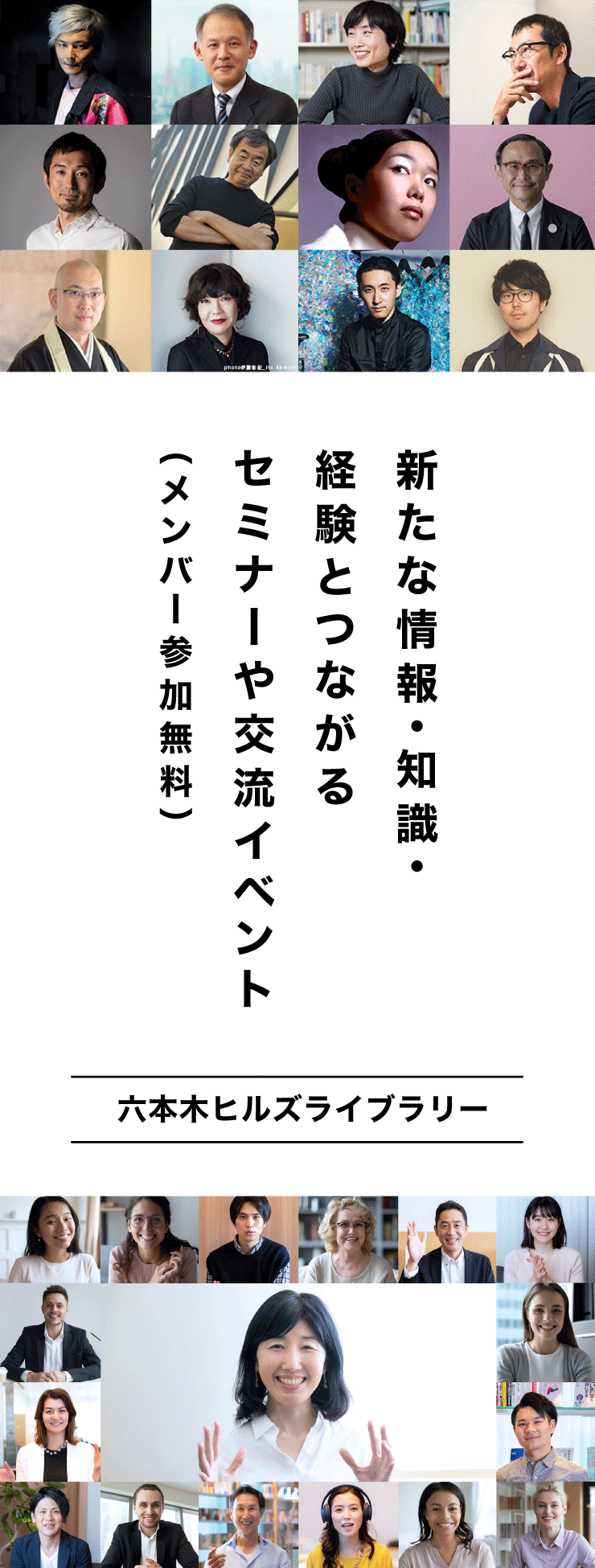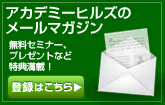記事・レポート
中田英寿×栗林隆×南條史生「伝統が開く日本の未来」
アートって、こういうことだったのか!
更新日 : 2012年05月11日
(金)
第4章 “新しさ”のない伝統工芸は“伝統”として生き残れない
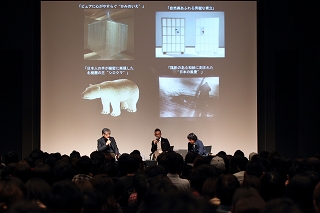
南條史生: 栗林さんはアーティストだから、今まであったようなものはつくらないんですよね。誰も考えたことがないような、クリエイティブものをつくろうとする。たとえリスクが高くてもそれに挑戦する。だから栗林さんがつくるものには、いつも驚きがあるわけです。
森美術館の「ネイチャー・センス展」での作品《ヴァルト・アウス・ヴァルト(林による林)》は、真っ白な紙でつくった大地の上に木が立っている作品でしたが、これも観客は最初は何だかわからないんです。というのは、まずは大地の下に入っちゃうので。その大地に所々穴が開いていて、そこから顔を出すと、初めて林が見えるという仕掛けでした。 今回の作品《Erde(エルデ)》も同じような仕掛けですね。頭を地球の中に突っ込むと、初めてやろうとしていることがわかるという。
栗林隆: そうですね。最初はものすごく大きいのをつくろうとしていたんです。でも会場の都合で大きさは1,600cmまでという条件だったのでそれに合わせました。
中田英寿: 和紙というと、皆さん「薄っぺらい平面のもの」を想像すると思うのですが、そのイメージを裏切ろうとするチームが多くて、大きくて立体的な作品が多かったですね。僕としては「頭に“伝統”と付く工芸というものに新しいアイディアを入れることで、新しい使い方を提案できれば」という意図だったので、皆さんが和紙の枠を超えた素晴らしいものをつくってくれたのでよかったと思っています。
南條史生: 伝統工芸は非常に大事ですが、それを維持するだけでは、つくっているものが時代のライフスタイルにだんだん合わなくなっていくので、やがて売れなくなります。そうなると伝統工芸自体が衰退してしまいます。だから伝統工芸とはいえ、新しいアイディアで違う製品をどんどんつくっていかないと、伝統工芸も生き残れないと思うんです。中田さんがやっていることは、そのポイントを突いていると思います。
中田英寿: 僕はこの活動を始めたときから「伝統工芸とアートの境界線はどこだろう?」という疑問みたいなものを感じてきました。栗林さんの《Erde(エルデ)》はアートなのか、それとも和紙でつくっているから伝統工芸品なのか——。僕のイメージでは「伝統工芸品は基本的に素材がありきでつくる生活用品」で、「アートはアイディアがあって素材を選んでつくるもの」なのですが、これについてはどうお考えですか?
栗林隆: 僕は伝統工芸というものから一番離れたところにいる人間なんです。じゃあ、伝統工芸を重んじていないのかというと、そうではなく、僕は日本人としてとても大事なものだと思っています。
この2つを誰が発信するか、というのが結構大きい気がします。伝統工芸に新しさを取り入れている人はいないわけじゃないんですけど、そこにスポットを当てて、世界に発信して宣伝できる人は少ないわけです。「中田英寿」という人間は、それができる希有な人なんです。会場のみなさんも「中田君が何をしゃべるんだろう?」と期待して来ていると思うんです。そういう人間は限られているので、そういう人がどんどん発信していけばいいと。
じゃあ僕は何をするのかといえば、伝統工芸と一緒に何かをやって云々ということじゃなくて、自分がやることをやる。僕は僕が考えていることをやる。南條さんは南條さんで、中田君は中田君で、それぞれやればいいんじゃないかと思っています。
森美術館の「ネイチャー・センス展」での作品《ヴァルト・アウス・ヴァルト(林による林)》は、真っ白な紙でつくった大地の上に木が立っている作品でしたが、これも観客は最初は何だかわからないんです。というのは、まずは大地の下に入っちゃうので。その大地に所々穴が開いていて、そこから顔を出すと、初めて林が見えるという仕掛けでした。 今回の作品《Erde(エルデ)》も同じような仕掛けですね。頭を地球の中に突っ込むと、初めてやろうとしていることがわかるという。
栗林隆: そうですね。最初はものすごく大きいのをつくろうとしていたんです。でも会場の都合で大きさは1,600cmまでという条件だったのでそれに合わせました。
中田英寿: 和紙というと、皆さん「薄っぺらい平面のもの」を想像すると思うのですが、そのイメージを裏切ろうとするチームが多くて、大きくて立体的な作品が多かったですね。僕としては「頭に“伝統”と付く工芸というものに新しいアイディアを入れることで、新しい使い方を提案できれば」という意図だったので、皆さんが和紙の枠を超えた素晴らしいものをつくってくれたのでよかったと思っています。
南條史生: 伝統工芸は非常に大事ですが、それを維持するだけでは、つくっているものが時代のライフスタイルにだんだん合わなくなっていくので、やがて売れなくなります。そうなると伝統工芸自体が衰退してしまいます。だから伝統工芸とはいえ、新しいアイディアで違う製品をどんどんつくっていかないと、伝統工芸も生き残れないと思うんです。中田さんがやっていることは、そのポイントを突いていると思います。
中田英寿: 僕はこの活動を始めたときから「伝統工芸とアートの境界線はどこだろう?」という疑問みたいなものを感じてきました。栗林さんの《Erde(エルデ)》はアートなのか、それとも和紙でつくっているから伝統工芸品なのか——。僕のイメージでは「伝統工芸品は基本的に素材がありきでつくる生活用品」で、「アートはアイディアがあって素材を選んでつくるもの」なのですが、これについてはどうお考えですか?
栗林隆: 僕は伝統工芸というものから一番離れたところにいる人間なんです。じゃあ、伝統工芸を重んじていないのかというと、そうではなく、僕は日本人としてとても大事なものだと思っています。
この2つを誰が発信するか、というのが結構大きい気がします。伝統工芸に新しさを取り入れている人はいないわけじゃないんですけど、そこにスポットを当てて、世界に発信して宣伝できる人は少ないわけです。「中田英寿」という人間は、それができる希有な人なんです。会場のみなさんも「中田君が何をしゃべるんだろう?」と期待して来ていると思うんです。そういう人間は限られているので、そういう人がどんどん発信していけばいいと。
じゃあ僕は何をするのかといえば、伝統工芸と一緒に何かをやって云々ということじゃなくて、自分がやることをやる。僕は僕が考えていることをやる。南條さんは南條さんで、中田君は中田君で、それぞれやればいいんじゃないかと思っています。
「なにかできること、ひとつ。」をテーマに様々な活動を続ける「TAKE ACTION」を通して、積極的に新しい価値発信を続ける中田氏。そのプロジェクトのひとつとして始まった「REVALUE NIPPON PROJECT」は日本の伝統・文化をより多くの人に知ってもらうきっかけをつくり、新たな価値を見出すことにより、伝統文化の継承・発展を促すことを目的として、気鋭の工芸作家とアーティストやクリエイターのコラボレーションで作品を作っています。今回、「REVALUE NIPPON PROJECT」2011年メンバーとして参加しているアーティスト栗林隆氏、森美術館館長南條史生氏、そして中田氏が、現在進行形のプロジェクトについて、さらに世界を知る三人から、これからの日本がつないでいくべき伝統・文化、そして新しい価値創造について語ります。
中田英寿×栗林隆×南條史生「伝統が開く日本の未来」 インデックス
-
第1章 伝統工芸に新たな価値を加えてプロデュース
2012年05月07日 (月)
-
第2章 和紙の地球《Erde(エルデ)》誕生秘話
2012年05月08日 (火)
-
第3章 境界へのこだわり、挑戦、困難
2012年05月10日 (木)
-
第4章 “新しさ”のない伝統工芸は“伝統”として生き残れない
2012年05月11日 (金)
-
第5章 一番大事なのは「自分が楽しめるかどうか」
2012年05月14日 (月)
-
第6章 自分の作品を目の前でオークションにかけられる気持ちは…
2012年05月15日 (火)
-
第7章 重厚長大産業からソフト産業へ ~日本の新たなブランド力~
2012年05月17日 (木)
-
第8章 1つひとつ丁寧に&信じることをやり続ける
2012年05月18日 (金)
注目の記事
-
03月26日 (火) 更新
動的書房 ~生物学者・福岡伸一の書棚
目利きの読み手でもある生物学者の福岡伸一による、六本木ヒルズライブラリーのための選書書棚「動的書房」。2024年3月に新たに21冊が並びまし....
-
03月26日 (火) 更新
本には、人生を変え、時代を創るパワーがある!
2023年4月から2024年2月まで全6回で開催したシリーズ「編集者の視点〜時代を共に創る〜」。モデレーターの干場弓子さんと何度も企画会....
シリーズ編集者の視点〜時代を共に創る〜 <編集後記>
-
03月26日 (火) 更新
【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ
「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....
現在募集中のイベント
-
開催日 : 05月08日 (水) 19:00~20:30
多様な個性が育むナラティブパワー
「⾃分の物語(ナラティブ)」を語り、社会との関係性や「私たち」の目指す世界につなげていくことで、何か問題があっても、人々の共感を得て社会を変....
-
開催日 : 05月21日 (火) 12:00~12:45 / 05月21日 (火) 19:00~19:45
ゆる~くつながろう!メンバー雑談
テーマなし!年齢制限なし!ライブラリーメンバーなら誰でも参加できる雑談イベントです。肩の力を抜いて楽しく、そしてリラックスした45分を過ごし....
-
開催日 : 05月02日 (木) 見学ツアー11:00〜12:00/オルガン・プレコンサート13:40~/コンサート14:00〜16:00頃
【メンバー対象イベント】日本フィル&サントリーホール
平日2時のクラシックコンサート「にじクラ~トークと笑顔と、音楽と」のリハーサルを体験しませんか?俳優・高橋克典さんがナビゲーターとなり、上質....
「にじクラ」リハーサル見学・ロビーツアー&昼公演鑑賞